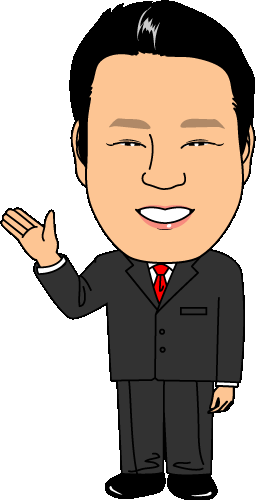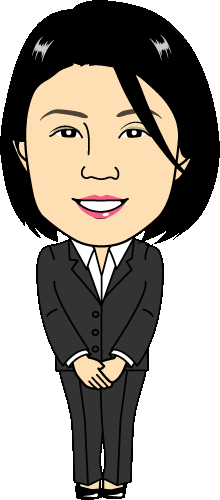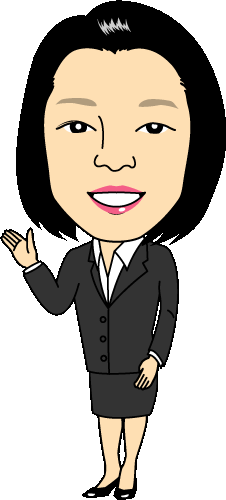スタッフのおすすめ
- 自分の旬で勝負する

柴崎 誠- 何か思いついたときに「これはいける!」と自分の中で吹いて、ものすごく盛り上がることがあります。
何年後かには関心を失っているテーマでも、自分の中で旬、風が吹いているときに勝負をしてみる。
今の自分の勢いを利用するやり方です。
この方法のいいところは、他人を説得しやすいことです。
自分の中で盛り上がっていないものでは熱が入りませんし、他の人の心は動きません。
まずは自分自身がその企画をいいと思っている気持ちが重要です。
「これを広めたい!」という熱があれば、相手も反応します。
つまり「何をやりたいのか?」と聞かれたとき、「これをやりたい!」とはっきり言えるような、少し偏った熱が企画の中に入っているのが大切で、その熱い思いが人を動かします。
- 「立場が変われば」

中澤 正裕- 中国の古典「菜根譚」にこの条はあります。
ここには物事は全て対比することによって、その長短・優劣などを認識するものであると記されています。
これは仕事の上でも人間関係を築く上でも大切なことだと思います。
自身の考えを貫くだけでなく、相手の立場になって考えてみるということです。
独りよがりにならず、常に多角的な視点を持って、物事を捉え、判断していくことを心掛けていければ良いのではないでしょうか。
- 正しいことが人を救うとは限らない

有村 瑞穂- 私は今までいくつかの「忘れられない言葉」をかけられてきました。
そしてあるとき、かけられる言葉の共通点に気が付きました。
何かと言うと、「正しさ」にかかわる言葉です。
その中でも、言われた当時はよく意味が分からなかったのが「正しいことは人を救うとは限らない」でした。
今になって改めてその意味を考えてみると、
「自分が正しいと選択した結果、人に感謝されることもあれば傷つけることもある。安易に正しいと思いこみ行動するのはおそろしい。」
ということだったのではないでしょうか。
「正」の字は、一度止まると書きます。
こわいもの知らずで、猪突猛進な私に「おいおいちょっと待てよ」と言ってくれる、そんな宝物のような言葉です。
- 好調な時こそ、お客さんの方を向く。

丹下 優子- 行列を作っている大繁盛のお店があります。
きっと業績も良いのでしょうが、お店(会社)が好調=そこを訪れるお客様がうれしい!とならない場合もあるようです。
消費者からしたら、それほど混雑していない店内で、程よいタイミングで品物が出てきて、店員さんをある程度独占できる状態が「うれしい状態」ではないでしょうか?
子供服チェーンの西松屋さんは、一定の売上を超えて混み合い出したら、すぐに新店舗展開を企画するそうです。
目指すはガラガラ店舗。
静かな店内でゆっくり買い物をしてほしいそうです。
お客様にも従業員にとってもストレスフリーな状態は、会社の生産性も向上させているとのことです。
好調な時上り調子の時こそ、あらためて、そこを訪れてくれる人の方を向くことを忘れてはならないなと思いました。
- 夢を語るべき人はだれか

工藤 正悟- 子どもを対象とした「将来の労働に対する意識調査」が行われた結果、過半数以上の子どもが働くことに対しネガティブな感情を持っているという結果が出ました。
その調査結果から推察される原因は、両親の会話、テレビの情報から仕事は辛い、大変という情報が子どもに伝わっているからだという可能性が示唆されました。
子どもにとっては社会人の感情を知る数少ない機会の全てにおいて働くこととネガティブな発言がセットになっていることにより、今回の調査結果が出たのではないでしょうか。
会社に置き換えたらどうでしょうか。
社長が夢を語らなかったら社員は何を目指せばよいのでしょうか。
武蔵野というダスキンのレンタル事業を行っている会社は、駅から離れた場所に事務所を構えていた時、経営計画発表会で社員に向かって「想像してください。駅前のビルのテナントに我が社が入っている。」と言い、事実そのビルのテナントに事務所を構えることが出来たそうです。
社長を支える私たちは、社長が夢を描けるように頑張れば届く目標を示さなくてはならないのではないでしょうか。
- 優柔不断は誤った決定よりなお悪い

江原 智恵子- 決めるという行為は単純で〇か×かなど二つに一つを選択するという場合が多いと思います。
それでも人はなかなか決められない場合が多いようです。
その要因は「失敗を恐れる心」があるからで、自分が正解ではない方を選んでしまわないか不安になってしまうのです。
ここで問題なのは多くの人は物事には常に正解があると思い込んでいて、自分は未熟だからその判断を間違ってしまうのではないかと考えてしまうのです。
しかし実際には正解というものがある訳ではなく、ほとんどの判定は後付けです。
成功すれば正解、失敗すれば間違いと言われるだけです。
自分が間違った判断をしてお客様に損をさせてしまわないかが先にたち、なかなか決断できないことがあるかと思います。
でも、そもそも正解などないのだから、常に正解を選択しなければならないと考えずに、その時に一番良いと思ったことを選択し決断することが大事なのだと思います。
- 自分らしい人生を生きて幸せになってほしい。絶対にだよ。

堺 友樹- アメリカの歴史上、他国から直接攻撃されたのは数少ないですが、2001年の今日9月11日のアメリカ同時多発テロもその一つです。
この時飛行機に搭乗していたたくさんの人が家族に向けて電話し、そのメッセージが残っています。
ブライアン・スイーニさんは貿易センタービルに激突したユナイテッド航空に乗っていた人で、妻に搭乗の5分前に電話をし、このメッセージを送りました。
死ぬ直前にも関わらず、相手に感謝や愛の言葉を述べることは本当の人間の姿なのだと。
そして、自分の人生に誇りを持っていたからこその言葉だと思います。
私は今年、38歳になりますが、家族にこのように言えるか分かりません。
同時多発テロのような悲劇を忘れることなく、自分の人生を見つめ直すきっかけにしたいと思います。
- 人を動かすのは 感情揺さぶるストーリー

石原 あい- 何かを人に伝える時、ストーリーとして語ることは非常に効果があると言われています。
ストーリーは人の心を揺さぶる力があり、相手の感情に訴えることにより大きく進展していきます。
例えば、小説やマンガ・映画が良い例ですが、相手にストーリーを思い描かせることは何も長い物語でなくてもよいのです。
一見、仕事とストーリーは関係ないと思うかもしれません。
しかし、ロジックやデータだけでは人は動かない、相手の感情を動かし共感してもらう為には、ストーリーが大きな力を発揮するのだと思います。
- どっちみち100年たてば誰もいない。私も、あなたも、あの人も

土肥 宏行- あるセミナーでこの言葉を聞きました。
講師の方は失敗をしてもそんなこと気にしないでチャレンジしましょう。
という意味を込めて言ったようです。
これを聞いたとき、限られた時間の中で誰かの印象に残るような人生を送るためにはどうすればよいのだろうかと思いました。
ある人が「何のために」「誰のために」という優先順位が重要だと言っています。
では世の中で成功者と言われる人の優先順位はなんだったのか。
ビルゲイツは「世界中の家庭にPCを」と掲げ企業の成長が行動基準でした。
しかし経営を退いた現在は社会貢献活動のために個人資産の95%を用いています。
フェイスブックのザッカーバーグも社会貢献活動のために保有自社株の99%を寄付しているのだそうです。
成功者の行き着いた結論が「自分のために」から「世のため、人のために」だったようです。
今の私は自分のために頑張るしかないのですが、「世のため、人のために」を最優先にと思えるような人間になることが1つの答えなのかなと思いました。
- 一歩先の光景を心に描く

有村 瑞穂- モチベーションとは2つの欲求からから構成されるといわれています。
一つは「期待欲求」そしてもう一つは「成長欲求」です。
モチベーションを高く保ちたい、最高レベルに引き上げたい、そう考えた時「期待欲求」と「成長欲求」の両方を意識する事が大切です。
仮に、今やっている仕事が地味でつまらないと毎日鬱々と過ごしている人がいます。
その人は、モチベーションが全然ないと嘆きます。
一方で、同じ仕事をしているのに生き生きしている人がいるとします。
この違いは何でしょうか。
それは、未来の自分の姿に期待しているかどうかです。
後者の方は、期待欲求が強いのです。
それに加えて後者の方は、小さな目標を自分で設定しそれを達成する事によって成長する手ごたえを感じています。
成長欲求を満たしながら、期待欲求を持ち続ける。
そのためには、常に、一歩先の光景を心に描くことが大切ではないでしょうか。
- 情報について

工藤 正悟- ①情報を取得する速さ
その情報のカテゴリにおいて優位な地位の者ほど情報を早くできる。産業であれば年商が高い経営者、政策であれば国会議員など。ただ、どのカテゴリにおいても富裕層が先に情報を取得する。
②情報の信頼性
情報のカテゴリにおいて優位な地位にいない者ほど、新たに得た情報を正しいと錯覚する。その情報事態の信憑性を確かめる技量が無いからである。
③その情報を誰から聞くか
情報のカテゴリにおいて優位な地位にいない者ほど、誰が話すかに影響される。話し手が自身と同じ感情を代弁してくれたら味方だと認識し、話し手の情報を全て受け入れてしまう。
その情報が本当に正しいかどうかと心象は関係がない。
- NO!と言われることに慣れる

丹下 優子- タレントのGACKTさんがテレビ番組で紹介していた話です。
海外のジムでトレーニングをしていた時のこと。
ある男性が懸垂をする機械の下で腕立て伏せをしていました。
そこに他の男性がやって来て
「そこで懸垂をやりたいから、腕立て伏せは違う場所でやってくれない?」
と言いました。
すると腕立て伏せをしていた男性は「NO!」と言ったそうです。
近くで聞いていたGACKTさんはギョッとしましたが、もっと驚いたのはもう一人の男性の反応でした。
その男性は「OK♪」と言って他の場所へ去って行ったそうです。
私達は、お願い口調で会話をする時も、それが当然とばかりにNOと言われた時の答えを用意していません。
また、固定観念にとらわれすぎて様々な価値観を阻害してしまいがちです。
もっとNOと言われること、言うことに鈍感になってもいいのかなと思う話でした。
- 信じるということ

幕内 彩乃- 元プロボクサーのガッツ石松さんをご存知でしょうか?
元祖おバカタレントなどと云われていますが、実際の彼は非常に常識人で頭も切れる方のようです。
こんな話があります。
ガッツさんは1987年に公開されたスピルバーグ監督の映画『太陽の帝国』に出演しました。
そこでの演技が認められアジア人では初めて全米映画協会の最優秀外国人俳優賞を受賞しました。
受賞のお礼として貧しい地区の孤児院やジムを訪れて、その子供たちにボクシングを指導してその後、こんな話をしたそうです。
「僕はとんでもなく貧乏な生まれで、本当に彼らと全く変わらない育ちだった。ただ一つ違うのは母が自分を信じてくれたこと、お前は馬鹿だし私は貧乏で何もしてやれない。ただお前を信じてやることだけはできる。といつも言ってくれていた。」と
人などそんな簡単に信じられないという人もいるでしょう。
では信じるという事を≪その人の将来の成功と成長を信じる≫というのではいかがでしょうか?
先日の所内フィロソフィー勉強会で、責任感を持たせて仕事を任せると良いとありましたが、これはまさしく≪将来の成功と成長を信じる≫ことだと思いました。
- 恩を贈る

石原 あい- ペイフォワードとは、社会に所属する一人ひとりの人間が互いに無償のボランティアを提供する関係を表す言い回しであり、親切を広げるための運動としてアメリカ等では広く知れ渡っています。
私達日本人はこの無償のボランティアに対しては、見ず知らずの人に親切にされると疑うという習性があるようです。
声をかけることも勇気のいる事です。
この勇気に感謝の気持ちがあるなら素直に親切を受ける勇気も必要です。
このペイフォワードは人と一緒に幸せになることが目的です。
打算や計算もなく、人に優しくして貰って嬉しかったことを人にもしてあげるというシンプルなものが基本にあります。
けなされても笑われても、それでもちょっとやってみようかと思った時、その一瞬の小さな勇気は世界を変えていくものなのかもしれない、という事です。
- 怒りは二次感情

土肥 宏行- 自分の家族、友人、会社の部下に対して怒る時、自分の気持ちが相手にうまく伝わらずギクシャクってないことがあったりしませんか?
怒りが他の感情と性質が違うことが1つの原因だからだそうです。
例えば友人と待ち合わせをしていて、友人が10分たっても、20分たっても来ない。
連絡もとれない。
「何かあったのかな・・心配だな」と思っていたところ30分ぐらいして友人がケロッとした顔で「ごめーん、待った?」。
「待った?じゃないだろ」と爆発して怒る。
この怒りの感情のもとは「心配」でした。
この一時感情の「心配」が相手に伝わっていないため、そんなに怒んなくても・・となるようです。
怒るときは、ただ感情をぶつけるのではなく、この一時感情を相手に伝えると相手も受け入れやすくなります。また怒られた側も怒りそのものを癒すより、元々の感情を理解しようとした方が怒りもおさまりやすくなるそうです。
- 作業は一気に畳みかけるようにやる

柴崎 誠- やるべきことを見つけた場合には一気にやることが成功のポイントで、成果が出る確率を高めたかったら何においてもそうすべきなのだそうです。
成果を出すにはコツコツやることも大事です。
しかし、マンネリが苦手な場合があります。
人は同じことを繰り返していると、良い面でも悪い面でも要領を使うようになります。
初めてやるときに比べると緊張感も消え、全力でしなくなる傾向があります。
そうすると作業に時間がかかりミスも多くなります。
緊張して全力でやった時に比べると成果が出にくくなるのです。
一気に畳みかけるようにやるためにはストップウォッチを使うことです。
ストップウォッチを使うメリットは時間に対する意識が高まることです。
1秒でも違いが分かることから計りはじめると作業をできるだけ早くしようとする心理が働きます。
普通であれば無駄に過ごしてしまう所を少しの時間でもストップウォッチで計っている感覚を持てば時間を有効活用しようと意識をするのではないでしょうか。
- チャレンジして失敗を怖れるよりも、何もしないことを怖れろ

中澤 正裕- これは本田宗一郎さんの言葉です。
成功や失敗についての考え方は人それぞれですが、成功と失敗についての言葉は異人の話の中でもよく出てくると思います。
成功しているから言えるのだろうとすぐ思ってしまうのですが、成功と失敗それぞれ経験をしているから語れる。
普通に考えたら当然ですよね。
歴史に名を残している多くの人は、失敗を失敗だと思わず、成功の糧にするという点で共通しています。
なにかを成し遂げている人は目指しているところがあるからそれに向かうのみで、失敗を失敗だと考えず途中でやめることなくチャレンジしてきたのだと思います。
ですので、失敗を失敗だと思わず、今後取り組んでいきたい、うまく事が進まなかったらやり方を変えたり、工夫して取り組んでいきましょう。
- 「多動力こそが最も重要な能力だ」

幕内 彩乃- ホリエモンこと堀江貴文さんの言葉です。
多動力とはいくつもの異なることを同時にこなす力のことをいいます。
あらゆるものがインターネットにつながって、全業界のタテの壁がなくなった。
業界の壁を軽やかに飛び越えられる越境者にこそチャンスがあるのです。
1つのことをコツコツと、といった学校教育から教え込まれた洗脳を解き、100%取ることに執着せずに80%の知識を様々なジャンルに持つことによってレアな存在となり、あなたの代わりは誰もいないということで、面白い仕事があちこちから舞い込むのです。
こだわりと当たり前を捨てた考え方がとても刺激的でした。
- 嫌なことは良いことの前触れ

江原 智恵子- 嫌なことがおきた時にできるだけ早い段階で気持ちを切り替える方法として「自分の身におきた事の意味付けを変える」ということがあります。
嫌なことがおきた時にそれが嫌な事だと思うからマイナスの感情が生まれてしまうのです。
そんな時に嫌なことは良いことの前触れと思えば気持ちをうまく切り替えるこができるのではないでしょうか?
ある人が通勤途中に鳩のフンが落ちてきて服が汚れてしまったということがあり、嫌な気分になっていたところ、同僚にそのことを話すと、鳩のフン(運)がつくことなんて滅多にないことだと言われ、滅多にないことが起きたんだから何かいいことが起こるかもしれないと考え方を変えたところ、実際にいいことが起こったそうです。
自分の身におきた事の意味付けを変える(マイナスからプラスへ)ことで、今、目の前で起きている嫌なことに対する考え方も変わってくるのでなないでしょうか?
人生は悪いことばかりが続く訳ではありません。
人生楽ありゃ苦もあるさという水戸黄門の歌にもあるように楽しいことと苦しいことが交互にやってくると考えれば前向きな気持ちになれるのではないでしょうか?
- アンテナを立てていると情報が集まる月間MVP

堺 友樹- 当社で経営発表会を行った顧問先の社長が言っていた言葉で、とても感銘を受けました。
こうしたい、ああしたいとなった場合、まず情報を集めると思います。
今は便利な時代なので、インターネットでキーワードを検索すれば、いくらでも情報を集めることができます。
それだけでなく、例えば新聞を読んでいたりしたときでも、普段ならスルーすることもアンテナを立てているとその情報に目が止まり、入手することができます。
自然と自分が思っているものが目に止まる。
それを情報が集まると表現されたのだと思います。
日々アンテナを立てて生活すると、欲しいと思っている情報が手に入ると思いますので、皆さんもそのように生活してみてはいかがでしょうか?
- 小さな実績を一つ一つ増やす

柴崎 誠- 仕事において大事な指標があります。
その中でも事実ほど大事なものはないと実感します。
なぜ事実が大事なのか?
一言でいうと変えられないからです。
事実は一つ、それ以上でもそれ以下でもない、それだけなのです。
事実を評価する観点から別の言葉に置き換えるとしたら「実績」になると思います。
どんなに夢や理想や目標を語ったとしても、その人に実績が無ければ説得力を持ちません。
逆に実績のある人が何かを言ったりやったりすると、また大きな成果を出すのではないかと注目されます。
仕事や人生で成功したいのであれば実績をどんどん積むことではないでしょうか。
今ある環境で全力を尽くし、小さな実績を増やしていくことです。
- ポジティブシンキング

中澤 正裕- 人間がしつこいくらいポジティブに考えろというのは、もともとネガティブで非建設的な考えに陥りやすいからです。
最近は、「ポジティブな考え方」と「明るい考え方」をはき違えて危機的な状況にあっても危機感を抱かなくなっている傾向にあるそうです。
不満や無力感があるのは人間本来の性質です。
それは個人や集団の伸びしろとも言えます。
問題から目を背けず、立ち向かい改善できれば、閉塞感は打破されます。
それがポジティブシンキングの真の意味ではないでしょうか。
- お礼と謝罪はいつもセット

有村 瑞穂- ①お礼と謝罪は、コインの裏と表のような関係。
お礼…「相手がしてくれたこと」に対して述べる
謝罪…「相手にかけた負担」に対して述べる
これをセットで言うことを意識するのはどうでしょうか。
②では、いつ言えばいい?
相手がしてくれたことや相手にかけた負担…気づいたらすぐ!
出来るだけ早く!スピーディーに!!
③どうやって言う?
?まずは相手の負担に気付く、察する。どんな些細な事でも。
自分の「これくらい大丈夫だろう」は、実は大丈夫ではない。
?謝罪の言葉をはっきりと言う。
謝っているつもりでも伝わっていないと意味がない!
?逆の発想をして、「相手がしてくれたこと、フォローしてくれたこと」に対してお礼を述べる
これらを意識し「お礼と謝罪」がしっかりできる社会人になります。
- あなたといると仕事ができるようになった気がする。

丹下 優子- 女優の小池栄子さんのことを、ある俳優さんがこのように言っていました。
「小池さんと一緒に舞台をやると、自分のお芝居がうまくなったような気がするんです!本当はうまくなんかなっていないのに」
とても素敵なことだなあと思いました。
人と接する時、相手を萎縮させてしまうことはあると思いますし、なにも影響を与えないということも簡単です。
でも、「あなたといると何だか仕事ができるようになった気がする」なんて最高の褒め言葉のひとつではないかと思います。
相手の良い面をどんどん引き出せるような仕事ができたらいいと思います。
- 決断をするきっかけ

工藤 正悟- 販売心理学において、人間は感情で物を買うそうです。
損得は情報として理解し、その上で感情と天秤にかけて物を買うのです。
また、感情の中でもマイナスイメージを回避するための感情が一番行動に結び付くそうです。
通販番組でも一度マイナスイメージを出してからおまけとしてプラスイメージを流しています。
迷うという現象は、損得と勘定のジレンマによって発生します。
ビートたけしさんによれば、感情を完全に捨てきれることができれば迷いはなくなるそうです。
感情で判断をするのが良い、損得で判断するのが良い、どちらが良いというわけではありませんが、自らが迷った時や誰かが迷っている時はどんなジレンマなのかを見てあげると良いかもしれません。
感情によるジレンマは他の方法で解決できるかもしれません。
- プラスの言葉を最後に言う

江原 智恵子- 人は強く思っていることを最後に言いたくなるそうです。
例えば、あの人は口は悪いけれど本当は優しい人だと言った場合、優しい人だということを言いたいのだそうです。
逆にあの人は優しいけれど口が悪いと言った場合には口が悪い人だということを言いたいのだそうです。
そして言われた側も後に言われた言葉が心に残るので、前者の場合は優しい人、後者の場合は口が悪い人というイメージが残ってしまうそうです。
この心理をよく考えて、親や先生、上司は人を育てるのだそうです。
親は子供に「あなたは勉強はあまりよくできないけれど友達思いよね」と言った場合や、上司が部下に「君は仕事はまだまだだが、あいさつは社内で一番だ」と言った場合、言われた子供や部下は後に言われた言葉の方が心に残るので、ほめられて嬉しいという気持ちの方が強い為、前半部分も素直に受け入れて、勉強もっと頑張ろうとか仕事頑張ろうという気持ちになるのだそうです。
プラスの言葉で締めくくることで相手が前向きな気持ちになったり、元気になるのではないかと思います。自分がまわりに人に対してどんな言い方をしているのか思い返してみて、プラスの言葉でしめくくるように心がけたいと思います。
- 絶対は絶対にない

堺 友樹- 織田信長が言ったといわれている言葉に「絶対は絶対にない」という言葉があります。
これは、絶対に出来ないということはないという意味と、絶対これで大丈夫と思った時が一番危ないという二つの意味があると言われています。
高校の部活の試合で相手は全国大会常連の選手とやることになりました。
普通に打ち合っては勝つことが出来ないだろうから、1つのポイントを3回までしか打たないとペアで決めて試合に臨みました。
例えミスをしても良いから絶対に4回以上打ち合わないと決めてやった結果は、ファイナルセットで負けてしまいました。
最初から力の差ははっきりしていても絶対に出来ないことはないということを、試合で負けはしましたが感じることが出来ました。
仕事や普段の生活の中で絶対に出来ないことはないんだと心に思って取り組んでいきたいと思いました。
- もう一人の自分を育てる

石原 あい- 物事を誰かに伝える時は独りよがりにならないように、もう一人の自分を持ってそれを育てていくと良いそうです。
例えば、思いついたアイデアを書きだしたとします。
もう一人のあなたがいたら、その人はどう見るでしょうか。
このもう一人の自分は常に自分に突っ込みを入れます。
改善する余地がまだまだある、とアドバイスをくれるというわけです。
これは物事を客観的に見る力にも繋がってくると思います。
一流アスリートに共通する必要条件に「自己を客観視する能力」があるそうです。
確かに、自分の能力を的確に把握できなければ世界では勝てません。
これはスポーツの世界だけではなく、ビジネスマンにとっても不可欠な能力です。
このように客観視する事の重要さは分かりますが、同時に主観と客観のバランスを取ることも大切です。
これを実践するとなると少し難しく感じるので、まずはもう一人の自分を意識する所から始めてみては如何でしょうか。
もう一人の自分なら何というか、自分になら一番ツッコミを入れやすいと思います。
それを育てていくことで、気づく癖がつき客観的な思考が身について行くことになると思います。
- 「永久保証」という意味

土肥 宏行- 最近家族でキャンプでもしたいなと思い、皆の意見を聞いているうちにたどり着いたのがスノーピークというアウトドアメーカー。
まずとにかく値段が高い。
値段は高いが品質には絶対の自信があるようです。
社長の山井さんは自分がユーザーとしてアウトドア用品を使うときに嫌だなと感じるケースは大きく分けて2つあると言ってます。
1つは製品が壊れること。
もう1つは使い勝手が悪いこと。
自分がユーザーだったら嫌だと思う製品を提供することをしてはいけない。
だからそんなものづくりをしないと決めたそうです。
そしてユーザーにとことん誠実に向きあった結果生まれたサービスが「永久保証」みたいです。
製造上の欠陥だったらいつまでも保証がきくんです。
保証期間ってだいたい1、2年ですよね。
そこを永久。たんなるユーザーへのサービスというだけでなく、この会社の品質の価値を、絶対的な自信を、この4文字に詰め込んでいるような気がして強烈な印象をうけました。
- 仕事の種類を考える

工藤 正悟- 仕事は4つの分類に分ける事ができると言われています。
①緊急度:低、重要度:低
他の人にやってもらえるなら振った方がよい領域。出来れば無くしたい。
②緊急度:高、重要度:低
時間を割かずに消化すべき領域。短い時間でいかにこなすか。
③緊急度:低、重要度:高
一番時間を割くべき領域。能力向上のための勉強などが挙げられる。業績の高いセールスマンが最も時間を割いている部分。
④緊急度:高、重要度:高
とにかくすぐ取り組んで対応すべき領域。顧客対応など。重要度が低い仕事に割く時間をいかに減らして、重要度が高い仕事に取り組むか、自分の今の仕事の時間配分はどうなっているか考えながら自分をマネジメントしてみてはいかがでしょうか。
- 気持のいい「はい」を言えない人は何事に対しても腰が重い

仲吉 美香子- これは厳しいマナーで有名な平林都さんの言葉です。
一時期テレビ出演などで大変有名になった方ですが、この方はどんなお客様に対しても最高のマナーを守って対応するという事を教えていらっしゃいます。
以前テレビでお菓子屋さんの従業員に対して接遇を教える中で、実際に平林さんが接客をされていましたが、低姿勢さや丁寧さは有名ホテルのような対応でした。
客単価を考えても有名ホテルとお菓子屋さんでは全く違いますし客層もまた変わってくると思います。
しかし「お菓子屋さんならこの程度のサービスでいいだろう」というところに有名ホテルのような接客をプラスアルファで付ける事によりお客様の満足度は良くなりますし客単価のアップも見込めるかもしれません。
気持ちのいい「はい」もこうした平林さんの考え方からきているんだと思います。
確かに「はい」の言い方一つとっても印象は全く変わります。
元気よく「はい」と返事をされている方の方がキビキビとした動きをしているような気がします。
これは電話対応で生かせると思います。
気持ちにいい返事をする事により印象もだいぶ変わってきますのでこれから心がけていきたいと思います。
- 前向きになる子の親が実践する3つの声掛け

幕内 彩乃- ①GOOD NEWSを毎日語り合う
人間はGOODとBAD,またはプラスとマイナスを同時に考えることは出来ないので、GOOD NEWSを語り合うことによって、最後は必然的に気持ちはGOODに支配され、それが習慣になると前向きな性格に変わっていきます。
②褒めるのではなく認める
前向きにさせるには自分は出来る!という自己肯定感を高めるようにすることだそうで、ただ褒めるだけだとマンネリ化し、褒める度合いを引き上げざるを得なくなりますが、認めるのは単純なだけに飽きがこず、人をモチベートするには最適な方法です
③ではどうしたらいいだろう?HOWを口癖にする
失敗は自分が一番よく分かっています。それに対してなぜWHYで聞かれてもやる気が削がれるだけ。そこで根気よくHOWの提案をしてくれればその瞬間から思考は前向きになります。子供のみならず、人を育てるには効果のある声掛けではないでしょうか?
- 「私は今日が人生最後の日だと思って生きよう」

野本 理恵- 世界最強の商人の著者、オグマンディーノ氏の言葉です。
111ページの短い小説の中に、成功10の巻物としてポイントが書かれています。
その中の一つ。
私は今日が人生最後の日だと思って生きようという言葉。
明日があれば。
またいつか会うだろうから。
明日から。と思うことは日々の中で沢山ありますが、人生という長い時間で見た時に大きな成果の違いです。
仕事でもプライベートでも今日が最後の日だとしたら、と考えると優先順位ややりきる心構えも変わってくると思います。
今日会うお客様が最後だとしたら、
今日、見送った家族が最後だとしたら、そう考えて、すべてのものを大切にすることが多いと思います。
営業というと一部の人というイメージがありますが、
日常生活でも仕事でも人とかかわる限り、「営業的な要素」は誰しも持っています。すべての人により濃い今日を送るためのヒントになると思いましたので紹介しました。
- 素直=行動のスピード

土肥 宏行- 子供の成長ってものすごく早いなと感じます。
こんなこと話すようになったんだとか、こんなことできるようになったんだと日々驚きです。
子供は、良いなって思うことを素直にすぐにやれます。
でも我々大人はどうでしょう。
ある統計ですが、セミナーなど勉強会で本をすすめられた時、すぐに買い読む人3%、1週間後に買いに行く人は87%、買わない人10%という比率になるそうです。
その時は良いなと思ってもなかなか行動に移れない。
結局できる人とそうじゃない人の違いってこういうところに出るんじゃないかな。
やる前に障害を考えてやらない、出遅れる。
これ良いよってすすめられたら、すぐに取り入れようとする。
その素直さのスピードが後になって大きな差になってくるように思えます。
- 今行うべきかどうかは「間」で考える

柴崎 誠- 物事を行うタイミングについて考えたことありますか。
時間こそ最大の武器戦略的にあえて時間稼ぎをすることもあります。
なんでも素早く行えばいいというわけではありません。
場合によっては少し間を置いてから取り掛かった方がいいものもあります。
忙しい中では時間が何よりも大切ですし、心配なことであれば手っ取り早く片付けてしまいたくなります。
しかしちょっと立ち止まり、それは今やるべきこと何かを考えてみることが必要なのだそうです。
「間」という言葉には「隙間」「ひま」などの意味がありますが、「ちょうどよい折」「ころあい」といった意味もあります。
舞踊や演劇などでは動作やセリフの時間的間隔のことをいい、リズムやテンポの意味として用いることがあります。
間を置いた方が良い例として、人間関係でトラブルが起こってしまった場合には少し時間を置いた方が良いそうです。
カッとしたまま自分の意見を言ってしまえばその場はスッキリするかもしれませんが、それは自己満足に過ぎません。
言われた相手の気分を害することになります。
しばらく時間を置くと自分の気持ちが整理されてお互いのことを客観的に考えられるようになり、円満に解決することになるのではないでしょうか。
- 注目すると成果があがる

丹下 優子- アメリカの自動車工場で、労働者の生産性を向上させるための実験が行われました。
組立てラインで働く女性達を対象とした実験です。
工場内を明るくしたり暗くしたり、どんな環境で一番生産性が上がるのかを調べると、なんとどんな環境下でも、実験前より効率があがり欠陥品も減るという結果がでました。
この結果をもとに、女性達に「どうしてこのような結果が出たと思いますか?」とたずねると、ひとりの女性がこう応えました。
「私は、何かに選ばれたこともないし、工場労働者という立場以外の扱いを受けたことがない。だから今回の実験の被験者に選ばれたことがとても誇らしかったのです!」
注目されることで自分が重要な存在になったような気がして、いつも以上精を出した、とのことでした。
注目される仕事は、注目されない仕事より効果が期待できる・・・という研究結果が証明されているそうです。
仕事や家庭においては、あなたに注目していますよ、あなたは大切な人ですよと接することで、大きな成果に導くことができるかもしれません。
自分の仕事に対しては、自分が一番関心を持ち、自信と誇りをもって取り組むことで、結果をつくり出すことができるのではないでしょうか。
- よく考える。しかし考えすぎない。

江原 智恵子- 知人にプレゼントを贈ろうと思ったときに、何を送ったら相手に喜んでもらえるか一生懸命考えることは良いことだと思いますが、あまり考えすぎると何を贈ってよいのかわからなくなってしまうということがあるのではないでしょうか?
よく考えるということはとても大事なことですが、あまり突き詰めて考えすぎるとかえって迷いが生ずることにつながってしまうのではないでしょうか?
仕事にしても何か目標と立ててそれを達成しようとする場合においても、「よく考えて行動する」ことは大切ですが、「突き詰めて考えすぎる」とかえって迷いが生じ、心も乱れ、何をしてよいのかわからなくなってしまいます。
人生にはこれが絶対に正しい答えだということはありません。
又、100%完璧だということはないということをよく理解して、「よく考える。しかし、考えすぎない。」という、ちょうどいいバランスを保ちながら生きていくことが、あまり悩まずに平常心でいられる秘訣ではないかと思います。
平常心でいるということは、まわりの状況に必要以上に影響されずに動じない心でいることだと思います。
平常心でいることができれば、色々な場面で普段どおりの力を発揮することができると思います。
よく考える。
しかし考えすぎないように心がけ、なるべく平常心でいられるようにしたいと思います。
- 体を動かすこと

堺 友樹- 長い時間机に座っていると、体が硬くなってしまいます。
最近、ストレッチ専門店というところに通っています。
体が硬くなってしまうと血流も悪くなり、色々なところに不具合が出てきます。
そのお店では、ストレッチをすることによって体の筋肉をほぐしていきます。
これを繰り返していると、人間の体は3ヶ月くらいすると慣れてくるらしいです。
私自身、ふくらはぎなどとても硬く、一日中歩くと足が痛くなってしまいます。
しかし、ストレッチをすることによってその痛みを感じにくくなってきて、自分でもこの効果を実感しています。
普段の生活の中で体を動かすことをこれからもやっていきたいと思います。
- 自立とは依存先を増やす事

石原 あい- 一般的に、自立の反対語は依存であると勘違いされていますが、人間はものであったり人であったり様々なものに依存をしないと生きてはいけません。
依存先を増やし一つ一つの依存度を浅くすると、何にも依存していないかのように錯覚できます。
実は、膨大なものに依存しているのに、私は何にも依存していないと感じられる状態こそが「自立」と言われる状態なのだろう、という事です。
また、子育ての自立を目指すならむしろ依存先を増やす必要があり、子供の自立とは、親以外の依存先を開拓する作業である、と述べられていました。
自立に対しての考えは人それぞれで色々な意見があるかと思います。
Give&Takeという言葉があるように、双方で支え合って初めて自立した関係が築けるのだと思いました。
- お客様が満足を感じるための条件

工藤 正悟- アメリカのマーケッター、ブライアン・トレーシーいわく、お客様が満足を感じるには条件が4つあるそうです。
①お客様自身が、サービスを選択したという実感があること。実際には誘導されていたとしても、選択したという実感があれば十分だそうです。
②お客様が労力をかける。サービスの効果を得るために、お客様自身にも労力をかえてもらう方が、効果に対する思い入れ、意気込みが増すそうです。
③お客様がサービスの効果を実感する。具体的な数字、変化をお客様自身が感じ取る必要があります。
④お客様がサービスをシェアできる。どんなサービスか、どんな効果があったかを知人、友人にシェアすることです。
この4つの条件は決して困難なことではありません。
各条件を通過するようにお客様と接することを心がけましょう。
- 早寝早起きについて

仲吉 美香子- 早寝早起きは健康に良いと昔から言われていますが、常日頃から気を付けている人は少ないのではないでしょうか。
早寝早起きのメリットはゴールデンタイム(夜10時~深夜2時頃)と呼ばれている時間にはホルモンが分泌されたり身体の疲れを癒したりと身体の中で大きな変化の現れる時間です。
つまり、この時間に しっかり睡眠をとっていれば子供は成長していく事が出来ますし大人も身体の調子が整えられたり美容面で言えば肌がきれいになったりするそうです。
逆にこの時間帯に夜更かしをするとホルモンが分泌されることもないので、身体は十分調整できなくなったりして免疫力の低下、寝不足による集中力の低下、さらには肥満になりやすいという事が言えます。
ただ、私たちの生活スタイルやその人自身のタイプ(朝型・夜型)を考慮してみると一概には早寝早起きがいいとは言えないので、早寝早起きが出来る環境や状態にあるなら取り入れていきましょう。
- 目先の欲望に負けない

幕内 彩乃- こんなうれしい提案があったとしたら、どちらを選びますか?
①今日ここで1万円をあげます。
②1年後にあなたに1万1千円をあげます。
1年後なんて先の事は分からないからと①を選んだ人が多いのではないでしょうか?
人はどうしても目先の利益を優先しがちで、我慢して得られる将来の価値を実際の価値より小さく感じる傾向が強いようです。
アメリカのスタンフォード大学で行われた「マシュマロ実験」によると(詳細割愛)マシュマロを食べずに我慢できた子供のグループは、我慢できなかったグループに比べ、周囲から優秀という評価を得、大学進学適正試験SATの点数も高かったという事です。
目先の欲望に負けないで、将来の価値に目を向けるように心がけると、今本当にやるべきことと同時に将来のビジョンも見えてくるのではないかと思いました。
- 誰にも負けない努力について

野本 理恵- 会社の経営理念やビジョンは社員と共有することは大切ですが、それだけで成果がでるものではありません。
京セラのフィロソフィーを例に取るとこれが組織の成果の要であるようにとらえられる人がいるように思いますが、これには誰にも負けない努力極限までの経験を行った人にしか、この本当に意味はわからないということです。
経営理念やビジョンはその人の仕事へ努力や意識によって受け止め方が大きく違います。
同じように「大事なことだ、共感できる」と思っても、日々の仕事に努力が伴わなければ、ただの自己満足や意識だけが高く成長にはかえって邪魔になるかもしれません。
本当にお腹に落ちる努力をしている、上位5%の人間に少しでも近づけるように日々、仕事に当たりたいと思います。
- モチベーションのポイントを工夫する

土肥 宏行- 大事だと思っていても続けられないものって誰にでもあると思います。
例えばスポーツジム通い。
適度な運動は必要だからと始めてはみたものの、いつの間に通わなくなっていました。
その問題に対してホリエモンこと堀江さんは「ジムの近所に住む」と言っています。
人間は怠惰な生き物。
だからシンプルに、「通うの面倒くさい」を排除して、行動を変えようとしているのです。
またこうも言っています。
「美人のトレーナーをつける」。
ジムに行く目的自体を置き換えてしまう。
美人やイケメン目当てに通うんだから楽しいですよね。
大変なことを気軽に行けて楽しいことに変換させた今回のように、モチベーションの下がることを排除し、モチベーションが上がるポイントをいくつも用意することが、嫌なこと大変なことを続けるコツなんだと思います。
- 面ではなくたくさんの点を想像する

柴崎 誠- どんな仕事に就いても働く人にとって大事な要素の一つに想像力が挙げられます。
考えを重ねていろいろなアイデアを生み出してもそれだけでは仕事になりません。
思いつきのその先にあるものは何かを考え行動に移していく。
その際にはアイデアを例えてみることが有効なのだそうです。
人に説明するときに「例えば~」と話を展開することがよくあります。
その「例えば」をいろいろなバリエーションでできる限りくっつけてみることです。
「このアイデアは食べ物に例えるとどういうものか?」この例えはどんなものでもいいそうです。
例え話を用いた説明を繰り返すとアイデアはどんどん具体化して自分の中でも整理がついてきます。
理解が深まり、アイデアを実行に移す手がかりが見つかるはずです。
また、例え話を作る際のコツは目の前にある物事の真ん中ばかりを考えないこと。
核心ではなく周辺には何があるのかを想像してみるのが効果的なのだそうです。
- 正しい情報だけが効果をうむとは限らない

丹下 優子- A先生とB先生という二人のお医者さんがいます。
どちらも真面目な先生ですが、風邪薬を渡す時の対応が違いました。
A先生「この薬をのめば必ずよくなりますからね!」
B先生「この薬が効く確率は80%、副作用が出る可能性も10%あります・・・」
どちらのお医者さんに診てもらうほうが元気になりそうですか?
正確さという意味では間違いなくB先生ですが、病気がよくなりたいと期待する患者に対して、期待に応えている(効果を出している)のはA先生ではないでしょうか。
私達のような仕事で大切なことのひとつは、正確さを背景にした相手に対する効果であり、相手に確信と勇気を持ってもらえる能力を養うことだそうです。
毎日様々な「相手」と向き合いますが、なんだか元気が出てきた!やれそうな気がする!と思ってもらえるような対応をこころがけたいと思います。