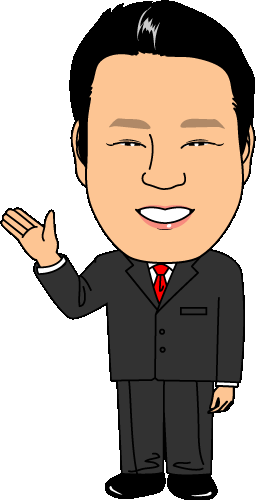スタッフのおすすめ
- 今度とお化けは来た試しがない

堺 友樹『今度、旅行に行こう』『今度、飲みに行こう』などのように『今度』と使われることがありますが、本当にそのようになることはほとんどありません。お化けと一緒で、来た試しがないとうちでは言われます。
今度という言葉はよく使われますが、言った相手も覚えていないので、うちでは期日を設けることをしています。
例えば、今度という言葉を9月20日のように具体的に設けることもあれば、年末とか時期で設定することもあります。
具体的な日を設定すると、言った方も忘れないようになるので、うちではそのようにしています。
- 完璧主義者の危険性

山村 佳恵完璧主義であることの弊害には3つあるという研究結果がありました。
- 少しでも駄目だと思ったら補器してしまう
- 自分のキャパシティーを超えた作業内容を設定してしまう
- やるべきことを先延ばしにしてしまう
・・・何れもやるからには完璧を目指さなければという意識が原因となっているとのことです。
私自身完璧主義者であるとは思っていませんでしたが、いくつか当てはまることがありました。
解決方法として小さくはじめてみる、そして作業を時間で区切ることなどが有効とのことですので、意識して実行してみようと思います。
- 努力の仕方を変える

中澤 正裕仕事をしている人は基本的に全員頑張っています。
時に努力が実を結ばないこともあるでしょう。
そこで、努力の方法を変える人と、努力を続ける人の大きく分けると2パターンの人間がいます。
論理的に物事を考え、ダメだった時に何が悪かったのか思考し、どのように軌道修正をするかを考える人間、柔軟に対応して、事態を良い方向へ向かわせる能力が必要ではないでしょうか。
- 本物が持つエネルギー

丹下 優子何でも100円ショップでも買えますし、よくできたコピー品もあります。
でも本物にはやはりそれなりのエネルギーがあるそうです。
良質な物を身に着けていると背筋が伸びるということがありますが、人の心に良い影響を及ぼす良いエネルギーです。
高いエネルギーの物を周りに置くと仕事の能率もUPするそうですよ!
安いものがダメ・・・という訳では決してありませんが、手間暇かかった逸品を一つふたつ持って、修理をしながら10年20年と大切に使い続けるのもいいなぁと思います。
- 情報のタコツボ化と購買までのパルス消費

工藤 正悟SNSの発達により購買ステップに変化が訪れた。
- 情報のタコツボ化
ほしい情報だけが日常的に与えられる。
自分が求めているものに関連している情報に囲まれる。 - 購買までのパルス消費
探る、考えるを繰り返し突発的にこれだと思ったものを衝動的に購入する。ピンときたら買う。
日常的な消費がパルス消費であり、めったに買わないものが衝動買い、異なる。
パルス消費にはピンとくるきっかけが必要です。googleが提唱するパルス消費を誘発するトリガー
- 安全性
- for me 私にあったものが欲しい
- お得なものがほしい
- 人気・評価の高いものがほしい
- ワクワクするものが欲しい
新商品、めずらしいもの。 - 手軽に買いたい 労力をかけたくない
- 情報のタコツボ化
- 希望を抱ける脳

竹内 純子人は新しいことをやろうとする時、リスクを感じて不安を覚える。これは生命を維持する上ではかかせないが、成功している人は「予期せぬことが起こっても【なんとかなるのでは】と考えられる」=「希望を抱ける脳をもっている」という特徴がある。
例えばビルゲイツは「生来の楽観主義者」で、「どうすればできるか」だけを考えて将来を悲観することがなかったそうだ。また、予期せぬ不確定な要素を取り入れるために、専門ではない分野の本を集中して読む「シンク・ウィーク」という習慣を持っている。
コロナの影響で日々状況が変わるが、この「希望を抱ける脳」で考えると初めての経験をマイナスではなくプラスととることができ、新しい働き方やビジネスが生まれてくるのだと思う。
- エンターテイメントを提供する

江原 智恵子エンターテイメントというと芸能界など何か自分たちとは違った世界の話だと思っていましたが、どんな仕事においてもエンターテイメントの要素が必要ではないか思います。
エンターテイメントの根底にあるのは「相手を喜ばせること」だと思います。今日会ったお客様に少しでも喜んでいただくことを念頭に置くことで、いつもの仕事も違った視点から見られるようになるのではないかと思います。
相手に少しでも明るく前向きな気持ちになっていただけることがエンターテイメントの力だと思いますので、自分たちの仕事におけるエンターテイメントを提供できるように心がけたいと思います。
- 言葉は何のために使うのか?

土肥 宏行言葉を何のために使うのか。
- 自分の意見を伝えるため
- 相手を幸せにするため
- 自分をわかってもらうため
- 相手をもっと理解するため
- その場をもりあげるため
- 相手にミスなどを気づかせるため。
普段コミュニケーションをとる時に皆さんはどれを重視していますか。
選択肢の中で自分が重視しているものが、あなたの強みであり、傾向が強すぎると弱みにもなります。
自分の特長をわかっていると、軌道修正がしやすいと思われます。
今まで目の前で相手の反応を見れたものから、ZOOMなど機会が増えるとより言葉が重要となると思います。
- 常識は常々変わる

堺 友樹- 以前は常識であったことも変化をしています。
鎌倉幕府の開設年のように、1192年(いい国)が常識であったものが、今では1185年に変わっています。
IT技術の進歩により、コロナの影響も相まって、仕事は会社に出社して行うものという常識も一気に覆りました。
今現在常識と言われているものも、来月には非常識になってしまう可能性がある世の中です。
その変化に対して上手く対応していかなければならないでしょう。
- 探し物は年間150時間のムダ

山村 佳恵- ビジネスパーソンは年間約150時間をモノを探すことに費やしているそうです。
ある会社では探し物の時間を無駄時間として削減する試みを行っていて、2段階で「片付け」を行っているそうです。
第一段階◆一年間以上使用していない備品は捨てるなどルールを作り、それに乗っ取って不用品をどんどん廃棄する。
第二段階◆必ず誰もが元に戻せる仕組みづくりをする。例えばハサミの枠に切り取った型紙を置き場所に配置する等といった工夫をする。
効率良く仕事をするための環境整備としてぜひお勧めします。
- ずらして価値を再定義する

中澤 正裕- 商品やサービスが売れなくなった時に使える方法です。
当初は自己啓発書として出版していた本を児童向けコーナーに移動したら、ベストセラーが生まれました。
当たり前のことも一度「ずらして」見直すと新しい価値が生まれる可能性があります。ポイントは、思い込みや経験値などを一度捨て、ターゲットを限定せず、ずらせる場所や人を探すこと。ユーザーの声をよく聞き、よく観察すること。
新しいものをつくるだけだけがイノベーションではなく、「価値の再定義」でイノベーションを起こすこともできるのです。
- 信頼関係とは安心感である

江原 智恵子- 信頼関係とは一言で言うと安心感だと思います。
信頼関係は時間をかけて少しずつ構築するものですが少しの疑念が生じると簡単に崩れてしまうものです。
特にレスポンスが遅いのはよくありません。
お客様からの質問にすぐに回答が難しい場合でも、とにかく何かしらの反応を返すことが大事です。
お客様は回答を早く求めているではなく、反応がないことに不安を感じてしまうものだからです。
信頼関係を築くためには相手の立場になって考えることが大事です。
- 相手も自分もストレスフリーを目指す

丹下 優子- ある程度のストレスは物事のモチベーションとなることがありますが、必要以上に溜め込むと生産性を落とすことにつながります。
仕事を先延ばしにするなどの自分のクセを見直し、自分で自分にストレスを作り出さないよう努めたいです。
また、この人と仕事をしているととても気持ちがいいな、という人がいます。
相手にとってどんなことがストレスになっているかを想像しながら、小さなことでも改善していけたら、仕事の質が上がるのではないかと思います。
- 事実をそのまま受け入れる

丹下 優子- 篠山紀信さんの人生が変わったきっかけがあるそうです。
それはリオのカーニバルへ取材に行った時のこと。
道の反対側に渡ろうと、パレードを無理やり横切ろうとしても何度も跳ね返されてしまった篠山さん。
そんな時、半ばやけくそでサンバのパレードに参加し始めたところ、ス~と向こう側に渡れたのだそうです。
「あ、こういうことなんだ。全部受け入れちゃえばいいの。」
というのは篠山さんの言葉です。
反発するのではなく、まずは全部を受け入れることで、道が開けることがあるのかもしれません。
- 2:3:0の法則

工藤 正悟- コロナによってテレワークが普及。
社員一人一人に細かなタスクを課し管理する会社が増え、組織はより文鎮型になりました。
これにより、以下の事象が発生しました。
①一人一人の働きぶりが一目瞭然に
②管理職が不要に
2:6:2の法則の中間層には管理職も含まれます。
中間層の6のうち管理職やパフォーマンスが低い社員、そして下位の2が不要となり、2:3:0の時代になると言われています。
- プロスポーツ選手の勘の凄さ

竹内 純子- プロスポーツ選手が自分の勘でたどりついた練習法が、最新のスポーツ心理学で正しいことがわかってきています。
サッカーの中田選手は、PK練習であえて失敗を蓄積することで、緊張で力んだ時でもゴールを決められる状態を作っていました。
野球の長嶋さんは、大リーグに行った松井選手のスイング練習の音を電話で聞きアドバイス。
ベストスイングをフォームではなく音で判断でき、擬音語や擬態語で理解しあえるレベルの選手ならではのエピソードだと思います。
- 信頼関係とは安心感である

江原 智恵子- 信頼関係とは一言で言うと安心感だと思います。
信頼関係は時間をかけて少しずつ構築するものですが少しの疑念が生じると簡単に崩れてしまうものです。
特にレスポンスが遅いのはよくありません。
お客様からの質問にすぐに回答が難しい場合でも、とにかく何かしらの反応を返すことが大事です。
お客様は回答を早く求めているではなく、反応がないことに不安を感じてしまうものだからです。
信頼関係を築くためには相手の立場になって考えることが大事です。
- マイナスをゼロではなく、いかにプラスにして帰ってもらうか

土肥 宏行- 佐藤義人さんは昨年のラグビーW杯を裏で支えた名トレーナー。
なぜ多くいるトレーナーから彼が選ばれるのか?
1つは彼の施術の「即効性」ではないかと思う。
ラグビーのW杯は3日で次の試合になる。
怪我をしている選手を次の試合までに送り出してきた。
そして彼の信念。
痛みをとるだけでなく、マイナスをゼロではなく、いかにプラスにして帰ってもらうか。
治すだけではなく、ケガをしないためのトレーニング。
それを伝えていく彼の姿、気持ちに信頼がうまれているのではないか。
- あたり前だと思っていることを見直す

江原 智恵子- とんかつチェーンの「かつや」をご存知でしょうか?「かつや」の特徴として“安い”というのがありますが、安さ実現のために失くした4つのあたり前があるそうです。その一つに「あったらいいな」は「なくていい」があります。とんかつ屋特有のキャベツ・ごはんのおかわり自由はなし。漬物、小鉢もなし。千切りキャベツのいろどりのにんじんもなし。お皿の隅に添えるからしもなし。漬物とからしは食べたい人が好きなだけ食べられるようにテーブルに置くようにした。これだけでかなりの無駄がなくなったそうです。従来のとんかつ屋特有のあたり前を見直すことで安くておいしいとんかつを提供できるようになったそうです。私たちの業界においても、あたり前だと思ってやっていることが実は相手の側からみたら「なくてもいいこと」がないかを考え見直すことで無駄がなくせるのではないでしょうか?逆に必要なもの、相手に求められていることは何なのかを考え、それに応えるために集中した時間を作ることが重要だと思います。働き方改革に関連してAI化が進むこれからの時代における仕事の仕方にもつながってくると思います。
- ピンチの時のリラックス

土肥 宏行- ピンチの時に焦ってしまい、スポーツや今なら受験などでいつも通りの実力が発揮できないような場面は多くあると思います。もしピンチの時に焦らず、逆にリラックスできるようになる。それが日々の訓練でできるようになればいいなと思います。例えば梅干しを食べると唾液が出る。すっぱいから当たり前なのですが梅干しを食べるときにいつも鈴の音が鳴っていたら、うめぼしがなくても鈴の音が鳴るだけで唾液がでてしまうらしいのです。反射というらしいのですが、これを応用します。いつもリラックスしている状態の時に、常に何かをする。例えば消しゴムを握るとか、自分の鼻をさわるとか。それを繰り返していくと、いつか消しゴムを握ると、自分の鼻をさわるとリラックスした状態になれるのだとか。ここぞという時に頼れる武器になるかもしれませんね。
漫才や落語が好きですが、卓越した話術には私たちが学ぶべきところがあるように感じます。笑いのセオリーとして“フリ”があり“オチ”があります。このフリを効果的に使えないと笑いをとるというオチにはつながりません。話の構成、どこでどのフレーズを使うか・・など、話の組み立てはとても計算されてものなのではないかと思います。もうひとつ見習うべきは練習量。時に数年ぶりにやったネタなんていう時も完璧に笑わせます。これは、肌にしみつくほどの練習があるからなのではないかと思います。私たちも、相手を説得したり納得させたりする場面があります。どのように話をしたら相手はうんと言ってくれるのか、そのためにはこう言われたらこう切り返すという、反射的に反応できるくらいのシミュレーションを繰り返したか、笑いという成果同様、相手に影響を与える(おとす)方法努力は、見習う点があるように思います。
- 声を出す

堺 友樹- 日本ではマスクをして応対すると失礼にあたると言われています。ですが昨今、マスクをしていないと失礼にあたるそうです。マスクをすると、表情が見えない・声が聞こえにくいなどの理由で失礼にあたるようです。
マスクをしている場合、いつもどおりの大きさで声を出すと相手に聞こえにくいです。いつもより一段回、大きい声を出すことによって、相手にも聞こえるようになり、免疫力も高まり、病気の予防にも繋がります。
いつもより一段回大きな声を出して話をするようにしてみてはいかがでしょうか?
- 自分をほめる!

山村 佳恵- 新しく始めるチャレンジはなかなか長続きしません。とっても簡単で短時間でできる解決方法をご紹介します。それは寝る前にその日自分が頑張ったことを一つ見つけ出し、「よくやった!」と自分をほめてあげる事。ただこれだけで、今自分がチャレンジしている事に対し、辛い・・・苦しい・・・という意識から、楽しい!もっと続けてみよう!という前向きな意識に変えていくことができます。いわゆる世の成功者と言われている人々は楽しくて夢中で一つのことを続けた結果として成功がついてきます。「自分をほめる」という非常にシンプルな方法ですが、チャレンジに対して前向きに継続することで誰でも一つの事を極める成功者になれる可能性があるのです。
- ヒントは普段の生活の中に

土肥 宏行- 病院で働いている看護師さん。大変忙しく早出や残業が常態化しているイメージがありますが、ある取り組み1つで残業時間を1/5までにした熊本の病院があります。その取り組みとは、日勤の制服を赤、夜勤の制服を緑にしたことです。これにより勤務終了が近い人には医師から新たな仕事の声掛けしないという判断がしやすくなりました。また残業すると色違いの制服が目立ち、個々人も定時退勤を心掛けるようになったそうです。たったこれだけで労務が改善され、働きやすい職場となり採用面でもプラスになっているのだとか。この取り組みは前院長が発案しました。攻撃の時は攻撃の人が出てきて、守備をする時は守備の人が出てくる攻守で分業をしているアメリカンフットボールからヒントを得たのです。解決策は何も仕事の中からだけではなく、普段の生活の中にもあるのかもしれませんね。
- お笑い芸人の話術に学ぶ

丹下 優子- 漫才や落語が好きですが、卓越した話術には私たちが学ぶべきところがあるように感じます。笑いのセオリーとして“フリ”があり“オチ”があります。このフリを効果的に使えないと笑いをとるというオチにはつながりません。話の構成、どこでどのフレーズを使うか・・など、話の組み立てはとても計算されてものなのではないかと思います。もうひとつ見習うべきは練習量。時に数年ぶりにやったネタなんていう時も完璧に笑わせます。これは、肌にしみつくほどの練習があるからなのではないかと思います。私たちも、相手を説得したり納得させたりする場面があります。どのように話をしたら相手はうんと言ってくれるのか、そのためにはこう言われたらこう切り返すという、反射的に反応できるくらいのシミュレーションを繰り返したか、笑いという成果同様、相手に影響を与える(おとす)方法努力は、見習う点があるように思います。
- 見た目と年収について

工藤 正悟- イケメンと不細工だと年収に17%も差があるそうです。
顔の作りはしょうがないとして、立ち振る舞いなど相手からの印象に気を配ることはできます。NYのキャリアは見た目にお金を使うそうですが、服装や身に着けるものよりも立ち振る舞いや表情などのレクチャーにお金を使うらしいです。
日本人が気をつけるべきポイントは
・表情筋の使い方を意識する
・姿勢に気をつける(猫背になりがち)
猫背は謙虚に見えて日本人には馴染みやすいという考えもあるらしいですが、我々は先生業なので自信があるように見せる必要があります。
意識されてはいかがでしょうか。
ちなみに、太っているかどうかと年収に相関関係はないらしいです。
- 「ユニバーサル日本語」の使い方

竹内 純子- ユニバーサルとは、「一般的」なという意味で、「誰もが読みやすい・理解しやすい日本語」を「ユニバーサル日本語」と呼んでいます。
ポイントは整理すると3つあります。
・読み手の気持ちを考える…中学3年生の自分」が「予備知識がなくても最後まで読み切れて理解できる文章
・一文を短く簡単にする…1文は長くても100字くらい(Wordで2行半以下)
・文字のバランスを考えて使う…漢字が多いときは、あえてひらがな・カタカナにする、「」でくくる、接続詞を入れるなどくふうする。
Webの場合は一つの記事で4000字をオーバーすると読者にまず読んでもらえなくなるそうです。文字数が多い場合は前後2本に分けるなどの工夫が必要です。
有名人など特別な場合を除いては、多くても1記事2000〜3000文字でとどめるのがおすすめとのことでした。
- 最適は見つけるものではなく創るもの

中澤 正裕- みなさんは、「自分にとって最適な仕事は何か」を把握されていますでしょうか。
少なくとも、最適な仕事を探すのは非常に困難です。
それは、世の中には数え切れないくらいの会社や部署があり、その中にも数々の仕事が存在するからです。
ですから、入社してから最適が見つかる方が不自然です。
だからと言って「今、自分の前にある仕事をそのまま受け入れろ」と言いたいわけではありません。
面白い仕事を探すのではなく、仕事の中に面白さを見つけることが大切だと思います。
そうでなければ、永遠に最適を求めるか、ストレスを抱えたまま妥協することになってしまいます。
そんな「自分に合うもの」や「面白いもの」を見つけるためには、新しいことに挑戦したり、仕事と既存の何かを結合させてみることが大切です。
長く続く人は、早い時期から自分の天職はこれだと決めて既に取り組んできた人。
又は、「自分を取り巻く環境」を「自分らしい環境」へと作りかえていく意識を持って行動できる人だと思います。
- 親父の小言

堺 友樹- 1.火事は覚悟しておけ
災難というものはいつやってくるかわかりません。また、自分では気をつけていても周囲から来るものもあります。それに対する備えは忘れるなということです。
儲けを全て使ったりせず、内部留保もいざという時のために備える必要があるでしょう。
2.何事にも分相応にしろ
一時期の成功により馬主になったりフェラーリを乗り回したりした経営者は、ことごとく失敗に転じています。
分相応は上り調子のときにこそ、肝に銘じる教えのようです。
3.この言うこと八九聞くな
そのままの解釈だと『子供の言うことの八割九割聞くな』となりますが、真意は『全てを否定せず、一割二割は聞け』ということです。『子供を信じろ!』という意味になるでしょう。
江戸時代に作られたと言われる『親父の小言』ですが、新しいものがどんどん出てくる昨今においても通ずるものがあるのではないかと思います。
- コミュニケーションはキャッチボール・・・ではない

山村 佳恵- 昔からコミュニケーションは相手と自分との言葉のキャッチボールであると言われていましたが、脳科学に基づく仕事術の本を書かれている宇津出雅巳さんという方によるとこれは間違いであるとのことです。
例えば話し手が昨日所沢で友達とお酒を飲んだといったとします。
しかし昨日といってもそれが何時頃かわかりません。
また所沢のどこなのか、そもそもお店なのか自宅なのかも省略されています。
しかし聞き手は情報が省略されていても聞くことができます。
それは話し手の言葉に聞き手の持っている記憶が反応することで省略された情報の部分を無意識に補っているからです。
しかし話し手の中にある風景と聞き手が想像した風景は異なります。
お互いこれまでの人生で蓄積してきた記憶が違うのでそれは当然の結果になります。
これがコミュニケーションはキャッチボールではないという理由であり、コミュニケーションミスの原因になります。
それではこれをどのように防ぐか。
まず自分が話し手側だった場合は何かを伝える時「自分は相手のことを知らない」と意識して思うことが大事です。
知らないと思えば自分の記憶ではなく、自然と相手に意識の矢印が向くので具体的に話そうという気持ちが働きます。
自分が聞き手側だった場合は相手が発した言葉の中の不明点を適度に質問することによって認識のズレを埋めていくことができます。
これらの方法でコミュニケーションミスが防ぐことができます。
- 不便益を考える

丹下 優子- 不便益とは不便だけど利益になる、メリットとなる、楽しみがあるといったことです。
マニュアル車や焼肉は、運転すること、自分の好みに肉を焼くことの楽しみが、面倒を上回っている典型的不便益です。
最近は、あえて小さい段差を残す高齢者住宅があるそうです。
足を上げることによって本来の運動能力や注意力を維持する意味合いがあるそうです。
またある観光地用のナビシステムは、目的地手前でナビゲーションを終了するそうです。
あとは自分で探すことを楽しんでね!という具合です。
何でも便利に効率的にという昨今ですが、こういった不便さをウリにした商品づくりに目を向けてみることもとてもおもしろそうです。
- 時は金なり

江原 智恵子- 「時な金なり」ということわざがあります。
時間はお金と同じくらい貴重で大切なものだから時間を無駄にしてはいけない、時間を大切にしましょうという意味のことわざです。
しかし、人は時間が無限にあると勘違いし、つい時間を無駄に使ってしまうものです。
ビジネスの視点からすると、時間を無駄にするということは利益の損失につながるそうです。
松下幸之助さんは「多くのことをより短い時間でやり遂げる方法を会得すべきだ」と言っています。
誰でも時間をかければできることを、より短い時間で習得することで、人より多くのことを会得することができます。
時間は全員に平等に与えられています。
平等に与えられた時間をどのように使うかは自分次第です。
時間を上手に使うことで利益の損失を回避し、さらには利益を生み出す時間を作ることができるのだと思います。
- 男脳と女脳

竹内 純子- 一般的に男性と女性では脳の構造が異なり、違う考え方をすると言われています。
男脳の人は、客観的な数字のデータから、自分の価値基準に照らし合わせて判断することが得意です。
女脳の人は、数字よりもイメージしやすい「言葉」が重要です。
また、男性は楽天思考で「うまくいく可能性」を先に考え、女性はリスクヘッジしたい傾向があり「失敗する可能性」を先に考えるそうです。
口コミに対しても違いがあり、共感力の高い女性は良い口コミを広め、また自分の購入の際も口コミを判断基準にする場合が多いです。
男性は人よりも優位に立ちたい、他人よりも良いものを持ちたいという欲求が強いため、プライベートの場合は良いものを自分から宣伝する役割を担ってくれる人が少ない傾向があるようです。
CMなどについても男脳・女脳どちらにむけたものかを意識してみるとおもしろいかもしれません。
- 相手に理想像を投影する

工藤 正悟- コンサルタント養成DVDにて紹介されていた内容です。
子どもに何かしてほしい時「お姉ちゃんだから出来るもんね?」と語りかける技法の事です。
本人の自発性を促す技法です。この方法は大人にも当てはまるそうです。
「皆さんご存知のとおり」
「皆分かっていると思うけど」
などの枕詞もこれにあたります。あまりにも現実と離れた理想像を伝えてしまうと嘘っぽくなります。
以下がポイントです。
・少ない成功を盛大に言う
・3割程度の人が出来ているものを全体に言う
・技術ではなく思考について言う(比べ様がないため)自発的に働いてもらうためのちょこっとしたテクニックです。
- 「決断疲れ」を回避する

土肥 宏行- 人は1日に9000回の決断をしているのだそうです。
そんなにしてるの?と思うかもしれませんが「ダイエットをしよう」という大きな決断から、スマホを見て「どのサイトを見よう」これも決断です。
人はモノや情報に触れている時、必ず何かしらの決断をしています。
そして決断の回数が増えるたびに精神が疲れていき、決定の制度が下がっていくのだそうです。
例えば裁判官は、午前中に比べると午後の方が好意的な判決が少なくなることが明らかになっているようで、決断疲れをしてくると思考停止状態になり、判決を下すのが面倒くさくなり、今のままでいいやってなるのです。
決断の回数が増えたのはスマホの普及が大きいようですね。
では決断疲れを回避するにはどうすればいいのか。
1つは決断する回数を減らすです。
スティーブジョブスもやっていましたが、毎日同じ服を着て、服を選ぶ決断をしないなどです。
スマホを見ないこれも方法の1つです。
自分にとって些細な決断を減らすということでしょう。
もう1つは疲れるのは仕方ないと諦めて、重要な決断を先にするということです。
疲れる前に決断をする、決断をしてもらう。
相手も自分も決断疲れをするということを知っておくことは大事でしょう。
- 舞台に上がったら役を演じきる

堺 友樹- 芝居を見に行く機会があり、その芝居の中で
『舞台に上がったら、何が何でも役を演じきらなければならない』
というセリフがありました。
例えば仕事に置き換えると、お客様の前に立ったら、どんな状況であっても自分の役割を演じ切らならないということです。
どんな事があっても相手の役に立つために、役者になりきって仕事をしなければ相手には伝わらないと思います。
- 人は無意識のうちに変わらない決心をしている

山村 佳恵- 心理学者アドラーによると人は無意識のうちに自分の性格やライフスタイルを変えない決心をしています。
それは新しい自分やライフスタイルになった瞬間から何が起こるか予測できないという恐怖心からくるものだそうです。
もし本当に変わりたいと願うのであれば、この無意識の決心を解除する必要があります。
例えばアドラーの本の中に小説家になることを夢見ながらなかなか実現できない人物が出てきます。
その人によると本業の仕事が忙しくて小説を書き上げられないのだというのが理由です。
しかしアドラーによると実際はそうではなく、小説を書かないことによって、本当は自分には才能があるが環境悪いから・・・時間が無いから・・・と言い訳をしているに過ぎないとの事。
現状打開を目指し、無意識にある「変わらないという決心」を解除するためにはまずは目標に向かって小さくとも一歩を踏み出し見てみることが大切だそうです。
- ファスト&スロー

中澤 正裕- 人の意思決定には2つのシステムがあります。
システム1は一瞬で答えが出せる早い思考、システム2は注意して考えないと決断が出ない思考です。
時にこのシステムはエラーを起こします。
例えば、バットとボールの合計は1,100円です。
バットはボールより1,000円高いです。
ボールの値段はいくらですか。
システム1で瞬時に答えをだすと100円!となりますが、よく考えてみると50円というのが分かります。
瞬間の判断で物事を進めてしますと時に間違った方向へ進んでいくことになります。
人間の脳はあまり考えたくないと無意識に考えているといわれているので、意識的に一瞬立ち止まって考えてみる、そのような意識が正しい選択につながるのではないでしょうか。
- 紹介のタイミングは契約直後!

丹下 優子- お客様になっていただく最も効果的な方法は、やはり紹介かと思います。
要はクチコミの力を活用する訳ですが、人間真理として紹介したくなるタイミングは、契約(購入)直後が最も高いのだそうです。
なぜならその時期は、その商品もしくは営業マンに強く惚れ込み期待している状態だからです。
この時期に「ぜひお仲間を教えていただけませんか?」とお願いすると、友好的に協力してくれる可能性が高いそう。
私たちの心理からすると、商品や人の熱烈なファンになってくれるまで待とうしますが、時間をかければかけるほど、紹介のタイミングは逸するのだそうです。
契約したばかりのお客様から紹介を得るなんてそんな無茶な・・・と思うかもしれませんが、良いと思って契約してくださったわけですし、さらにはお客様も、同じサービスを受ける仲間が欲しいと思っているかもしれません。
契約直後にご紹介のお願い・・・。おもしろいタイミングかもしれません。
- 共感力を鍛える

工藤 正悟- 共感力とは、相手の状況・心情を察する力です。
共感力を鍛える方法を調べると心構えについてなど、いくつか方法が出てきます。
今日は自分の共感力を鍛えるのではなく、相手にとって「この人は自分のことを分かってくれている」と感じてもらうための技を紹介します。使ってみてください。
①主語を入れ替えて話す。
社長は~とか、御社は~とかではなく、相手になりきったつもりで私は~、うちの会社は~と話すことです。私たちの立場で言えば、関与先の会社のことを「うちの会社は~」と表現することがあると思いますが、まさにこれが主語を入れ替えて話すということです。
②ひょっとして、という枕詞を使う。
相手がなかなか打ち解けてくれない時、相手の心情を探るために使う言葉です。
「あなた、こう思っていませんか?」より「ひょっとして、こう思っていますか?」と聞いた方が、違かったときにあっさりと流すことが出来ます。断定的な言い方で否定された場合と印象が異なります。
- アプリの光と影

竹内 純子- メルカリというアプリでは、品物を買おうと検索したときに「すでに売れてしまっているデータ」も表示されます。
通常は買う人にとって邪魔なデータに思いますが、この表示を便利に使っているユーザーもいます。
買おうとしたときに、今出されているものが妥当な値段なのかという判断ができる、売ろうとしたときに、写真や説明文のほかに「出品時の値付け」にも利用できる、といったことです。
売る・買うというそれぞれのニーズでアプリを見ている人の視線は、光と影のような関係です。
また、美容室などの個性を生かしたビジネスの場合、ホームぺージやSNSを見る人も使い方は分かれます。
お客様のほかに、同業他社や就職を考えている人も見ている割合が高いそうです。
そのため、ホームページもお客様以外の目線があるということを意識すると一石二鳥なのかなと思います。
- 口コミの影響力は大きい

江原 智恵子- 皆さんは飲食店を探す時にどのように探しますか?
インターネットのグルメサイトでお店を検索し、口コミの評価が高いところに行くという方も多いのではないでしょうか?
口コミは実際に食事に行かれた方の意見なので、説得力があると思います。
ただ、人それぞれ主観があるので、あくまでも参考にとどめるのがよいと思います。
さらに友人・知人から直接薦められた場合は、もっと説得力があるのではないでしょうか?
最近、私は人から薦められたうどん屋さんに実際に行きましたが、おいしかったです。
その人からの口コミがなければ、そのうどん屋に行くことはなかったかもしれません。
又、そのうどん屋さんにとっての新しいお客である私が別の人においしいよと口コミをし、それが繰り返されることによってお客様は増えていくのでしょう。
お客様が勝手に営業をしてくれるという訳です。
なんともありがたい話です。
私たちの仕事も、お客様に口コミをしていただけるよう、良い商品・サービスを提供できるように努力したいと思います。
- 問題の意味を知る

江原 智恵子- 人生には様々な問題が生じます。
一難去ってまた一難ということもあれば、同じ問題が繰り返しやってくるということもあるかもしれません。
問題に直面した時の問題に対する捉え方は人それぞれだと思います。
問題から逃げようとする人、誰かのせいにして恨む人など、その人の人生観が色濃く出ます。
しかし、人生に起きること全てに意味があると考えると、問題の捉え方は変わってきます。
問題を避けるのではなく問題の意味を知ろうとします。
この問題の本当の意味は何なのか、何を教えようとしているのかを繰り返し考えると問題の意図がわかるようになっててきます。
自分にふさわしい問題が与えられているということがわかり、そのメッセージが読み取れるようになってきます。
又、問題は根本が解決されないと繰り返し同じ課題がやってきて、それが解決されるとより高い問題に切り替わるようです。
問題解決の本質は問題が消えてなくなることではなく、より高い応用問題がとけるようになることかもしれません。
それは同時に自分の問題解決から他人の問題解決へとレベルアップしていくことかもしれません。
根本的な問題解決には問題の意味を知ることが大事になってくると思います。
- 長く続けること

堺 友樹- ポルノグラフィティが9/8にデビュー20周年を迎え、記念コンサートが東京ドームで行われました。
そのコンサートで、初期のポルノグラフィティを支えた本間昭光氏が長く続けるコツを2つ上げていました。
1つ目は長く続ける意志を持つこと。
2つ目はファンから求められ続けさせること。
これを私たちの仕事に置き換えると、まず、この仕事を長く続ける意志を持つこと。
そして、お客様から私たちを求めてもらえるような仕事をすること。
少なくとも、私たちをお客様から求め続けられるような仕事をしてきたからこそ、長い間仕事ができるのであるから、これからもお客様から求め続けられるような仕事をしていかなければならないと思います。
- ほったらかしキャンプ

土肥 宏行- 私が何回かお邪魔した南房総にあるキャンプ場は台風15号の影響により、建物は半壊し、電気、水はまだ復旧されていません。
大丈夫かなと思いながらブログをみていると、台風からわずか2日後にはイベントの告知が。水も電気もないけど片付ければ泊まるところは問題ない。
施設側は何も提供できませんが、ほったらかしでよければ!南房総の状況を生で見て欲しい。
そして3連休なので皆でワイワイやりましょう。
台風があった週末にやることになったイベント「ほったらかしキャンプ」です。
こういう時は大変なんだから、ゆっくり休むのが普通だと思うのですが、このキャンプ場の管理人のように皆が大変な時、つらい時でもすぐに立ち上がって行動できる人がいるんですよね。
またブログには「解体した廃材で焚火しましょうw」とあります。
こんな時でもユーモアをもてる、強くあることができる。凄いなと思いました。
- 3つの喜びを味方につける

柴崎 誠- 物事を長く続けていきたいなら継続自体を楽しむことが最良の方法です。
つらい行動は楽しみながら継続することができるのでしょうか。
今回紹介するのが次の3つの喜びを継続の糧にする方法です。
1.賞賛される喜び…ほめられて嫌な気持ちになる人はまずいません。もし、何かつらいことを継続させたい場合には賞賛の言葉を糧にすると困難な習慣でも続ける勇気が湧いてくるはずです。
2.変化する喜び…2~3日続けたからといってすぐに効果が現れるものではありません。自分のイメージに一歩でも近づくことができれば、それは大きな喜びとなります。そして、その喜びを糧にまた継続することができます。
3.蓄積される喜び…継続していてもあまり効果が実感できなくて途中でモチベーションが下がってしまうかもしれません。そんなときに心の糧となってくれるのが目に見える蓄積です。挫折しそうになったときは目に見える蓄積が心の糧になります。
この3つの喜びを意識しておけば、困難な行動でも楽しみながら継続することができるのではないでしょうか。
- 今日は自分でつくるもの

丹下 優子- 身体的ハンディキャップを持ち車椅子での生活をしているお子さんがいます。
彼女はとても明るくて、毎日「今日はどんな楽しいことしようかな^^♪」と言って出かけて行くそうです。
早速自分を振り返ってみると、実に「今日は○○をしなければ。今週中に○○を仕上げなければ」という受け身の態勢が多いことに気づかされます。
あらためて今日一日は自分が作るもの。
受動的な思考は先が見えず、不安と恐怖を倍増させるのに対し、能動的な思考は不安と恐怖を激減させるというデータもあるそうです。
朝起きたら、よし!今日は何をしよう?と、今日一日を自分で動かすという意識をもって元気にスタートしたいと思いました。
- イノベーションの条件

工藤 正悟- マッキンゼーに務めていた方の著書より
イノベーションとは、以下の2種類に分類される。・技術的イノベーション:技術進歩による発展。
・非技術的イノベーション:問題解決、課題解決の手段。技術的イノベーションは科学の発展によるものなので、考慮外とし、非技術的イノベーションを起こすための条件は以下の通り。
(1)イノベーションのための時間的余裕
イノベーションの意識を持つ時間が必要。
(2)制限
制限の中で問題をどう解決するかがイノベーション。著書には、元設計士の方のコメントでこう記されていました。
「予算も制限もなく広大な土地を与えられても、良い設計は出来ない。
特定の条件下でいかに良い物を作るかという制限が無ければ良い発想は生まれない」
私たちの仕事では、(2)の制限は予算、時間、人数などが当てはまります。普段から意識していることなので問題ありません。
まずは時間を確保することを取り組んでみてはいかがでしょうか。
- 職業を決める日本人、生き方を決めるアメリカ人

竹内 純子- 日本では小さいころから「将来なにになりたいか」と職業について聞かれます。
しかしアメリカでは、「将来どんな人でいたいか」と聞くことが多く、理想のライフスタイルや生き方を答えるのだそうです。職業よりも、「どんな人でいたいか」「人生でどんなことを大事にしたいか」ということの方が、自分の価値観についての問題なので誰にでも考えやすく、その答えは「理想の自分」を意識したものになると思います。
日本の子供には「大学に受かる」ことが人生の目標になってしまう場合もあります。その場合失敗してしまうと目標を失ってしまう場合があります。
しかし、「自分がどうありたいか」という視点で考え、例えば「正直な人でいたい」というのが答えであれば、大学に落ちたことは「正直な人でいたい」という自分の生き方には影響しないので、自己否定をする必要がないことがわかります。「自分がどんな人でいたいのか」ということを意識して行動できることが、幸せな人生を送る上で重要なことで、日々それを達成することで幸せを感じることができるのかなと思いました。