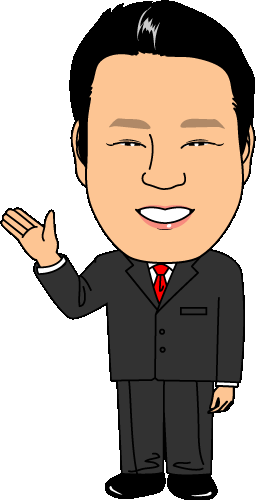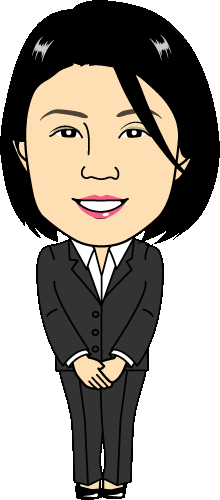スタッフのおすすめ
- 紹介のタイミングは契約直後!

丹下 優子- お客様になっていただく最も効果的な方法は、やはり紹介かと思います。
要はクチコミの力を活用する訳ですが、人間真理として紹介したくなるタイミングは、契約(購入)直後が最も高いのだそうです。
なぜならその時期は、その商品もしくは営業マンに強く惚れ込み期待している状態だからです。
この時期に「ぜひお仲間を教えていただけませんか?」とお願いすると、友好的に協力してくれる可能性が高いそう。
私たちの心理からすると、商品や人の熱烈なファンになってくれるまで待とうしますが、時間をかければかけるほど、紹介のタイミングは逸するのだそうです。
契約したばかりのお客様から紹介を得るなんてそんな無茶な・・・と思うかもしれませんが、良いと思って契約してくださったわけですし、さらにはお客様も、同じサービスを受ける仲間が欲しいと思っているかもしれません。
契約直後にご紹介のお願い・・・。おもしろいタイミングかもしれません。
- 共感力を鍛える

工藤 正悟- 共感力とは、相手の状況・心情を察する力です。
共感力を鍛える方法を調べると心構えについてなど、いくつか方法が出てきます。
今日は自分の共感力を鍛えるのではなく、相手にとって「この人は自分のことを分かってくれている」と感じてもらうための技を紹介します。使ってみてください。
①主語を入れ替えて話す。
社長は~とか、御社は~とかではなく、相手になりきったつもりで私は~、うちの会社は~と話すことです。私たちの立場で言えば、関与先の会社のことを「うちの会社は~」と表現することがあると思いますが、まさにこれが主語を入れ替えて話すということです。
②ひょっとして、という枕詞を使う。
相手がなかなか打ち解けてくれない時、相手の心情を探るために使う言葉です。
「あなた、こう思っていませんか?」より「ひょっとして、こう思っていますか?」と聞いた方が、違かったときにあっさりと流すことが出来ます。断定的な言い方で否定された場合と印象が異なります。
- アプリの光と影

竹内 純子- メルカリというアプリでは、品物を買おうと検索したときに「すでに売れてしまっているデータ」も表示されます。
通常は買う人にとって邪魔なデータに思いますが、この表示を便利に使っているユーザーもいます。
買おうとしたときに、今出されているものが妥当な値段なのかという判断ができる、売ろうとしたときに、写真や説明文のほかに「出品時の値付け」にも利用できる、といったことです。
売る・買うというそれぞれのニーズでアプリを見ている人の視線は、光と影のような関係です。
また、美容室などの個性を生かしたビジネスの場合、ホームぺージやSNSを見る人も使い方は分かれます。
お客様のほかに、同業他社や就職を考えている人も見ている割合が高いそうです。
そのため、ホームページもお客様以外の目線があるということを意識すると一石二鳥なのかなと思います。
- 口コミの影響力は大きい

江原 智恵子- 皆さんは飲食店を探す時にどのように探しますか?
インターネットのグルメサイトでお店を検索し、口コミの評価が高いところに行くという方も多いのではないでしょうか?
口コミは実際に食事に行かれた方の意見なので、説得力があると思います。
ただ、人それぞれ主観があるので、あくまでも参考にとどめるのがよいと思います。
さらに友人・知人から直接薦められた場合は、もっと説得力があるのではないでしょうか?
最近、私は人から薦められたうどん屋さんに実際に行きましたが、おいしかったです。
その人からの口コミがなければ、そのうどん屋に行くことはなかったかもしれません。
又、そのうどん屋さんにとっての新しいお客である私が別の人においしいよと口コミをし、それが繰り返されることによってお客様は増えていくのでしょう。
お客様が勝手に営業をしてくれるという訳です。
なんともありがたい話です。
私たちの仕事も、お客様に口コミをしていただけるよう、良い商品・サービスを提供できるように努力したいと思います。
- 問題の意味を知る

江原 智恵子- 人生には様々な問題が生じます。
一難去ってまた一難ということもあれば、同じ問題が繰り返しやってくるということもあるかもしれません。
問題に直面した時の問題に対する捉え方は人それぞれだと思います。
問題から逃げようとする人、誰かのせいにして恨む人など、その人の人生観が色濃く出ます。
しかし、人生に起きること全てに意味があると考えると、問題の捉え方は変わってきます。
問題を避けるのではなく問題の意味を知ろうとします。
この問題の本当の意味は何なのか、何を教えようとしているのかを繰り返し考えると問題の意図がわかるようになっててきます。
自分にふさわしい問題が与えられているということがわかり、そのメッセージが読み取れるようになってきます。
又、問題は根本が解決されないと繰り返し同じ課題がやってきて、それが解決されるとより高い問題に切り替わるようです。
問題解決の本質は問題が消えてなくなることではなく、より高い応用問題がとけるようになることかもしれません。
それは同時に自分の問題解決から他人の問題解決へとレベルアップしていくことかもしれません。
根本的な問題解決には問題の意味を知ることが大事になってくると思います。
- 長く続けること

堺 友樹- ポルノグラフィティが9/8にデビュー20周年を迎え、記念コンサートが東京ドームで行われました。
そのコンサートで、初期のポルノグラフィティを支えた本間昭光氏が長く続けるコツを2つ上げていました。
1つ目は長く続ける意志を持つこと。
2つ目はファンから求められ続けさせること。
これを私たちの仕事に置き換えると、まず、この仕事を長く続ける意志を持つこと。
そして、お客様から私たちを求めてもらえるような仕事をすること。
少なくとも、私たちをお客様から求め続けられるような仕事をしてきたからこそ、長い間仕事ができるのであるから、これからもお客様から求め続けられるような仕事をしていかなければならないと思います。
- ほったらかしキャンプ

土肥 宏行- 私が何回かお邪魔した南房総にあるキャンプ場は台風15号の影響により、建物は半壊し、電気、水はまだ復旧されていません。
大丈夫かなと思いながらブログをみていると、台風からわずか2日後にはイベントの告知が。水も電気もないけど片付ければ泊まるところは問題ない。
施設側は何も提供できませんが、ほったらかしでよければ!南房総の状況を生で見て欲しい。
そして3連休なので皆でワイワイやりましょう。
台風があった週末にやることになったイベント「ほったらかしキャンプ」です。
こういう時は大変なんだから、ゆっくり休むのが普通だと思うのですが、このキャンプ場の管理人のように皆が大変な時、つらい時でもすぐに立ち上がって行動できる人がいるんですよね。
またブログには「解体した廃材で焚火しましょうw」とあります。
こんな時でもユーモアをもてる、強くあることができる。凄いなと思いました。
- 3つの喜びを味方につける

柴崎 誠- 物事を長く続けていきたいなら継続自体を楽しむことが最良の方法です。
つらい行動は楽しみながら継続することができるのでしょうか。
今回紹介するのが次の3つの喜びを継続の糧にする方法です。
1.賞賛される喜び…ほめられて嫌な気持ちになる人はまずいません。もし、何かつらいことを継続させたい場合には賞賛の言葉を糧にすると困難な習慣でも続ける勇気が湧いてくるはずです。
2.変化する喜び…2~3日続けたからといってすぐに効果が現れるものではありません。自分のイメージに一歩でも近づくことができれば、それは大きな喜びとなります。そして、その喜びを糧にまた継続することができます。
3.蓄積される喜び…継続していてもあまり効果が実感できなくて途中でモチベーションが下がってしまうかもしれません。そんなときに心の糧となってくれるのが目に見える蓄積です。挫折しそうになったときは目に見える蓄積が心の糧になります。
この3つの喜びを意識しておけば、困難な行動でも楽しみながら継続することができるのではないでしょうか。
- 今日は自分でつくるもの

丹下 優子- 身体的ハンディキャップを持ち車椅子での生活をしているお子さんがいます。
彼女はとても明るくて、毎日「今日はどんな楽しいことしようかな^^♪」と言って出かけて行くそうです。
早速自分を振り返ってみると、実に「今日は○○をしなければ。今週中に○○を仕上げなければ」という受け身の態勢が多いことに気づかされます。
あらためて今日一日は自分が作るもの。
受動的な思考は先が見えず、不安と恐怖を倍増させるのに対し、能動的な思考は不安と恐怖を激減させるというデータもあるそうです。
朝起きたら、よし!今日は何をしよう?と、今日一日を自分で動かすという意識をもって元気にスタートしたいと思いました。
- イノベーションの条件

工藤 正悟- マッキンゼーに務めていた方の著書より
イノベーションとは、以下の2種類に分類される。・技術的イノベーション:技術進歩による発展。
・非技術的イノベーション:問題解決、課題解決の手段。技術的イノベーションは科学の発展によるものなので、考慮外とし、非技術的イノベーションを起こすための条件は以下の通り。
(1)イノベーションのための時間的余裕
イノベーションの意識を持つ時間が必要。
(2)制限
制限の中で問題をどう解決するかがイノベーション。著書には、元設計士の方のコメントでこう記されていました。
「予算も制限もなく広大な土地を与えられても、良い設計は出来ない。
特定の条件下でいかに良い物を作るかという制限が無ければ良い発想は生まれない」
私たちの仕事では、(2)の制限は予算、時間、人数などが当てはまります。普段から意識していることなので問題ありません。
まずは時間を確保することを取り組んでみてはいかがでしょうか。
- 職業を決める日本人、生き方を決めるアメリカ人

竹内 純子- 日本では小さいころから「将来なにになりたいか」と職業について聞かれます。
しかしアメリカでは、「将来どんな人でいたいか」と聞くことが多く、理想のライフスタイルや生き方を答えるのだそうです。職業よりも、「どんな人でいたいか」「人生でどんなことを大事にしたいか」ということの方が、自分の価値観についての問題なので誰にでも考えやすく、その答えは「理想の自分」を意識したものになると思います。
日本の子供には「大学に受かる」ことが人生の目標になってしまう場合もあります。その場合失敗してしまうと目標を失ってしまう場合があります。
しかし、「自分がどうありたいか」という視点で考え、例えば「正直な人でいたい」というのが答えであれば、大学に落ちたことは「正直な人でいたい」という自分の生き方には影響しないので、自己否定をする必要がないことがわかります。「自分がどんな人でいたいのか」ということを意識して行動できることが、幸せな人生を送る上で重要なことで、日々それを達成することで幸せを感じることができるのかなと思いました。
- 安易に妥協しない

江原 智恵子- 仕事を進めていくと必ずと言っていいほど抵抗にあいます。
色々な理由で自分の希望通りに仕事を進めることができなくなることはよくあることだと思います。
多くの人はここで妥協をします。
妥協という手を使って仕事をうまく収めようとするのです。
妥協には智慧の妥協と逃げの妥協があります。
智慧の妥協とは、これくらいのミスであれば大勢に影響がないので、深い入りしないようにしよう、ここはあえて貸しをつくって次につなげようというように、その妥協を戦略的にとらえるものです。
逃げの妥協とは、時間がないから、今更やり直すのは面倒だからなど本来はやり直すべきものを他の理由をつけてあきらめる妥協です。
この、どこで妥協するかの違いが仕事の質を決めます。
仕事ができる人は安易に妥協しません。
そして自分の妥協ラインを守ることで仕事の質を保っています。
仕事をする上で妥協が必要な場面は多くあると思いますが、今ここでやろうとしている妥協は智慧の妥協なのか逃げの妥協なのかをよく考えて判断をしたいと思います。
- 『積極的休養』と『消極的休養』

堺 友樹- 高校の部活で休養に2つのものがあると言われました。
1つ目は体を動かし気持ちを休養させる積極的休養です。
目的はストレス解消して心の疲れを取ることです。
もう1つは体を休ませる消極的休養です。
体の疲れを取ることが目的です。
どちらも休養に違いないのですが、働き方改革で勤務時間に制限をつけようとする現在の傾向からすると、せっかく早く帰れても消極的休養に時間を費やしてしまっては、改革の本来の目的が成し遂げられません。
必ずしも消極的休養をするなということではありませんが、より生産性を高めて仕事をしていくためには、時間を有効に使わなければできません。
積極的休養には個々人の趣味も含まれます。
自分の仕事における生産性を高めるために読書をしたり勉強したりするのも積極的休養になります。
時間を有効に使い、かつ、仕事の生産性を高めるためにも、積極的休養は合致するのではないかと思います。
- 「言いたいこと」より「聞きたいこと」を伝える

土肥 宏行- トヨタの豊田章男さんがバブソン大学卒業式で行ったスピーチの動画を見ました。ドカン、ドカンと笑いがおこり、最後には皆が聞き入り、拍手喝采でとにかく凄かったです。
そして豊田氏がこのスピーチに相当準備がされているのだと感じました。
基本、人は自分の信じる考え方しか受け入れないし、聞きたいことしか聞かないのだそうです。
だとしたら相手の聞きたい内容に自分のメッセージをさりげなく潜り込ませるしかない。
豊田氏は聴衆がどういう人たちで、何を聞きたいのかを調べ上げた上で、すりより、道化にもなり、最後に一生に一度のはなむけの言葉をしっかり伝えていました。
なんとなく伝えたいことを伝えるから伝わらない。
言いたいことより聞きたいことを伝える。
その最高の教材がこのスピーチだと思ったのでお勧めしました。
- 運は後ろからやってくる

柴崎 誠- タレントの萩本欽一さんはコント55号の活動が少なくなり、個人での活動を始めようとした時に事務所へ1つだけ断りを入れました。
「テレビで司会の仕事はやりません。」
台本が覚えられないので司会進行をするのが苦手だったそうです。
ところが、テレビ局からは司会の依頼ばかり来てしまいました。
決心して引き受けた仕事がオールスター家族対抗歌合戦の司会でした。
芸能人とその家族が歌を披露する番組でしたが、中にはとってもユニークなお父さんがいたようで、萩本さんはこの番組でテレビに素人が出るのはすごく面白いことに気づいたそうです。
後に萩本さんが企画した番組ではそれまでバラエティーに出たことないタレントや素人を次々に起用して番組は成功しました。
この経験から最初は嫌だなと思った仕事でもそこには運がついていて良い仕事をさせてくれると考え、あえて引き受けるようにしたそうです。
- 行ってらっしゃいの効果

中澤 正裕- 出かける際にしっかりお見送りをして、「行ってらっしゃい」と声をかけるといろんな効果があります。
1.交通事故率が下がる
2.年収がアップする
3.寿命が延びる
4.病気の確率が下がる
5.抗うつ作用がある
今回は事故率について取り上げますが、満たされていない生活を送っていたり、ストレスを感じていると精神的に不安定になり、判断能力などが鈍ります。
また、自分には守るべき人がいるという認識をするので、自然と安全に気を遣い、結果的に事故率が下がるそうです。
大事なパートナー、家族、職場でもお出かけの前には「行ってらっしゃい」と声をかけてあげてください。
- 一日が25時間になったらどうしますか?

中澤 正裕- 睡眠を1時間増やす!私も最初はそう答えました。
普段の活動を4つの領域に分けてみます。
第一領域は緊急性も重要性も高いもの。
第二領域は、緊急性は低いけど重要性の高いもの。
第三領域は、緊急性は高いけど、重要性の低いもの。
第四領域は緊急性も重要性も低いもの。
に分かれるそうです。
最初の質問に対する多くの答えは第二領域に入るものだそうです。
つまり緊急性は低いけど重要性の高いものです。
ジムの時間だったり、趣味の時間であったり、あまり手付かずのものです。
実際考えても時間は増えません。
最初は15分でも良いから意識的に時間を作ることが重要だそうです。
一日の1%の時間です。
意識が変われば行動が変わる。
行動が変われば習慣が変わる。
習慣が変われば人生が変わる。
- 決断力を磨く方法は『決断すること』

丹下 優子- ある怪物に捕まって、次の問題を出されたとする。
【7分の砂時計と4分の砂時計を使って、ちょうど9分経過したことを知らせる事ができれば、殺して食べるのは勘弁してやる】
人間は、おおよそ次の4つのパターンに分かれるそうだ。
1.腕組みして考えている間に食べられてしまう人
2.「え、どういうこと?」と質問で時間を稼ぎ、結局食べられる人
3.とにかく砂時計を倒して、それから考える人
4.笑みをみせながら悠々とクリアしてしまう人
幸い、ビジネスではこれまで命がかかった即断即決の場面はないものの、実は似たような状況は多い。
意志決定に迫られたら、とりあえず砂時計を倒して与えられた時間で何らかの結論を出せば上出来だ。
考える時間が多い割に何も決めていないことが多い。
決断力をみがく方法は一つしかない。
それは、「決断する」ことだ。
- サボタージュマニュアル

工藤 正悟- CIAの前身組織OSSが作成した、敵国に送り込んだスパイが敵国の組織のパフォーマンスを下げるためのマニュアル。
サボるの語源。
インターネットで調べた内容を見ると16項目あり、まとめると
・目的よりも手段を優先させる
・全体の進捗よりも、細部にこだわらせる
・自責よりも他責にできる仕組みを作る
となります。
まとめた内容をみると、わざわざそんな事をする人はいないと思いますが、
細かい項目をみると
・常に文章による指示を要求せよ。
・準備を十分に行い完全に準備ができているまで実行に移すな。
・重要な決定を行う際には会議を開け。
など当てはまりそうなものがあります。
自分自身がサボタージュらないように気を付けましょう。
- つながりを生むビジネス

竹内 純子- 三鷹に「ブックロード」という無人の古本屋がある。
オーナーは日中会社員として働いているため、「野菜の無人販売所」からヒントを得て「無人の古本屋」を開いた。
無人のため、お客さんは本を並べ替えたり、気付いたことを手紙でおいていったり思い思いにお店を利用している。
お店が地域を信じて無人の古本屋を開いた結果、顔をあわすことのない不思議なつながりが生まれている。
また、支払は本の値段分ガチャガチャを利用し、出てきたカプセルの中にはいったビニール袋がレシートがわりになり、お金を払ったという無言の証明になるようにしている。
直近10年で3割の本屋が減っているが、人手をかけなくても人と人とのつながりを生み出し、その中で続けられるビジネスなら魅力的だ。
商品だけでなく、そのやり方に惹かれて来店する人も多いのではないだろうか。
- 「数学は役に立たない?」

堺 友樹- 林修先生が、「数学は大人になって役に立たない」という生徒の意見に、以下のように話されていました。
数学は実社会で、四則演算以外使うことはなかなかありません。
しかし、縦軸を【好きなこと】、横軸を【役に立つこと】としてグラフを書いた場合、4つのエリアに分かれます。
【好きで役に立つこと】は率先して人間は行動します。
逆に、【嫌いで役に立たないこと】には行動をしません。
では、【好きだけど役に立たないこと】と【嫌いだけど役に立つこと】はどうでしょうか?
人間は嫌いなことは避ける傾向があります。
しかし、後々役に立つことであれば、そこにチャレンジする重要性は皆さんもわかると思います。
そして、このような捉え方(グラフ)ができるのは、実は数学をやっているからだそうです。
数学とは本来、このような考え方を教えるべきで、解を求めることではないと解説されていました。
自分の人生で【嫌いだけど役に立つこと】をどのように捉えるかで、大きく人生が変わるのだと思います。
- 「共感力を高める」

石原 あい- コミュニケーションをとる上では共感力が大切である、と言います。
日本コミュニケーショントレーナー協会の椎名規夫さんという方の著書の中で、
「共感力とは、こちら側が相手の気持ちに共感することではありません。相手からこの人だったら分かってくれる、この人だったら信頼できる、と感じてもらうこと」
であり、
「どんなに相手の気持ちを感じる事が出来たとしても、同じ体験をしていない限り"あなたの気持ちが分かります"と言う言葉は安易に使わないことをお勧めします」
と書かれています。
例えば、災害で家族を失った方に対して"あなたの気持ちが分かります"とは言えません。
それは同じ体験をしていないからです。
このような被災した方のメンタルケアをされている臨床心理士の方は
「本当の共感と言うのは、相手が"辛いんです"と言ったら"今は辛いんですね、、"と、つまり、こちらがどうかではなくて相手の気持ちに寄り添い確かめるように話を聞くことが、本当の共感なのです」
と述べられています。
- 与えすぎず、与えなさすぎず

土肥 宏行- 家電量販店のIKEAは、家具を組み立て式にすることで低価格を実現しています。
そんなIKEAの家具をプロが組み立てたものと自分が組み立てたものを並べ、値段をつけさせるという実験をしたそうです。
すると自分で組み立てたものに高値をつけたのだとか。
自分の作ったものを過大評価し、他人にとっても価値のあるものと思う心理効果が働くのだそうです。
ホットケーキを作る材料のホットケーキミックスは、販売当初粉に水を混ぜ焼くだけで完成するというものでしたが、あまり売れなかったそうです。
そこでホットケーキミックスから卵と牛乳の成分を抜き、自分で卵と牛乳を加えるよう変えてみたところ、売上が劇的に向上したそうです。
普通はユーザーの手間が少なければ喜ばれると考えがちですが、ユーザーの手間を増やすことで逆に楽しみや満足感を与えることができ、逆の結果になることもあるようです。
「与えすぎず、与えなさすぎず」が時には良い結果になることもあるようです。
- 徹底的なシミュレーションをする習慣をつける

柴崎 誠- 物事が成功するかどうかを決める大きな要因の一つは、その前に行う準備、段取りです。
その準備で大事なのが現実に即して考える「シミュレーション」です。
計画を確認する際は、必ずシミュレーションを行います。
特に一日の始まりである起床後にすると効果的。なぜ起床後なのか、一日の大事なスタート時点だからです。
一日の過ごし方、時間の使い方、また力の入れ方にメリハリをつける必要があります。
大事なことに力を注ぐということです。
行動のシミュレーションは、心の準備をする上で効果的です。
心が定まると、迷いがありませんから全力で頑張れます。
シミュレーションも慣れるまでは、頭だけではできないので最初は紙に書くことで頭を整理してみます。
シミュレーションをして、まず、どんな行動をするのか、その目的は何なのか、また、その目的のためには、最初の行動を起こした後どんなフォローをしなければならないのかを、一目瞭然となるよう書きます。
自然にシミュレーションをする習慣がつけば、深く考えること、また、行動する前からの心の準備ができて、余裕ある行動ができるので、仕事術としてはとても効果的なテクニックとなるのではないでしょうか。
- 合言葉は『時短・レンタル・ひとりで』

丹下 優子- 次のような仕事が既に成り立っているそうです。
時 短・・・ジグソーパズルの代理制作。テレビゲームをある程度までレベルアップさせておいてくれ、自分は強くなってから始められる(時間はないが飾りたい!遊びたい!の良いとこ取りサービス)
レンタル・・・ペット・洋服・装飾品のレンタル。(所有から借りる・定額制へ)
ひとりで・・・ひとりでじっくりガッツリ集中して仕事をしたい人のための"有料ひとり時間確保セミナー"(みんなでからひとりで)
私たちも、場合によっては思考のテーマをこの3つに絞ってみると何かヒントがみつかもかもしれません。
- 会社は儲け続けれなければ、社会に迷惑をかけてしまう

工藤 正悟- 誰の言葉か分かりませんが、学生時代に聞いた言葉です。
言葉の意味はいくつかあります。
儲けられない=世の中が受け入れていない商品を押し付けている=迷惑
儲けられない=存続できない=今のお客様が商品を買えなくなる=迷惑
儲けられない=今は変えないが将来のお客様が商品を買えない=迷惑
儲けられない=給料が多く払えない=迷惑
この言葉に則るならば、儲ける=社会に貢献していることになります。
私たちの仕事も社長の儲け=社会への貢献の一端を担っています。
また、この言葉に則るならば値引きはありえません。
世の中に貢献しているのに、値引く理由がない
値引き=儲けを減らす行為=社会への迷惑につながる
- イノベーションは誰でも起こせる

竹内 純子- 「イノベーション」とは「労働力など、それまでと異なる仕方で新結合すること」という意味だそうです。
そう考えると、「新しい生産方式」「新しい販売の仕方」さらに「新しい組織の実現」といったことも「イノベーション」にあたります。
人事的なイノベーションで「管理職が3ヶ月会社に来なくて良い」という面白い取り組みをしている企業があります。
日々忙しい管理職の方にとっては、「今の職場でどんなことをしたいのか」を考える時間になり、他のメンバーにとっては新しい変化がおこったり、情報の共有化が進んだりと良いことがあるそうです。
この例は極端ですが、自分の職場でも小さなことからでも変化をおこすことはできるかもしれません。
もっと身近な範囲でも、イノベーションを起こせる可能性はあるのだと感じました。
- 思い込みをなくす

江原 智恵子- 人はいったんこうだと思ったらその考え方にとらわれてしまうものです。
これが思い込みと言われるものです。
インドの象の話になりますが、インドでは象が子供の頃に足にロープをまかれて頑丈な杭につながれます。
初めは逃げようともがくのですが頑丈な杭はびくともしません。
そのうちに諦めて逃げることをしなくなります。
逃げらないという強い思い込みによって象は大人になっても逃げることをしません。
私たちもこの象と同じように過去の経験に基づいて将来を予測するので、過去にあったことは将来も同じように続くと考えてしまいます。
でも世の中はめまぐるしく変わります。
過去にとらわれ過ぎず、今これから判断していかなければならないことは、過去はこうだったが本当に将来もそうなるのかと疑問をもつ必要があると思います。
自分だけの思い込みにとらわれてしまうと新しい発想も生まれませんし、できる可能性があるのにできないと自ら決めつけてしまうことにもつながります。
思い込みにとらわれないことが自分の視野や可能性を広げるために大事になってくると思います。
- 良いものは高くて当たり当然

土肥 宏行- 湯浅醤油(有)の出している生一本黒豆という醤油は200m?、1000円と大変高額です。
社長が世界一の醤油をつくると決めてから、材料や製法にこだわり、時間と手をかけて作ったものです。
我々日本人は良いものを安くという考えがあるため、金額でまず判断してしまいます。
この醤油を世の中に広く知れ渡るきっかけになったのは、ヨーロッパのミシュランシェフでした。
シェフはマカロンなどの外側に隠し味として醤油を使うようなのですが、その隠し味にこの醤油を使いたいと言ってきました。
社長はこの醤油が高いことを心配していたのですが、シェフは
「客は満足するためにうちの店に来ている。この醤油じゃないと満足しないのだから高くて良いのだ」
と答えたそうです。
ヨーロッパにはワインなど良いものをじっくり時間と手間をかける文化があり、そのことに対する尊敬があります。
作り手は世界一のものをつくる。
それを認める文化がある。
両方があって本物が育つのだと思いました。
- 力を入れすぎるから時間の感覚を失う

柴崎 誠- 限られた時間内で成果を上げる仕事の方法として優先順位設定があります。
これは「多くの仕事の中から、どこからするべきかを決めること」です。
今回はインバスケットというものを紹介します。
このインバスケットの考え方は、仕事の結果より、プロセスを重視しています。
実際の研修では60分間で20ほどの案件を処理することが望まれます。
ただ、実際の研修で出されるインバスケットの問題は、時間内にすべての案件処理が終わるようにはつくっていません。
インバスケットでの正しい仕事の進め方はすべてを頑張る必要はない。
大事なのはほんの一部でそれだけ頑張ればよいそうです。
何を解決すると、一番成果が上がるかを考えて優先順位をつける。
そして、優先順位の高いものに力を入れる。
なぜ頑張らなくていいのか、それは、時間には限りがあるからです。
時間は限りがあって減るものです。
決して増えるものではありません。
やらなければならない仕事を一覧にして、どこに力を入れたら良いのかを考えることから始めます。
考えるポイントを変えることが成果につながるはずです。
- 人を集める3つの基本

中澤 正裕- コピーライティングの目線から人を集める3つの基本を紹介いたします。
1.期待を裏切る
期待と現実の差が大きいほど行動を起こします。
2.未来を想像させる
変えたい現状があるから行動を起こします。
相手に理想の姿や未来をイメージさせることが重要です。
3.緊急性を持たせる
なかなか手に入らないものだと行動する傾向があります。
又、限定性も効果があります。よくある「残り〇〇個」「〇〇人限定」
などです。
集客で基本となることだそうなので、参考にしてみてください。
- ITは万能ではない

竹内 純子- 「AIと教科書を読めない子供達」という本に書かれている言葉です。
最近のニュースでは「AIが発達して人間の仕事がなくなる」という印象を受けますが、AIは人間の使っている言葉を読みこなす「読解力」がまだ不足しているそうです。
つまり、AIが勝手に人間の言葉や状況を理解し、独立して仕事をするというのはまだ難しいそうです。
「読解力」の他にも、AIが苦手とすることは
・新しいことを思いつくこと
・命令されていないことをやること
・起きていないことを分析すること
だそうなので、AIに負けないように仕事をする上でもこういった点を磨いていきたいと思います。
- メンタルの強さは成功の秘訣

江原 智恵子- スポーツの世界でプロとして成功した人に松井秀喜さんや松岡修造さんがいます。
そんな彼らが過去に勝てなかった天才がいたそうです。
松井さんや松岡さんよりも抜群に才能があり、かつては天才と言われていた人でもプロになれなかったり、プロになっても成績を残せずすぐに引退してしまったり、最終的に成功できなかった人と、実際にプロになって成功を収めた人との違いは何なのか。
共通して言えることはメンタルの強さの違いではないかと思います。
かつての天才たちは、能力は高いものの精神的に弱かったり、思っていることが言えないというタイプの人でした。
逆に成功している人の共通点は、自分の気持ちをコントロールすることができる、明るく前向きである、自分で自分を信じ切ることができるなどでした。
能力が高いだけではダメでメンタルを強くすることが本来の能力をさらにパワーアップさせ、結果的に成功する秘訣になるのではないかと思います。
- 小さな努力

堺 友樹- 阪神に『鳥谷敬』という選手がいます。
彼は高校時に甲子園出場を果たし、高校3年の秋にプロ志望届を出しましたが、どこからも指名されず、早稲田大学へ進学しました。
大学では1年生からレギュラーで活躍し、プロ入りを果たしました。
そんな彼は、プロ野球で連続出場記録1939試合という記録を打ち立てています。
これは、歴代2位の記録です。
しかし、実はいろいろ体の故障をしていました。
彼はそんな自分の体をよくわかっており、大学の頃には温冷入浴法を取り入れ、体に練習後の疲れを残さないことを必ず行っていました。
そういった小さな努力が、記録を打ち立てる原動力になっています。
- Small Gift, Big Smile

石原 あい- これはサンリオの企業理念です。
続けて「ほんの小さな贈り物が 大きな友情を育てます」と書かれています。
サンリオのキャラクターの中で最も有名なハローキティは沢山の商品とコラボをしているのですが、時には驚くようなものもあります。
メタルバンドの派手メイクをしたりムンクの叫びになったりと、ビックネームにも関わらず果敢に七変化していくキティに、仕事を選ばない大御所のような粋を感じる人も少なくないようです。
こうした経緯の中、昨年の株主総会での社長の発言の中に
「もし、いい商品やおいしいお菓子があるのに実はお店では売れていないと言うことがあれば、商品にサンリオのキャラをデザインしてみたらどうかと提案してみて下さい。そうすれば売れるようになりますから。うちはお助けビジネスですから」
と話したそうです。
これはキティのキャラに限ったことではないですが、キティの仕事を選ばない理由というのが、こうした知名度を使って売れないモノを助ける、と言う助け合い精神に基づいているという事です。
この助け合い精神や相手の役に立つ、といことは私たちの仕事にも通じる事だと思います。
- 度忘れは脳を活性化させるチャンス

中澤 正裕- 人間の記憶は、記銘、保持、想起の三段階で成り立っています。
この一つでも欠けると不完全なものになります。
度忘れは想起が欠けてしまって起きている現象になります。
頑張って思い出そうとしている時、脳はフル回転しているので、人に聞いたり、ネットで調べてしまっては活性化のチャンスを逃しているそうです。
何を考えていたのか思い出そうと、動き出した場所に戻ると思いだしたりすると思います。
記憶というのは、場所や、気温、周囲の状況を記録し、脳内にインプットされているからです。
どうしても思い出せないとモヤモヤした際には、脳トレだと思って、記憶したときの周囲の状況を思い返してみてください。
- 心で覚える

工藤 正悟- お笑い芸人の島田紳助さんの言葉です。
学生時代に勉強した内容は覚えていないのに、学生時代に体験した嬉しかったことや悲しかったことなど、感情が伴う記憶は具体的によく覚えている。
感情で記憶すると物事をよく覚えられ、聞く方も具体性が増すので聞きやすいらしいです。
トークがうまい芸人は感受性が豊かで感情の起伏が激しく、体験の多くに感情が伴うため上手く話せるらしいです。
仕事に置き換えると次の2つがポイントになるのではないでしょうか。
①クレームはすごくよく覚えられるので要注意。
②覚えてほしい内容には感情に関する言葉を添える。
・これが解決すると、安心しませんか?
・今すごく困っているこれをどうにかしませんか?
・仕事の目的を社員に伝える→自分の仕事はすごい!→仕事の目的が社員に根付く。
- 生まれたての名案はない。

丹下 優子- アイデアを出す時は、まずは名案か愚案かを問わず沢山の案を出すことが大切です。
ある業績向上会議で、なんならダメ案や、すぐ却下されそうな案を優先的に出してみようと提案したところ、ユーモアある多くの案が出されたそうです。
その中に、広告塔に有名人を使う!というものがあり、最初は突飛な案という意見もありましたが、当時今ほど有名ではなかった芸能人に比較的安い広告料で依頼することができ、会社の知名度を大きく伸ばす結果となったそうです。
意見を出すことは勇気のいることでもありますが、愚案の少し横に名案はある・・・という言葉もあるそうですので、恥ずかしがらず、どんどん発言してみることもよいことかもしれません。
- 言葉の贈り物

石原 あい- 「つんどく」という言葉をご存知でしょうか。
積み木の積むという字に、読むと書いて積読と言います。
これは、入手した本を読むことなく積んだままにしている状態を意味する用語で、明治時代に生まれた言葉だそうです。
そしてこの積読という言葉は、世界に誇るべき日本語だと言います。
ではなぜこの積読が注目されているのか。
人は、いつか読みたいと願いながら読む事ができない本からも影響を受けると言います。
それは、会って話したいと願う人にも似ていて、読めない本との間にも無言の対話を続けていて、その存在を遠くに感じながらも、ふさわしい時期の到来を待っている、との事です。
また積読は、知的欲求の鏡でもあります。
その本達が日常で目に入る所にあって、自分はこういうことを知りたがっていると深層心理に刻み付けることができれば、アンテナが更に広がるかもしれません。
これは、電子書籍では経験できないことだと思います。
言葉の贈り物は、読まない本からも贈られるという事を今回初めて知りました。
- 過大評価をする

土肥 宏行- 先日ボクシングのWBAバンダム級王者の井上尚弥選手は、世界戦で 1R70秒KO勝利し観衆を熱狂させました。
ところがセコンド陣は普段通り冷静で、当然といった顔でした。
練習を見ればこの結果は想像できたからだそうです。
井上選手の攻略理論は面白く、相手の映像を見ながら最も強い姿を想像するところから始めます。
あえて相手を過大評価して
「自分 のパンチは当たらない」
「動画で見るよりも相当速い」
と想定する。
最強 バージョンの相手を考え対策と戦略を練っているのです。
そうすると実際の試合では当たらないはずのパンチが「あれ?結構、当たる」と思え楽になるのだそうです。
高校時代に自分の慢心から格下相手に敗戦をした経験から、どんな相手でも常に過大評価をして万全の状態で臨むようになったのだそうです。
ちなみにこれまでの世界戦で、相手が想定外の強さだったことは1度もないそうです。
- 会話を受け止め、応答する

柴崎 誠- 読書は何のためにしなければならないものなのか、読書をするとコミュニケーション力が格段にアップするということです。
普通の会話をしていても、読書力のある人とない人では会話の質が変わってくる。
どこに違いが出るか、それは、相手の話の要点をつかみ、その要点を引き受けて自分の角度で切り返すことです。
相槌だけでも会話は滑らかになりますが、相槌よりも高度にしたのが「自分の言葉で言い換える」ということです。
言葉を換えて同じ内容に言い換えることができれば、相手の言っている内容をしっかりと理解しつかまえていることが相手側にも伝わります。
また、会話をしていて相手が喜ぶのは、自分の言った話が無駄に終わらず相手に届いて生かされていると感じる場合です。
それが具体的にはっきりするのは、相手の話の中に自分の言ったキーワードが入り込んでいるかどうかであり、自分の発言の中でも、重要だと自分が感じていた言葉を相手が使ってくれれば、それだけでも会話に勢いが出てくるのだそうです。
- 感情のコントロールとセルフイメージ

工藤 正悟- タイガーウッズに関する話です。
2005年に行われたトーナメントで、ライバルと一緒にラウンドし、ライバルがパットを決めればライバルが勝ち、ライバルがパットを外しタイガーが決めればタイガーが勝つという場面です。
誰もがライバルのパットに対して「外せ」と思う場面で、タイガーは「入れ」と願ったそうです。
なぜ、ライバルのパットを「入れ」と思ったか、理由は2つです。
①感情のコントロール
「外せ」と思って入ってしまったら、「相手が外していたらなー」と考えてしまう。その結果、その後のプレーに悪影響を及ぼす感情が貯まってしまうため。
②セルフコントロール
自分は世界トップクラスのプレイヤーなので、自分と一緒にラウンドしているライバルも世界トップクラスのはず。よって、このくらいのパットは決めて当然である。
という自分が世界トップクラスのプレイヤーであるという自信を保つため。SMCコンペでは、ぜひ一緒に回っている方のパットを「入れ」と念じてください。
- 3つの小瓶の運命

丹下 優子- 大きさも色も形もまったく同じ3つの小瓶がありました。
1つ目には、銘酒を入れたところ、豪華な食事と一緒に並べられみんなに大変喜ばれました。
2つ目には醤油を入れました。
台所の調味料棚に置かれた2つ目の瓶は、料理人からお呼びがかかるのを待つ身となりました。
3つ目には廃油を入れました。
その瓶はゴミと一緒に置かれ、捨てられる運命となりました。
まったく同じ3つの小瓶は中身によって置かれる場所もその後の運命も大きく変わることとなりました。
人間も同様で、器の中になにが入っているかが大切だと思います。
生かせる経験の積み重ねや、相手から聞かれていることに的確に答える能力など、"中身"を熟成させることにより、置かれる場所や状況、到達できるゴールも変わってくるのではないかと思います。
- 予測する未来と創造する未来

江原 智恵子- 私たちが未来を予測するという時の未来は「このままいけばこうなるよ」といいう未来で、世の中の情勢や技術革新の流れを見ていればある程度の未来を読むことはできます。
これが予測する未来です。
これに対して、今から一年間何か新しいことに打ち込めば、これまでとは違う人生を歩むことができます。
又、毎日これまでとは違う選択をし続けると未来は変わってきます。
つまり自分の意思と行動によって未来は変えることができるということで、これが創造する未来です。
予測する未来と創造する未来、この二つの考え方が重なって戦略的な人生を歩むことができます。
未来を予測しながら、予測した未来に対して自分がどのような人生を歩みたいか、それを実現するためにはどうすればよいか、具体的に何をどう行動すべきかを考えながら毎日を過ごすことで、世の中の流れがどうであっても、自分の人生を切り拓いていけるのではないかと思います。
今日の行動で明日が変わります。
こうなりたいと思ったら、今日新しい行動を起こすくらいの行動力をもちたいものです。
- 掃除について

堺 友樹- 皆さんは、掃除は好きですか?
一般的に掃除とは、ゴミを片付けたり、窓を拭いたりします。
株式会社武蔵野では、毎朝30分間の掃除を全社員に義務付けています。
そしてその掃除を『環境整備』と呼んでいます。
この環境整備は、仕事をやりやすくする環境を整えて備えるという意義で、目的は仕事をやりやすくするということです。
仕事をやりやすくするために整理と整頓を徹底しています。
また、この朝30分間の掃除は非常に重要な社員教育の場であると考えており、社員の心を揃えるには、全員で平等に同じことをさせることが重要だそうです。
社員はやればやっただけ成果が出るため、手応えを感じることができます。
社員に嫌な思いをさせたほうが良いとの持論を持つ社長であり、やりたくないことを強制的にやらせるので、心根の優しい素直な人間が育つと言っています。
私自身、掃除も整理整頓も苦手です。
仕事をやりやすくするためということを、自分のためだけでなく他の人のことを考えるとやはり整理と整頓はとても重要で、必要なことだと思います。