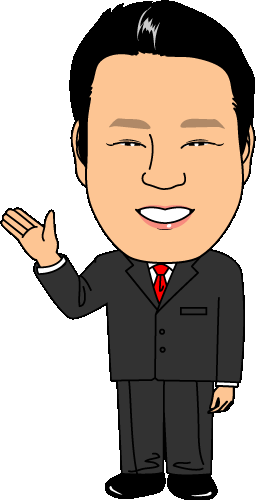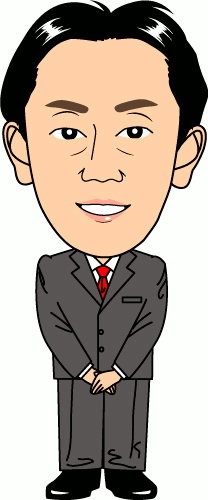スタッフのおすすめ
- 正しいと思いがちになること

工藤 正悟●人間は最後に得た情報を正しいと思う傾向がある
●人は自分の理解した世界(心理的空間)に基づいて行動を決定している
●こじつけ解釈
情報を集めて、情報に矛盾があると不安になる。
矛盾が生じないように説明できる物語を作ってしまう。
説明付けると原因追及をしなくなる●人は聴きたいものを聴く
つまり、
①自分が理解できる範囲で
②自分が最後に見つけた情報を正しいと思い
③自分の中で整合性を保とうとし
④原因追及をしなくなるその人に真っ向から「違います」というのはナンセンス
・その人が理解できるものの中で話をしよう
・真っ向否定ではなく、別アプローチ
そもそも違います→あなたは望んでいることはそれではできませんね
- ストーリーで人を動かす

竹内 純子ストーリーテリング:伝えたいことをストーリーで伝えるという手法があります。
感情を動かすことで強い印象を残すことができます。有名なのはAmazonのCMです。
大学生くらいの孫がおばあさんの家をたずね、亡くなったおじいさんとバイクで二人乗りをしている若い頃の写真を見つけます。
Amazonでヘルメットを買い、翌日届いたもので二人乗りをして、おばあさんを笑顔にするCMです。
機能面の説明やセリフはありません。
CMでAmazonによって実現した幸福を見ることによって、Amazonがあればこんなに便利で幸せな体験ができるよ、ということが強く伝わります。同様のことはAppleでもよく使われています。
ビジネスの場面でも、不満や課題を持っている相手に、その課題が解決できた具体例を紹介したりすると、ポジティブなイメージが共有でき、「自分もそうなりたい」と思わせることでぐっとひきつけることができるそうです。
- 限りある時間を大切にしよう

江原 智恵子人は限りあるものを大切にするようです。
スポーツ選手は現役選手でいられる期間には限りがあることを自分自身でよくわかっているので、その期間を大切にするように心がけていると思います。
では、自分の人生やまわりの人の人生についてはどうでしょうか?
人の命には限りがあります。
又、明日どうなるかもわかりません。
やりたいと思ったことは先延ばしにせず今やっておかないと後で後悔することにもなりかねません。又、まわりの人を大切にすることも大事です。
まわりの人も自分の命と同じように限りがあります。
日頃から感謝の気持ちを伝えたり、大切な人と過ごす時間を大事にしたいものです。
時間は無限にある訳ではありません。限りある時間を大切にしたいと思います。
- 人間はメンタルが9割

土肥 宏行目の前に幅50cmの道が20mほどあります。
この道を真っすぐ歩くことができますか?と聞かれたら大体の人が「はい」と答えると思います。では地上200mのところ所にビルとビルをつなぐように同じ道があったとして、同じように質問されたら答えはどうでしょうか?
この道は壊れないか、落ちたら死ぬのかなどネガティブなことが頭をよぎり、答えは変わることでしょう。
普通ならできることなのにネガティブなことを思考した瞬間に人間はたつことも歩くこともできなくなるのです。人間はちょっとしたきっかけで変わるのではなく、物事はトレーニングでできるようになる。平等にオギャーと生まれて話すトレーニングをして日本語を話すようになる。
歩くトレーニングをして歩けるようになる。
なぜかメンタルだけはなめられている。
やるきスイッチのようなものはないのに、その瞬間から変われると思われている。
行動を支配しているメンタルこそトレーニングが必要なのである。
- 運を自分で手繰り寄せる

土肥 宏行成功には能力と運が必要といいます。能力はあなたの個性で、運とはあなたの能力に日が当たるということ。
では運は運なのだから何もできないのか?秋元康さんは自分のヒットメーカーたるゆえんを「たくさんやってきただけ」と公言しています。
上手くいった仕事は秋元さんがやってきた膨大な仕事のほんの一部。
ヒットの裏には数知れない失敗がある。
優れた作品だからといってヒットするとは限らない。ピカソはなぜ世界で最も有名な画家になれたのか。
それは専門家が言う才能だけなのか。
15万点を超える彼が多作だったという事実があることも見逃せないと思う。成功には運が重要だから、成功、失敗に一喜一憂しても仕方がない。
ただアクションを多く打ったほうが良い。
そのことが「運」を自力で手繰り寄せることができることになるかもしれないからだ。
- 新しいものと古いものの融合

堺 友樹レトロモダンな家具や古民家カフェなど、古いものと新しいものを融合させたものが流行っている。
上記の様はデザイン世界ではうまく融合するが、では、電子機器の世界ではどうか?新しい電子機器の方が遥かに良いのはわかっていても、それが大型設備だと入れ替えるのも大変。手間も値段もかかる。
そんな場合には、設備の使用工程の一部をIot化するなど、古い機器でも新しい技術を取り入れると生産性は向上することができる。その工程を創造するのは人間の頭で考えないと出来ないものだ。
- 「速い思考」と「遅い思考」

山村 佳恵人間の思考パターンには「速い思考」と「遅い思考」の二つがあります。
本来なら「遅い思考」を使ってじっくり考えるべき場面で感情がかき乱される時などは「速い思考」が動いてしまい判断ミスを起こしてしまいます。
例えば家電量販店の値札には「限定五台!」という様に記載されていることがありますが、それを見てつい焦ってしまい、さほど欲しいと思っていなくてもつい購入してしまう、という感じです。
「速い思考」による判断ミスを防ぐ対策としては、急いで出した結論を実行する前に一度、それが失敗した時のことを考えます。
そうすることで「速い思考」で出した結論でも「遅い思考」を強制的に動かしてチェックすることができるので結果的に判断ミスを回避することができます。
- 自分で自分の限界を決めない

中澤 正裕学生時代の部活動などでよく言われた言葉です。そこでノミの話を聞きました。
人間も自分で限界を作ってしまうとその先の成長はないという話です。
ノミは自身の体長の150倍を跳躍することができるそうです。
そんなノミを蓋のあるケースに入れてみると、最初は持ち前の跳躍力で飛び跳ね、なんども蓋に頭をぶつけます。
ケースから開放すると150倍の跳躍力は失われ、ケースの高さまでしか飛べなくなるそうです。
限界が来てしまってからでは、その時はなにもできませんから、限界値を上げる工夫をしましょう。限界に近い時に考える業務効率化の方法などは非常に貴重だと思います。
- マニュアルをはずしたところに印象は残る

丹下 優子コンビニで最近は必ず「レジ袋は必要ですか?」と聞かれますが、ある店員さんが、籠いっぱいの商品と手ぶらなことを見て「レジ袋は“何枚”必要ですか?」と、荷物の持ち帰り易さに気を配ってくれたことに、タレントのマツコさんはとても感動したそうです。
何事もマニュアル通りにやっていれば安全で簡単ですが、少しはずしても相手のことを考えた言動が、人の印象に残るのだと思います。
- リンゲルマン効果を活用する

丹下 優子リンゲルマン効果とは、単独で行う場合に比べて、集団になると一人当たりの成果が減少するという行動心理のことです。
いわゆる私が手を抜いてもわからないだろう、または有能な人が目立つ中、私は評価されないだろうというモチベーションの低下などに由来します。ただ、『応援してくれる人がいる』と成果は変わらないという検証結果もあるそうです。
リンゲルマン効果ということがあることを前提に、プロジェクトは適正な人数にする、見ていてくれる人(上司など)を置くなど、適宜対応することで、最大の成果を引き出すことはできそうです。
- モラルに合わせてルールを変える

工藤 正悟1.ルールを作る目的
①業務レベルの統一
②効率化2.ルールを作るデメリット
①ルールを守ることが目的となると判断軸がルールとなる(ルールがモラルを超えている)
②決めたルールを変えられなくなる3.モラルの意味
道徳や倫理…物事の考え方や善悪の判断
SMCは顧問先の発展に貢献する…ルールはTKCだが、他のソフトの方が顧問先のためになるならば対応する(会社にとっての善)4.モラルとルールの比較
・ルールに基づいて作られるのがマニュアル
・モラルに基づいて作りるのがガイドライン(象徴的、目指すべき行き先を示す)
・ルールの動機付けはペナルティかインセンティブ(外的要因)
・モラルの動機付けは仕事感や使命感、人生観(内的要因)←ここが社員教育の目指すところルール、マニュアルは使いどころが別であることを理解しよう
大切なのはモラルにあわせてルールが変わること
- ホウレンソウの前にザッソウを

竹内 純子オフィスでの過ごし方は
①個々の業務をする時間
②会議などで顔を合わせる時間
③なんでもない会話:雑な相談・ザッソウ」の3つに分けられる。以前から「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」が大事と言われるが、実はホウレンソウをスムーズに行うには「ザッソウ(雑な相談)」が必要だそう。
ザッソウを行うことで、社内の人にいつでも話ができるという心理的安全性が高まるからだそう。あるコールセンターでパート社員同士の雑談がはずんだ場合、センター全体の幸福度が上昇し、受注率が30%向上したそうだ。
ここで重要なのは、雑談をした社員だけでなく、全体の生産性があがったということだ。変化が早い現代では、ひとりでできることは限られているので、互いに相談したりして生産性を高める働き方が重要なのかなと思う。
- 心のつながりがパワーを生む

江原 智恵子昔、2つの国で戦争が起こりました。
一方は豊かな国だったのでお金で10万の傭兵を雇い入れました。
一方の国は貧しい国でお金がないので古くからの家来1万の兵で戦うしかありませんでした。1万の兵に勝ち目はないように思いますが、なんと勝利したのは1万の兵しかいない国でした。
お金で雇われた傭兵は国王への忠誠心などありませんので自分の命が危なくなれば、とっとと逃げ出しました。
貧しい国の家来は忠誠心によって国王と強く結びついていたので、命がけで国を守ろうという強い覚悟がありました。このように「心」で結ばれた人間関係は強いパワーを生むようです。
強い人間関係を築くための基本的なことは、誠実で善良な気持ちをもって相手と付き合うことだと思います。
仕事の場合は極端にビジネスと割り切り過ぎないことも必要かと思います。
- 未完成の人生を楽しむ

江原 智恵子人は「手に入った瞬間から感動を失っていく」という心理学の法則があるそうです。
例えば、結婚する前は結婚することを望み、子供がいない家庭は子供が授かることを願います。仕事がない人は仕事のある生活を望みます。でもそれらが手に入ってしまうと理想だった夢の生活は日常の当たり前の生活に変化し、感動も少なくなってきます。マイホームも車も手に入れたいと思っている時が夢の最大値です。
憧れの世界を夢見ている状態が夢の最大値の状態です。
「成功者」とはそうした未完成の人生を楽しめる人であり、プロセスを楽しめる心を持っている人です。
今、自分の側にある幸せを、それを求めていた原点に立ち戻り、何度も何度も味わえる人が「成功者」になる可能性を秘めています。
- 仕事にのめりこむ

土肥 宏行日本人は仕事にのめり込んでいる人の割合が、世界に比べてかなり低いという結果になっています。面白くなくてもやらなければならない仕事があれば忍耐強く一生懸命やりつづけます。反面、何かに興味を持つのが苦手なようです。それは会社だけでなく学校でも、興味を持てる授業は少なく、卒業するために我慢しながら受けているという生徒も多かったはずです。
では、のめり込むためにはどうすればよいか?
キーワードは意義、課題、能力だそうです。
自分が取り組んでいる仕事内容に社会や顧客、会社にとって自分にとって何か具体的な意義を感じられるか。
次に課題。
簡単なものではなく、適度な難易度はもった課題が明確にあり、それにチャレンジしていきたいという気持ちが湧いてくるか。
最後に、自分の能力を客観的に認識した上で、この仕事こそ自分が取り組むべきものだと感じられるかどうかです。
これらが意識できればもっと仕事にのめり込めるようです。
- ネット情報に反応しすぎないために

山村 佳恵最近ネットで暗いニュースを目にする時間が多くなり、気持ちも落ち込むことが増えました。
何か対策はないかと探したところ「スマホ脳」という本に良い内容が書かれていました。
それによると、もともと人間の脳は生存のために悪いニュースを好んで選ぶ性質があるのだそうです。そのためネットでも気分が落ち込むようなニュースを立て続けに見てしまうそうです。対策としては運動が効果があるそうです。原始時代、獣を狩りやすくするために体を動かしたときに一番集中力がアップし、冷静な状態になれるように脳が進化しました。
現代人の脳も同じ仕組みになっていますので、運動することで暗いニュースを見ても反応しすぎず冷静な状態を保つことができるのです。
- 人間である以上、頭を使って働け

中澤 正裕本田宗一郎さんの言葉です。その中のユニークな話を紹介します。
人間が一日コツコツ働いた労働力を馬力で表現すると20分の1馬力となるそうです。これは扇風機と同程度の動力だそうです。動くだけの扇風機と同じパワーしかない人間は、人間にしかできないこと(考えること、人の気持ちを汲み取ること)をすることが大切であるということを言いたいわけです。
「動」にニンベンで「働」と書きます。
ただ動くだけの扇風機ではなく、人間にしかできないことをして働き、AIに取って代わられない仕事を目指すことが大切です。
- 正確な言葉より伝わり易い言葉に変換を

丹下 優子例えばですが、オーストラリアのことは豪州とも言い、文字にするとまだわかりやすいですが、聞き手としては豪州と言われても「・・・ん?ゴウシュウ?欧州?」と一度ですんなり入ってこない言葉かもしれません。
伝える・説明するなどの場面では、相手が飲み込み易い言葉や言い回しに瞬時に変換できる力は大切なように思います。
- キットカットのジャパンミラクル

工藤 正悟キットカットの売り上げが伸び悩んでいた当時、スイスの本社からキットカットの利益を5倍にしろという指示がありました。
この5倍を達成した方法はターゲットを若者に決めたことです。
語呂合わせで若者の受験などの悩みを解消するというイノベーションを起こしました。
キットカットの会社の社長は「製品自体が問題解決を実現してきた20世紀までと比べて、インターネットの登場などでデジタル化が進んだことで、現在は製品を超えたモノ・サービスでなければ、顧客の問題が解決できない時代になっている」と言っています。
また、「業績が悪いと商品開発に走りがちになる、イノベーションは商品だけでなく商品が消費者の手に渡るまでの全ての過程で存在する」とも言っています。
ターゲットを明確にしたことで生まれたイノベーションでした。
- ライバルを作ろう

中澤 正裕皆さんの周りにはライバルと呼べる人はいますか。
スポーツ、学校のテストなど周りのライバルに負けたくない一心で努力したこともあると思います。
結果的にチームが強くなったり、クラスの平均点があがったり、会社においても同じことが言えるのではないでしょうか。
大人なので、バチバチのライバル心をむき出しに仕事をするのは周囲の状況によって対応するべきだと思いますが、ひそかに誰かのこの部分はいつか超えたい。と意識してみてもいいのではないでしょうか。
- 楽しむことがどれだけ成功の原動力になるか甘く見てはいけない

竹内 純子エンゼルスの大谷選手の特集番組で、マドン監督がいっていた言葉です。
監督は「選手のやりたいようにプレーをさせるのが監督の仕事」と考えています。
大谷についても、「当番の前日と翌日も試合に出たい」という希望にあわせ、休みのルールを変更し、ほぼ毎晩大谷の体の状態を確認してからスケジュールを決めるようにしたそうです。
そこまで選手主体で起用するのは「楽しむことがどれだけ成功の原動力になるか甘く見てはいけない」からだそうです。
楽しんでいるから活躍ができ、偉大な選手になるチャンスがくるのだそうです。
- 働かないパン屋

竹内 純子「働かないパン屋」という言葉で「ドリアン」というパン屋さんが紹介された。
週6日午前中だけ働きあとは休むという「働かないパン屋」で、パンは4種類、500gか1kgのシンプルなもので2-3週間持つ。元は多くのパンを作る三代続くパン屋だった。
休業して修行にいったオーストリアのパン屋さんで、仕事が昼過ぎに終わることやパンを廃棄しないスタイルを知った。
手間は少ない代わり、材料にこだわり、手に入る「最高のもの」を使って、薪を使った石窯で焼いていた。
それまで職人が手をかけるほど良いパンが焼けると思っていたが、手間は当然料金に加算される。
オーストリアのお店のやり方ならお客さんは良い素材で作ったおいしいパンを安く買え、働く方も労働時間が半分になる。現在は拠点を田舎に移し、ネット通販のみで週4日労働のパン屋になったが売り上げは変わらず、生活の質が向上したそうだ。
- 地震の備え

堺 友樹阪神淡路大震災から27年が経過しました。
当時大阪に住んでいた人が寝ていた時に目の前に天井が目の前に迫ってくるほどだったそうです。
彼は以前、大きな地震を経験したことがあったようで、次に考えたのがトイレを確保するとこだったそうです。
庭に穴を掘り始め、トイレとして使えるようにしたそうです。
ライフラインや食べ物より、一番苦しむのがトイレだと彼は言っていました。地震の備えは一番はトイレで、特に最近はタンクレス化が進んできていますので、簡易トイレを家に準備しておいたほうが、食べ物を準備するより重要だそうです。
- 帰る場所が定まっている人は、道を踏み外さない

土肥 宏行箱根駅伝は今年も青山学院の選手が強かった。
青山学院大学の原監督は選手たちに「覚悟」を強く求めています。
なんとしても結果を出すという強い覚悟がなければ練習にも身が入らないし、結果にもつながらない。
なぜなら人は怠ける動物だからです。陸上競技部の日々の練習は1日3時間ほど。
残りの21時間をどのように過ごすかで結果は大きく変わりますが、「陸上に集中しろ!」と言われてもできるわけがないのが大学の4年間。
恋もしたいし、映画や買い物にも行きたい。
それは当たり前で、それを止めようとは思わない。
なぜなら自分が何のためにここにいるのかはっきり認識していれば歯止めは自然にかかるから。
陸上競技部のそれは「走る」こと。
そのことをいつも忘れないように生活の拠点を寮にすることは一つの方法です。自分にとっての原点、帰る場所が定まっている人は道を外さない。
- すきやばし次郎の哲学

山村 佳恵東京にある有名寿司店「すきやばし次郎」。
店主の小野次郎さんの仕事の哲学に、細かなことにもこだわるというものがあります。
例えば、お茶を熱々のうちに飲んでもらうためにお客様の食べるペースに気を配るのはもちろんのこと、最初の一杯のお茶の量にも神経を使っています。
またわさびの量もネタごとに微量に変えているそうです。こういう細かなこだわりは割りにあわないというお寿司屋さんも多いですが、目立たないことにも決して手を抜かないことが一流の仕事であると次郎さんはおっしゃっています。
- 月曜日の朝は仕事をしない

中澤 正裕業務時間内において1週間に2時間は自分を磨く時間として学習の時間を設けることを推奨されている企業があります。
ある人は、当初金曜の朝にその時間を設けるようにしていたそうですが、日々の業務に追われて結局はできなくなってしまっていたそうです。
月曜朝にその時間を設けて、その時間に顧客対応などは行わないようにしたそうです。
その結果、日曜日の夜に憂鬱にならなくなったり、仕事へのモチベーションにも変化があったそうです。公にそのような時間がない企業である場合は、いつもは金曜日に整理していた書類やデータを月曜日の朝にやるようにするのもよいでしょう。
時間の使い方で仕事へのモチベーションにも影響があることを意識していきましょう。
- 従業員エンゲージメント(愛社精神)を高めると会社はよくなる。

丹下 優子パプアニューギニア海産という会社では、“嫌いな仕事はやってはいけない”というルールがあるそうです。
また、好きな時に来て好きなだけ働いていいという決まりも。働き方の多様性を認めてもらっている従業員は、足りない所を補い合い高め合い、商品の品質も業績も向上しているそうです。
自分の能力を発揮して、務めている会社に貢献しようと思う気持ちのことを従業員エンゲージメントというそうですが、これが高い会社のほうが物事がうまく回っているそうです。
全ての会社でできることではないかもしれませんが、従業員に気持ちよく働いてもらい、より一層貢献してもらえる仕組み作りは、参考にできるところがあるかもしれません。
- 高級飲食店はアンケートを取らない

工藤 正悟脳科学者 茂木健一郎さん曰く、高級な飲食店ほど「食事は良かったか、おいしかったか」などのアンケートは取らないそうです。
アンケートを取らなくてもお客様の様子を見ていれば良かったかどうかは分かるからだそうです。
逆に、アンケートを取る飲食店は上手くいっていないことが多いとのこと。この話はアンケートを取るべきかどうかという話ではなく、お客様の反応を見ているかというサービスの本質が表れています。
「料理を提供する」が仕事ではなく「お客様が満足するサービスを提供する」意識の差であり、常に評価はお客様の中にしかないことを意識している差が表れています。
- 楽しむ力

江原 智恵子マラソンの高橋尚子選手がシドニーオリンピックで金メダルを取った時、レース後のインタビューで最初に言った言葉が「楽しい42.195キロでした」という言葉でした。
辛かった、苦しかったではなく、「楽しかった」という言葉は意外でした。同じように、周りからみると大変だろうなぁと思う仕事でも、やっている本人は意外と楽しんでやっていたりするものです。
「楽しむ力」がある人にとっては、どんなことでも楽しむことができるのだと思います。
楽しい仕事がどこかに転がっているわけではありません。
自分自身で何でも楽しもうという気持ちが大事だと思います。小さなことでも仕事が楽しいと思えることが続けていく原動力になると思いますので、自分なりの仕事の楽しみをみつけて頑張りましょう!
- お店のスタイルにお客が合わせる

竹内 純子都会から離れたエリアで、店主一人で独自のスタイルで営業するお店が結構あるそうです。
普通に考えると、メニューが少ない、時間がかかる、車でしか行けないと不便なことばかりに思えます。
成功している例は、一日一組だけの一軒家レストランです。
数か月先の営業日が発表されたら、メールで申し込み抽選予約となり、すぐ満席でほぼキャンセルもないそうです。
コロナになってから、こういった「お店の人もお客さんも少人数で、人の少ないエリアのゆったりしたお店」を、限られた機会に利用したいと感じる人も増えたようです。本来であれば不便なはずのお店のこだわりが、コロナで価値観が変わり、他のお店にはない魅力になってくるのかもしれないなと思いました。
- マーケットの未来をみる

江原 智恵子今後ますます少子高齢化、人口減少が加速することは誰もがわかっていることで、コロナ禍が落ち着いた後もこの事実が変わることはありません。
むしろコロナ禍になって消費が大幅に減少したことは、人口減少後の国内マーケット縮小を早い段階で実感することになりました。これからは少子高齢化、人口減少という変えることができない事実によって世の中がどう変わるのか、マーケットの未来をみる力が必要になります。
今後は未来をみながら相手にとって必要となるサービスは何かを考えながら仕事を創造する必要があると思います。
- 毎日一生懸命、当たり前のことを当たり前に

土肥 宏行アメリカのメジャーリーグ(野球)、サンフランシスコジャイアンツの「ブルペン捕手」から「アシスタントコーチ」になることが決まった植松泰良さんの言葉です。
1年間以上のコーチ契約は日本人では植松さんが初だそうです。
植松さんがどうやって信頼を得たのか。
ブルペン捕手の仕事は、当番直前のピッチャーのボールを受けマウンドに送りだすこと。
言葉にするとシンプルな仕事ながら、植松さんは自分なりの色を出すことを意識した。
キャッチングをする時にミットの芯で受けると「スパーンッ」と快音が響く。
アメリカでは周りにこのようなキャッチングをする人がいなかった。
超一流のピッチャーの球を毎回ミットの芯で受けるのは至難の業で、高い集中力と技術が必要。
だが毎日毎日続けた結果「気持ち良く投げられた」「球が速くなる感じがする」とピッチャーから信頼されるようになった。
- 一番を決める

堺 友樹例えば、2つの効果を期待したいと思い、ハーブティーを購入するとします。
①アレルギー改善
②冷え性改善
しかし、どちらかしか取ることができない時には、迷うことがあります。
迷うときには1番欲するものは何かを決めることです。
仕事では、お客様の1番欲するものは何かをお客様に決めてもらうこと。
物事を決める時には、1番が何かを決めることが重要だと思います。
- 「みる」には二種類ある

山村 佳恵「みる」という動作には確認するだけの「見る」としっかり観察する「観る」があります。
百貨店の伊勢丹のスタッフは観察能力に長けた人が多いそうです。
売り場に来たお客様を早くから観察することでお客様にとって的確なアドバイスをすることができます。
また、京都の伊勢丹のスタッフは来店したお客様が東京から来てその日に帰る事を観察で見抜き、京都はその日は快晴だったのですが東京は雨の予報だったため品物に雨除けのビニール袋をかけてお渡しし、お客様を感動させました。私も業務中は「観る」方を常に意識したいと思います。
- 業績を伸ばした飲食店

中澤 正裕最初は思うように客足が伸びなかった飲食店の話です。
その打開策として直接お客様にお店の悪いところを聞くようにしたそうです。直接聞くことが良いことなのか、良くないことなのかということは置いといて、客観的な意見によって変化をもたらしたかったのでしょう。
「我々の顧問料(商品)をあと3万円上げるにはどうしたらいいですか?」と直接聞いてみるのも良いかもしれません。間接的に商品への不満や、担当者への不満、ニーズが漏れるのではないでしょうか。お客様の本心を聞く機会になるかもしれません。
- 周りの良い点を探そう

丹下 優子タレントのアンミカさんは、人や物の良い所を探すことが得意だそうです。あるテレビ番組で「その白いおしぼりを褒めてみて」と言われ、間髪入れずに「白には200色あんねん!このおしぼりの白は日本人の顔色を一番キレイに見せる白で・・・」と、淀みなく良い所を話していました。
褒められて嫌な気がする人はいないでしょうし、周りの素晴らしい所をみつける習慣がつくことは、何より自分が気持ちのよい日々を過ごせることにも繋がるのではないでしょうか。
- 商品知識とは

工藤 正悟日本のある実業家は、商品知識とは「相手が何を求めているか知ることが商品知識である」と言っています。この言葉は非常に大切だなと思い発表させていただきます。
東京にある古田土会計が主催しているKODATO杯という、試算表を読み解く力と伝える力を競う大会の問題を見ました。とても難しい問題を扱っていて、自分ならどう答えるか悩むレベルでした。
我々の仕事の成果物が試算表・決算書とするならば、それを伝えることは「商品の説明」となります。
顧問先の社長がアドバイスを求めているとするならば、商品知識とは商品(試算表)から社長が求めているものを読み解くことであります。
顧客の求めている事を聴き、商品を適切に活用する、両方揃って初めて商品知識となるそうです。
どちらのレベルも高めていかなければなりません。
- 「人」の成長について

尾﨑 清真フィギュアスケーターの羽生選手はインタビューで「努力は嘘をつく」と言っています。
「人」は、生まれた時は他の動物と同じで本能のみで生きています。
さらにそこから学び続け、多くの経験を得ることで「立派な人間」として成長することが出来そうです。
様々なことを学び、経験することで「人間」として成長することができます。
今日の自分を明日の自分が超えていけるように日々学び、多くを経験することを忘れず、5年、10年先も今の気持ちを持ち続けることが大切であると思います。
- WinWinのサービスを提供する

江原 智恵子コロナ禍において医療の現場もサービスの形を変えています。
オンライン診療や電話診療です。このサービスは病院側と患者側の双方においてWinWinであると思います。
病院側は感染対策としてなるべく患者に接触せず短時間で効率よく診療できる。患者側も待ち時間などの負担も少なく早く診察を受けることができる。
双方にメリットがあるサービスです。
①相手が求めるサービスを提供する。
②サービスを提供する際には生産性を下げないようにシステム化する。
③緊急時にはスピード感が相手にとっての満足度になる。
この3つを意識したサービスを心がけたいと思います。
- 空気を読む力はあるけれど、あえて読まない判断をする奴が、本当に空気を読めるやつ

土肥 宏行空気を読むというと、相手に同調したり、その場の空気を壊さないというイメージです。
ただし仕事においては、人間関係の維持を仕事の本質、大事なものより優先させてはいけないでしょう。
仕事は、人とは違う気付きやアイディアをどんどん出して、積み重ね、上書きして作っていくものだと思います。
時には異論として、時には反論として。
だから良い仕事をするには、あえて空気を読まず、空気を壊していく姿勢も必要になります。
ただし何でもかんでもぶち壊して孤立しては意味がありません。
そうならないよう普段から信頼関係を築き上げ、ストレートな言い方などお互いにできる風土を作っていくことも大事です。
- 節税について

堺 友樹節税と思っていたことが脱税で逮捕される事件が起きたり、You Tubeでも税理士が『所得税をゼロにする方法』などを紹介したりしています。
中身を見ると税金を下げることを目的として損をしていると思われるようなことばかりですが、こういったことに影響される人も多いのが現実に存在していると思います。我々は相手に儲けてもらうこと一点に集中すべきで、他の税理士と集中すべき点が違うことを認識しなければならないと思います。
- 努力は嘘をつく

山村 佳恵フィギュアスケーターの羽生選手はインタビューで「努力は嘘をつく」と言っています。
「努力が嘘をつかないのだったら、やっぱり練習量が一番多い人が毎回毎回優勝できると思う」だから努力は嘘をつく・・・のだそうです。
また羽生選手は、「努力は嘘をつくけども、努力の正解を見つけることこそが大切」だとも言っています。
この意味を私なりに解釈すると、ただ時間をかけて闇雲にこなしていくのではなく、自分なりに考えをめぐらせながら努力をしていくことだと思います。仕事の上でも目の前にある仕事をただ時間をかけて力業でこなしていくのではなく、常に頭のすみで効率化などを考えたりしながら進めていくなど、こういったことが行動が努力の正解になるのではないかと考えます。
- ペース配分と力配分をコントロールする。

丹下 優子400m走の極意は“ペース配分”
400mすべて全速力のようだが、実際にはスピード維持のタイミングで体力の温存を図ることがコツ。
何においてもずっと全力投球はできない。そでは逆にパフォーマンスが落ちる。
雑にやれという意味ではなく、自らの能力100%で臨むことと、30~40%の力で完成させる事柄のメリハリをつけることで、本当に重要なところに120%の力をもっていくことができる。
要は、自らが『長く早く』走れる方法を見つけ出し実行することが生産性を上げるポイント。
- 危機感の継続期間

工藤 正悟民間リサーチ会社が週刊でアンケートを取った結果
①1,000人調査
コロナへの意識が大きく変わった出来事1位3月下旬(五輪延長、志村けん死去)26%
2位4月上旬(定額給付金、全国緊急事態宣言)18%以下、2020.6月まで10%以下
②3,000人週間調査
コロナに対し不安がある人の割合3/23…72.8%
3/30…81.7(五輪延期3/24、志村けん死去3/29)
最大は4月上旬83.6%
その後6月下旬64.7%までゆるやかに減少
80%を超えていたのは3月下旬~4月下旬の1か月のみ
その後、2021.7月まで80%超なし。70%台をいったりきたりコロナでも不安感が1ヶ月しか持続しないので、仕事においては「こういうことに気を付けよう」や「これを意識しよう」程度の警戒は1か月も持たないのではないでしょうか。
- パラダイムシフトについて

尾﨑 清真コロナ禍において、世界全体でパラダイムシフトが起こり、リモートワークの普及など、目まぐるしく様々な出来事が変わる中でも変わらず大切なこともある。
数年前より言われるようになったフィデューシャリー・デューティー(顧客本位の業務運営)はこれから先も大切なことであり、様々なことが変化する中でも、The SMC wayの「お客様に関する方針」にもあるように相手の立場に立った考え方をしっかり持っておくことが大切であると思います。
- お得意様が損をする 中国のダイナミックプライシング

竹内 純子中国のネット通販ではビッグデータをもとに分析され商品の値段が変わるダイナミックプライシングが使われている。ここでおもしろいのは、お得意様が高い価格になっていることだ。
日本でも飛行機のチケットが時期によって変わることは定着している。
中国はさらにスマホから個人情報を集め、その人が許容できる価格を算定する。高級住宅地に住んでいたり、iphoneを持っていると価格が高くなったりするそうだ。さらに使い始めは安く、お得意様には高い値段が表示される。
これは中国ならではの「たくさん買った人」が得をするのではなく、これから「たくさん買うであろう人」が得をするしくみになっているからだ。こういった方向に進むと、サイトに利益をもたらさない人や、返品が多い人などはか価格でふるいにかけられて排除されていく可能性もある。
- 成功を派手に応援する

土肥 宏行スティーブジョブスやアマゾンの創業者達に彼がいなければ成功できなかったと言わしめるほどの影響力を持った人ビル・キャンベル。彼は人の最良な部分を引き出す。
ある時Amazonで社員が取締役に対し製品の説明をしていると、その場にいたビル・キャンベルは、立ち上がって大きな手拍子を5回したそうです。
「君たちのやっていることは間違ってない、そのまま進め!」と言う気持ちになる。
たった一つのジェスチャーでその場の全員に弾みをつけたのだそうです。Amazonではこのビル・キャンベルクラップ(BCC)をチームの文化に取り入れている。ミーティングで何か良いことを発表すると、全員で大きな手拍子を5回するのだ。オリエンテーションでは手拍子の練習までさせている。
手拍子で彼らの成功を派手に応援する。SMCでも皆で成功を応援したいと思い紹介しました。
- ルールについて

堺 友樹テニスの4大大会のうち、全英オープンでは厳格なルールがあります。
それは、選手は白を基調としたものを身につけるというルールです。
それは汗を見せないためであり、色付きのシャツより白シャツの方が汗を見えにくくし、見た目も良いためという理由です。ルールは必ず、理由があって存在します。よってルールを守ることが原則です。
しかし、最近のシャツは鹿の子シャツより吸汗性に優れたものも多々出てきています。
ルールに必ずある理由が変わるなら、臨機応変に我々も変わる必要があると思います。
- 怒りをコントロールする

山村 佳恵最近よく聞く「アンガーマネージメント」を怒りの段階別にご紹介します。
レベル1:まだ怒り初めの段階。怒りのピークは6秒といわれています。その場を離れるなどして6秒間耐えれば弱い怒りなら自然と引いていきます。
レベル2:怒りが態度や言葉に滲み始めてきた段階。あらかじめ、怒った時に言うセリフを決めておくのが有効です。そのセリフを思い出すプロセスも冷静になるのに良い時間になります。
レベル3:怒りが抑えきれずに前面に出てきてしまった段階。怒っている自分を上からのぞき込んで見ているいわゆる「幽体離脱」しているイメージを頭に描くのが効果的です。他人の視点で自分の姿を見ることができますので、一気に怒りの感情がひきます。
怒りの感情に振り回されないためにぜひ参考にして頂ければと思います。
- 礼に始まり、礼に終わる

中澤 正裕柔道で金メダルを獲得した阿部一二三選手は、優勝が決まった瞬間、畳の上では、喜びませんでした。
武道の精神である「礼に始まり、礼に終わる」という精神から来ているものです。礼をわきまえることは人間関係をスムーズに、関係を良好にすることにつながると思います。
礼というと、挨拶、会釈という行動にフォーカスしてしまいがちですが、相手に対して尊敬・感謝できる心の持ち方が大事だと感じました。
良い仕事をするにはお互いの良好な関係が重要だと再認識させられました。