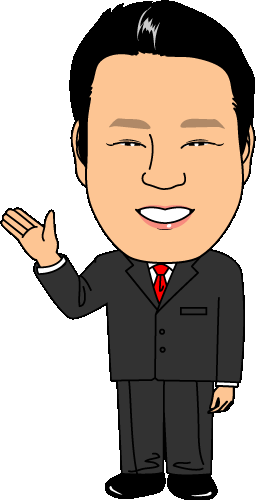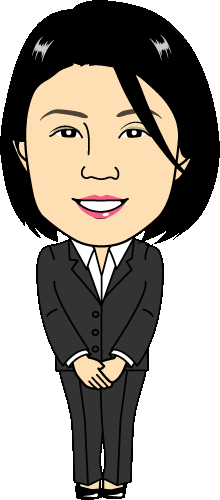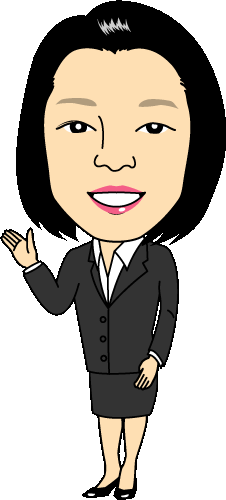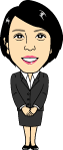スタッフのおすすめ
- 能ある鷹は爪を隠す

堺 友樹- 私が中学二年の担任の先生から三者面談中に私について言われた言葉です。
当時の私は爪を出しまくっていた様で、それを心配して先生が言ったのだと思います。
日々の業務でお客様の心に刺さる言葉を発する場合、いつもは爪を隠していてもいざというときに爪を出すような発言になると、相手も信頼するのだと思います。
最近のシェア会議でシミュレーションをするようになりました。
そこで私は早口でしゃべっていることを指摘されます。
そこからの反省で、いつもなら言葉を発する場面であっても、相手の話したいことをじっと聞いて、ここぞというときに相手に伝わるようにゆっくり話す。
そうすることにより、相手に言葉が伝わり、想いが伝わるのだと思います。
今後は、いつも心掛ける言葉にしたいと思います。
- どんな人と出会うかは、その人の「命の器」次第なのだ

石原 あい- これは宮本輝さんの「命の器」というエッセイ集の中にある一文です。
運の悪い人は、運の悪い人と出会いつながっていく、
へんくつな人はへんくつな人と、心の清らかな人は心根の清らかな人と出会いつながりあっていく。
類は友を呼ぶ、ということわざが含んでいるものよりもっと奥深い法則が人と人の出会いを作り出しているとしか思えない。
伸びていく人は、例えどんなに仲がよくても知らず知らずの内に落ちていく人とは疎遠となり、いつの間にか自分と同じ伸びていく人と交わっていく。
不思議としか言いようがない。
企んでそうなるのではなく知らぬ間にそうなってしまうのである。
抗っても抗っても、自分という人間の核を共有している人間としか結びついていかない。
その怖さ、その不思議さ。
最近やっと人間世界に存在する数ある法則の中の一つに気が付いた。
出会いとは決して偶然ではないのだ。
といった内容が書かれています。
どんな人と出会うかは全て自分次第、相手がどうだと言う前に、まずは自分の器を磨いていくことが重要だと感じました。
- 白黒つけない難しさ

野本 理恵- 久しぶりに田坂さんの本を読みました。
その中に、「腹決め」という言葉があります。
何かに迷ったときに、割り切って白黒つけるのは簡単です。
それは一見素早い決断力があり、お客さまにも説得力があるように見えます。
しかし、迷うことを辞めて、選ばなかった方に何か言い訳をして、 もしかしたら、相手に悪い理由を押し付けて自分の負荷を下ろそうとしているとも言えます。
腹決めとは迷うことを辞めずに考え続け、結論を出しても迷ったその事実を自分で持ち続けることです。
だから決めても負荷がなくなるわけでもありません。
割り切ることと腹決めにはこちらの心の姿勢が全く違います。
私達のこれからの仕事にはこのような白黒きめられない、答えのない難しさがあり、ここからに逃げないことがお客様に対しての高い付加価値を実現できると思っています。
- WINWINのサービスを考えよう月間MVP

江原 智恵子- 車のメーカーアウディでは、車の定期点検やちょっとした修理で車をお預かりする際に必ず手洗いの洗車サービスがついてくるそうです。
アウディはベンツやBMWと比べると少し見劣りするブランドとして位置づけられているようですが、ここ数年販売台数を大きく伸ばしているようです。
その要因として車そのものの価値の向上だけでなく様々なサービスというホスピタリティがあるようです。
洗車以外にもフロントの男性は全員ネクタイでスーツはユニフォーム、Yシャツは胸にロゴが入ったものを着ているそうです。
飲み物が出される時も陶器のカップでほんのりキャラメルの香りがするそうです。
かといって、言葉づかいなどは必要以上に丁寧過ぎず、極端に敷居が高い訳でもない。
これによって、ディーラーに足を運ぶ回数が増え、次もここで買おうという気持ちになり、結果としてリピート客を一人確保できたことになります。
洗車の話に戻りますが、なぜアウディが無料で洗車をするのかというと、街を走るピカピカのアウディを見てもらいたいのだそうです。
アウディの弱みはブランドの認知度なので、実際に街を走るお客様の車が広告宣伝物になると考えている訳です。
お客様にとっては自分の車を洗車してもらえるので単純に嬉しいし、会社も広告宣伝として考えているので、両者にとってWINWINな訳です。
ここまで考えたサービスはすごいなと思いましたし、何か参考にできたらいいなと思いました。
- 答えが返ってくるまでの沈黙を恐れない

永山 友梨子- カウンセラーやコーチングのコーチは聞き手のプロです。
カウンセリングでは、相手の内面のかなり深い部分にたいして問いかけをしますが、深い質問には聞かれた側も自分の内面に深く降りて行って答えを見つけ出す必要があるので、言葉にするのに時間がかかります。カウンセラーは、相手が話し出すまでの時間をじっくり待つのだそうです。
トレーニングを受けていない人は相手が答えを見つけ出すまでの時間になかなか耐えられず矢継ぎ早に質問してしまい、そうするとかえって相手から深い話を聞き出すことができません。
質問にすぐに答えられる質問とすぐには答えられない質問があることを理解し、聞く側には待つ覚悟が必要です。
待てない場合はその場を離れて相手に考える時間を作ったりすることも有効だそうです。
かえしてみれば、お客様からの質問もすぐに答えが出る質問とじっくり考えるべき質問があることを私たちは理解すべきです。
質問の内容がすぐに答えるべき・答えられる質問であるのか、あるいは持ち帰ってじっくり考えるべき内容なのか、よく考えてから言葉にすべきであると思いました。
- 意見と人間性は別

吉田 昇平- 外国の方々の多くが、日本人は議論をするのが苦手という印象を持っているようです。
その大きな理由は「人間性と意見を同一視する」ことだそうです。
簡単に言うと子供の「〇〇くんは僕と反対の事を言うから嫌い」が大人になっても変わらない、という人が多いということです。
会議の場では大いにやりあって、その後一緒に飲んで帰る。
というような光景は確かにあまり見ません。
ディベートを有意義なものにするためにはいろいろな意見で場を活性化させなければいけないのですが、意見≒人間性という認識があると、多くの人が思い切った意見が言えなくなります。
会議を活性化させたければ、まず意見と人間性を切り離す。
つまり意見で人を嫌いにならない意識を持つべきなのです。
- 挑戦し続けること

幕内 彩乃- 「私は決して強運ではないが、これだけ幸運に恵まれたのは挑戦し続けたからだ」というのは、ニトリ家具の似鳥昭雄会長の言葉です。
幼いころは親の闇米屋の手伝い、高校・大学入学は裏ワザを企て、大学時代はスナック未払金の取り立てや、入社した会社では仕事をさぼってパチンコなど、破天荒な人生を送っていました。
そんな会長が23歳の時に立ち上げた似鳥家具店は赤字続きで倒産寸前の危機に瀕し、藁をもつかむ思いで行ったアメリカ視察。
当時の日本人の年収はアメリカの三分の一にも関わらず、日本の家具の値段はアメリカの3倍もするのを目の当たりにし【何とか日本人の生活を豊かにしたい!】と思いました。
アメリカ視察を何度もするうちに家具のトレンドや価格調査だけでなく、住宅価格についても定点観測を続けていたところ気が付いたのが、ごく短期間に住宅価格が2~3倍に膨れ上がっていること。
これは明らかにバブルの兆候であって、そのあとには必ず反動がくる事は歴史的な事実です。
そこで今はコストを大幅に縮小させて50億の資金を準備し、好機を窺い、ここぞというときには挑戦し続けた。
この挑戦の継続が創業当時には全く売れなかった家具が、今や売上1000億円という大企業になっています。
時代を見抜く力と挑戦する気持ちの強さに感銘を受けました。
- 「内部要因思考」がないとリカバリー力がつかない

柴崎 誠- 何か意思決定をしてうまくいかなかったとき、最初のリアクションが愚痴から始まってしまうと、リカバリー力がないということです。
人のせいにしてしまうと、意思決定そのものに力がなくなります。
失敗の要因を外部に求めてしまってもその外部要因は変えられません。
しかし、内部=自分であれば訓練ができます。
やり方を変え、力の入れどころを変え、考え方を少し変えることでリカバリーが可能になるのです。
リカバリー力をつけるとするならば失敗した要因をすべて自分に求める「内部要因思考」に切り替えてみることです。
「すべては自己責任である」と引き受けること。
言葉にすると厳しく聞こえますが、裏を返せば自分で決められるということです。
自分が決めたことによって、自分が招いた結果であれば自分自身の力で良いほうにさらに変えることができるということです。
- 想うことがすべての始まり

丹下 優子- 「キリンの首が長いのは高い所にある草を食べようと首を伸ばしたからだ」
という、ダーウィン以前の進化論が、最近見直されているそうです。
母キリンは、首が長ければ子供達においしい食べ物をもっと上手に食べさせられるなーと首をめいっぱい伸ばす・・・。そんな強い想いが世代を超えてどんどん遺伝し、生物のフォルムをも変えていったのだとしたら、想うということは、どんなに強いものなのでしょうか。
ちょっと現実離れした話のようではありますが、仕事も成功も、心から想うことがすべての出発点なのだと、あらためて感じました。
- 10,000時間の法則

工藤 正悟- 高い業績を残すために必要な修練の時間は10,000時間と言われています。
これは仕事でもスポーツでもそうで、10,000時間に達するまでの成果と、10,000時間に達してからの成果を比べると、圧倒的な差が出るというものです。
高い成果を残すのに必要なのは、10,000時間の「修練」であり、そこにただいることではないので、単純に10,000時間分出勤をした社会人が高い成果を残すわけではありません。
ただ、どの行動が修練に当たるのか、何時間やったのかをいちいち覚えて行動する人はいないので、一つの目安として紹介しました。
~10,000時間という目安の使い方~
① 思った成果が出なくてつらいとき→10,000時間経ってないから当たり前か!と開き直る。
② 自信をつけたいとき→これだけ時間を割いた(10,000時間時間を費やした)から出来るだろう!
③ 自分の行動を見直すとき→こんなに頑張ってるのに効果がでない…時間は費やしてるけど行っている内容が修練じゃないかも。
- 「配慮と忍耐が差別(しゃべつ)をもたらす」

齋藤 章子- 『星の王子、禅を語る』という本にかかれていた言葉です。
差別(しゃべつ)とは、仏教用語の一つで、個性の違いのような意味合いで使われるそうです。
仏教の思想の根底には、空=万物は空虚なものであるという思想があり、その空虚な世界に差別をもたらすのが、配慮と忍耐ではないかと書かれていました。
自分で育てた1本のバラと公園のバラの違い、目で見ただけでは同じものなのに、そこには毎日水やりをして枯らさないように気を配る、そのような時間をかけた配慮と忍耐があってこそ、1本のバラは自分にとって特別な存在になるのです。
ビジネスの世界では、数字という目で見えることが大切で、それは正しいのですが、逆に目に見えないこと、配慮と忍耐もまた重要であるのではと感じました。
- ハングリー精神と自分自身を信じる事

榎本 恵亮- 文房具で有名なメーカー、パイロット社が開発したヒット商品に消せるボールペンの「フリクションボール」という商品があります。
この商品は30年間商品開発を行われたそうです。
30年間研究開発を継続することができた理由はなんだったのでしょうか?
1つ目は、「開発者達が自分たちの食い扶持は自分たちで稼げというハングリー精神に溢れていたこと」。
2つ目は、「自分たちが生み出した技術を何としても世の中に広めたいという強い気持ちを持っていたこと」。
3つ目に「自分自身をとことん信じていたこと」。
この3つの信念があり完成をさせる事が出来ました。
この信念はパイロットの社員に限らず優秀な社員や社長も共通してもっている信念でもあるそうです。
自分を信じられない人、自分が描いたビジョンを信じられない人が、他人を説得することも難しければ、他人を巻き込んで事を成し遂げることは難しいとの事です。
またお客様に自信をもってサービス・商品を提供することでお客様に安心感や信頼感も与える事ができるのだと思います。
成功するのに必要な重要な考え方であると感じました。
- 「苦難は幸福の門」

堺 友樹- 倫理研究所の創設者、丸山敏雄氏の言葉です。
世の中には病気であったり、交通事故であったり、その他たくさんの苦難というものがある。
それら苦難を乗り越えた時、幸せを感じるものである。
苦難は幸福を得られる小さな扉であるので、苦難だと感じることがあっても、その先にある幸福を目指していこう。
- 人は二回死なない

野本 理恵- ジャパネット高田の高田前社長の言葉です。
トップリーダーの「なぜうちの社員は失敗を恐れるのか」という記事の中で失敗に対しての考え方についてお話していました。
どんな人でも1回産まれて1回死ぬ。
1度きりの人生、常にチャレンジして失敗を恐れないというメッセージでした。
たった一度の人生に自分自身も感謝してチャレンジする勇気を与えられた言葉でした。
- 自分の逆から見る

土肥 宏行- 水族館プロデューサーの中村さんが手がけている水族館に北海道の「山の水族館」があります。
人気のある海水魚ではなく淡水魚だけを集めています。
ここは見せ方が特殊なのです。
例えば北海道の一年の川をイメージし、冬は氷の下の魚の世界、夏は水量の多い激流の中を泳ぐ魚の世界。
また滝壺の下の世界なんかも表現してもいます。
どれもどうなっているのかな?と想像しても見たことのない世界ばかりです。
昔の水族館は、徐々に盛り上げて演出のため、最後の方に大物を展示していました。
お客さんはチケットを買ったら、よし見るぞ!となってまず展示してあるイソギンチャクとかを一生懸命見るのですが、最後の大物を見るときには疲れてしまっている。
つまりまったく逆の展示をしていたのです。
そんな経験からお客さんが本当に見たいものに近いイメージのものを作ることがポイントだと思ったのだそうです。
山の水族館は主役を魚ではなく、魚が泳ぐ世界(空間)を主役にしました。
そこがヒットの要因のようです。
- 「話す力、聞く力よりも大切なものは問いかける力」

渋谷 佳代- (マサチューセッツ工科大学(MIT)の名誉教授:エドガー・H・シャイン氏の言葉)をお勧めします。
?コミュニケーションにおいて、話す力や聞く力はしばしば重視されています。
一方で、発言を控えて、「問いかける力」を高めようとする人は少ないそうです。
問いかける技術とは、ただ単に丁寧に質問すれば良いわけではありません。
自分では質問しているつもりでも、結局は自分が言いたいことを、質問の形式に置き換えただけだったり、自分が正しいことを確かめるために、相手に質問していることがあります。
相手を診断したりするような質問も、もちろん「問いかけ」には当たらないそうです。
顧客と面と向かってビジネスをする場合は、顧客の要望を聞くことが必要です。
的外れな質問をしてはいけません。
顧客に興味を持ち、それが伝わる問いかけを行うことが謙虚に問いかけるということです。
- 常に準備しておけ

幕内 彩乃- 「いつ来るか分からない15分のために常に準備しているのがプロフェッショナルで、来ないかもしれないからと言って準備していないのはアマチュアだ」
とはインダストリアルデザイナーの言葉です。
彼は日本人で初めてフェラーリ車体のデザインをした男として有名です。
彼は一瞬のすきを捕まえて自分を売り込む重要性を訴えています。
大プロジェクトで新しいデザインの車を出すとなった時に、最後のチャンスで会長に準備していたデザインのスケッチを見せたら、即採用、徹夜で仕上げたというエピソードがあります。
アメリカでは30秒250文字の短い時間少ない文字で、要点を絞り分かりやすくプレゼンをすることが重要だと言われています。
会長はすぐ帰ってしまうかもしれない、投資家にはエレベーターでの短い時間でしか話しかけることができないかもしれない。
だから常に準備しておかなければならないのです。
- 「ありのままの自分」は怠け者の甘え

吉田 昇平- 江戸時代、白隠という禅宗の僧侶がいました。
当時の禅宗にはさまざまな考え方の人間がいて、あらゆる儀式を虚飾だとして無視する者、心のままに生きるのが修行だと言い、好き放題する者。
そんな者たちに白隠は
「白木の器も最初から漆を塗らなければ剥げてきたなくなることもないという小理屈をこねてありのままが一番とうそぶくのは愚か者のすることだ」
と断じました。
世の中には飾り気のないことを称賛されるひとやものがありますが、元々飾り気がないのではなく訓練の結果無駄が削げ落ちた姿がそれなのです。
「型破り」という言葉がありますが、何の努力もなしに型を持たないのは「型破り」なのではなく「形なし」というのです。
- 自分との約束を守る

江原 智恵子- 相手との約束はほとんどの場合が守られると思いますが、自分との約束はどうでしょうか?
相手がいる場合には、約束を守ることに強制力が働くと思いますが、自分との約束の場合には、仮にその約束が守られなくても誰かに責められたりすることはありません。
でも、守れなかったという事実は自分の心に残りますし、何より自分が一番よくわかっていることなので、自己嫌悪や自己不信に陥ってしまう可能性もあるそうです。
又、これが続くと自信を失ってしまうことにつながってしまうそうです。
本当の自信というのは、自分との約束を守るという覚悟とその達成の積み重ねで生まれてくるものだと思います。
相手との約束はもちろん大事ですが、自分との約束を守ることも自分に自信をもつ為に必要な事だと思います。
- 「聴く」という字は、「耳」+「目」そして心と書く。つまり相手の話は耳と目と心を使って聴くことが大事である。

石原 あい- 毎年、全国から集まった100人の高校生が、100人の名人の所へ一人で行って聞き書きをしてレポートにまとめるという「聞き書き甲子園」という活動があります。
見ず知らずの名人、ほとんどが60歳以上の高齢者にまず電話し訪問日を決めて、当日は電車やバスを乗り継いで山の奥へと一人で出かけます。
会った瞬間からテープを回して取材を始めるのですが、助けてくれる大人は誰もいません。
時には、方言がきつくて何を話しているのかよく分からないことも多々あるそうですが、それでも高校生は諦めず真摯に、名人の人生や仕事について聞き続けます。
名人達は取材の中で、一生懸命に親身になって話を聞かれることがだんだんと嬉しくなり感謝の気持ちでいっぱいになるとの事です。
この高校生たちは、聴くという行為を通じで自らの心を開き、聴く事から他者との接点を見いだし社会へと繋がっていく、と評価されています。
相手が発する言葉の印象だけではなく、聴く心の持ち方が大切だと感じました。
- 心を楽にするための言葉 「人より損をする」

工藤 正悟- 仕事で忙しかったり、嫌なことが続いたりすると心の余裕がなくなってしまう→心の余裕がなくなってしまうと、他人の行動が目につくようになる→批判や悪口をいいたくなる→心の余裕がなくなる→他人の行動が...という負のサイクルに陥ってしまいます。
人は無意識に平等を求めるものなので、自分の努力の分だけ他人にも努力を要求してしまいます。
そうすると、批判や悪口を言ってしまい、負のサイクルに陥ってしまい、心が疲れてしまいます。
初めから「損をする」ということを決めてしまえば、他人の行動が気にならなくなるので、負のサイクルに陥らなくなります。
他人の行動が気にならなくなるので、楽に生きることができます。
- 悲観主義は感情に属し、楽観主義は意志に属する

齋藤 章子- 思考(考え方の癖)は意志の力で変えられるということを示している。
IQ(知能指数)に対してEQ(心の知能指数)が取りざたされている。
具体的には、感情をコントロールする能力、他者に共感する能力、挫折を克服する能力のことである。
IQは生まれ持っての能力なので後天的に高めることはできないが、EQはトレーニング次第で高めることができる。
また人生の幸福度への影響がIQは2割程度に過ぎないが、EQが人生の幸福度に与える影響は非常に大きいと言われている。
ストレスも気持ちのあり方一つで解消するそうだ。
困難な状況に対して、これは自分への試練だ、ありがたいと感謝の気持ちを持つこと、これだけでストレスは解消に向かう。
思考、考え方の癖を意志の力で変える。
一見、難しいようだが、まずは感謝するという方法から取り組んでみたい。
- 努力は人に言われてこそ努力

榎本 恵亮- 落語の世界で師匠が弟子によく話す言葉だそうです。
目標に向かって努力をするのは当然ではありますが、自分自身が思っている努力のレベルでは自己満足のレベルであり本当の努力ではなく、人から「努力しているな」と言われる、認められてこそ本当の努力に値するという事だそうです。
お笑いの世界でもビジネスの世界でも一流の方々は人より2倍・3倍の努力を見えない所で行っており、人より努力の量が多いため、相手に努力していると言われる・認められるのだと思います。
マンガキャプテン翼の主人公も授業中でも通学中でも常にサッカーボールを足で扱って常に努力をしている姿を見た時には感嘆した覚えがあります。
それがどんな世界でも成功をもたらすのだと思います。
- 信頼にかかるコストを惜しまない

永山 友梨子- ある人が亡くなった父親のクレジットカードの解約手続きを行ったとき、解約手続きの書類には「本人が署名して下さい」このような言葉が書いてあったそうです。
その方のお母様は、天国まで署名を貰いに行けということかと立腹されました。
このクレジット会社は、同じことでクレームを過去にも貰っていることでしょう。
それを上層部はオペレーターが処理すればいいことだからと問題を放置しているのかもしれません。
最近では、マクドナルドが食の安全に関する信頼を大きく失いました。
しかしながら信頼回復のためのコストを十分なほどかけているかといえばそうではないでしょう。
信頼を築くには多くの時間を費やしますが、失った信頼を取り戻すにはさらに多くの時間とコストがかかることを肝に銘じなければならないのといえます。
- 直感を磨く

幕内 彩乃- 最新の心理学の研究によると、直感は意思決定に役立っているという事。
その理由は3つ。
1つ目は直感は大量に蓄えられた知識を元に、非常な早さで結論を導くから。
2つ目は全くこれまで経験のない新規な状況においては、その場で一番先に浮かんだやり方が案外上手くいくから。
3つ目は直感に従って行動すると最も後悔が少なく、たとえ良くない結果になったとしても、納得のできるものだから。
以上の理由から、直感を磨くことは大切である。
- 志を高く

野本 理恵- ソフトバンクの学生向け会社説明会で孫正義氏が言っていた言葉です。
高校一年生で、竜馬伝より刺激を受けて、世の中のために21世紀に何か大きなことを成し遂げたい!という高い志をもって、アメリカに留学しました。
その志も素晴らしいですが、彼がこの夢を達成するために人生50年計画を建てたそうです。
20代で名を挙げる、30代で軍資金をためる、40代で勝負をかける、
50代で世にビジネスモデルを提唱する。60代で次の経営者に
バトンタッチする。
そして、プレゼン中に一番力強く言っていたこと、「私はだれにも負けない努力をした」
高い志と、達成するために計画・継続、そして、誰にも負けない努力をする。
これが成功する大きなポイントだと思いました。
- 達成ではなく経験を目的にする

柴崎 誠- 一歩踏み出そうと思ってもなかなか勇気が出ない時があります。
それは失敗が怖いからです。
一歩踏み出したら、失敗の可能性が生まれます。
以前に失敗した痛みを知っているなら余計に避けたい気持ちになります。
そのような時には「できるようになること」目的にせず、「経験してみる」ということを目的にしてみます。
どんな結果であろうとたとえ完璧にできなくても成果が伴わなくてもいい。
ちょっとでも経験できれば自分にとって「経験する」という目的は達成したことになるのです。
そうすることで自分を否定せず、自信を失うことなくこれでいいと肯定ができます。
自分でやってみないとわからないことはたくさんあります。
失敗を怖がって何もしないよりは気楽に考えて一歩前進です。
結果がどっちに転んでも目標達成、どんな経験でもすべてが成功となります。
- 今あるもので考えない。必要な資源は必ず手に入ると考える。

丹下 優子- 土ではなく十分な水に根を這わせ、絶え間なく栄養を与えることで通常の500倍もの実を実らせる農法があるそうです。
大切なことは、これから先も必要な養分は充分に与えられると、苗に思わせること。
そうすると若い植物は、自分を信じ世界を信じ、どこまでも伸びようと自ら選択するそうです。
これは人間にも共通する考え方かもしれません。
私たちの成長を妨げてしまうのは
①これくらいで満足という考え
②自分にはできないという自己疑念
そして一番の原因は
③いま存在している養分(才能や時間や資金など)だけを見つめて未来を見通すこと
なのだそうです。
今足りないものを軸に考えることはやめ、これからも養分は潤沢に集まるという前提で、今に全力をかたむけることが大切なのだと思いました。
- 相反することを取り入れよう

永山 友梨子- アメリカのウォルマートは、他のスーパーマーケットよりも多くのレジを設置するなど、お客様と接する面では多くのコストをかけています。
一方、内部的には在庫管理を徹底するなど、極力コストのかからない経営を行っています。
またトヨタも、ハイブリッド車に代表するように、経済面を重視するだけでなく環境にも優しい車の開発を進めています。
このように一方を重視すると一方はないがしろにされると思われがちなことも、あえてその両者を取り入れることが、今一番消費者に求められていることなのかもしれません。
- 待て、そして希望せよ

齋藤 章子- フランスの文豪デュマの『モンテ・クリスト伯』という小説に出てくる言葉です。
不遇の時期であっても、志を忘れず準備を怠らず、来るべきチャンスをつかめということですが、この言葉の素晴らしい点は2点あります。
まず、非常に簡潔な言葉であること。
そして、二点目はこの言葉を実践するには、非常に主体的に自分が動くことを迫られるということ。
希望するには、自分の目標・ビジョンが明確でなければならない、そして待つには、自分のできることをやり遂げている必要がある。
なんとなく調子が出ない時、不安な時、立ち止まっている時。
この言葉を思い出すことで、行動を起こす原動力となります。
- やりたいことはやりたくないことからみえてくる

江原 智恵子- やりたいことをみつけるには、やりたくないことを明確にして、その上で目標を紙に書きだすと必ず実現するのだそうです。
やりたくないことを消していくとやりたいことが残り、やりたくないことの裏返しがやりたいことだったりもするので、まずは、やりたくないことを紙に書き出してみると、自分がやりたいことが何かが見えてくるのだそうです。
実際にやりたくないことリストを作ってみると、自分でも認識していないことが見えてきます。
目標を実現するためには、やりたくないことリストに挙げたポイント回避しながら、いかにやりたくないことをやらないかが重要になってくるのだと思います。
- 聞かれたことに答える

丹下 優子- 「○○さんと連絡とれた?」と上司に聞かれた時「今日電話したんですけど、出張中でうんぬん・・・」と、状況や背景を先にこたえてしまうことはないでしょうか。
質問している側からすれば、まず聞きたいことはYesかNo。
逆に、叱られているような環境では、理由を聞かれているのに「すみません・・・」と謝ることしかしないと場面も多くありそうです。
まずは、『聞かれたことに答える』
お客様との会話の中でも、お客様が知りたいことは何か?質問をしている意図は何なのか?を常に念頭に置きながら、スムーズかつシンプルな会話をこころがけたいなと思います。
- 謝ることは危機管理になる

石原 あい- 日本人はよく謝る人と批判されたりしますが、これもコミュニケーションの一つと考えればどうでしょうか。
一言、謝られるとなんとなく納得し、なんとなく許してしまう、非常に日本的と言えば日本的ですが、これが多くの日本人の感性です。
悪いことをしたわけではないけれど、周囲の期待に応えられなかった時も謝ることで、反感をかったり問題が大きくなることを防げることが多いのです。
「正しいか、正しくないか」とは別に、「今何を言うべきか」を判断する能力はビジネスパーソンに求められる資質と言えるでしょう、と解説されていました。
場を見極めふさわしい対応をする、謝ることも大切なコミュニケーションの一つだと思います。
- 苟日新、日々新、又日新

野本 理恵- まことに日に新たに、日々に新たに、又日に新たなりと読みます。
中国古典「四書五経」の大学という文章の一説です。
常に昨日より新しく、より良い自分になれるように努力しようという意味です。
中国殷王朝の湯王はこれを自分の盤、今でいう、洗面器にこの言葉を彫り自戒の句としたそうです。
先日行われたヨシケイ埼玉さまの経営計画発表会で室伏会長がこの言葉をお話していました。
成功の秘訣は常に現状に満足せずに、常に新しく、成長していく姿勢なのだと思います。
- 記憶力がアイデアのヒントになる

柴崎 誠- 最近では食品や日用品あるいは読む本やクルマや家探しまであらゆる生活情報をネットから得ている人が増えています。
たしかに、これが便利であることは間違いありません。
なかった時代にはどうやって過ごしていたのだろうと思えるほど、今や誰にとっても必需品となっています。
しかし、それらの情報だけに頼って物事を決めるのは危険なのではないでしょうか。
そこには違和感が存在しないからです。
「経験に照らす」というプロセスがない限り、外部からの情報に違和感を覚えるセンサーが働きません。
思考や発想も困難になります。
こういう場合にはこう動くという回路が記憶として埋め込まれているわけです。
そして、その記憶にそぐわない行動をとろうとするときに感じるのが違和感です。
だから瞬間的に危険を察知したり、アイデアのきっかけを得たりできるのではないでしょうか。
- 人がやらないことではなくできないことをやろう

吉田 昇平- 人がやっていないことをやる。
「差別化」という言葉も使い古されてきた今日この頃ですが、人がやっていないことには大きく分けて2種類あります。
「やらないこと」と「できないこと」 です。
自分にしかない仕入れルートや、自分にしかないサービス、自分しか持っていない技術ニッチな事業で生き残るためにはそういったオリジナリティが必要なのです。
- 好きという力

土肥 宏行- ボクシングの元世界王者の長谷川穂積選手。
才能のかたまりだと思っていた彼は、実はプロテストを一度不合格になり、デビュー当初の戦績も3勝2敗と平凡な戦績でした。
あるコーチと出会いその後才能が開花し、世界王者まで上り詰めるのですが、ボクシングは減量があり、収入もそんなに多くなく逃げたくなるな場面がいっぱいあります。
家族ができ、また勝ち上がるにつれ失うものが多くなるほど怖くなるもの。
彼は「プロは好きなことを極める人。好きなことを納得するまで追い求める人。」と言っています。
「好き」という気持ちは自分で思うもので、人に言われて好きになるものではありません。
彼が世界王者になったり、王者陥落後に戦えたのはこの「好き」という力があったからなんだと思いました。
- 相手の立場に立って考えよう

江原 智恵子- この言葉は誰でも耳にしたことがある言葉だと思いますが、実際に実践出来ているかというと出来ていないことの方が多いかもしれません。
例えば就職や転職の際に書く履歴書などを例にとって考えてみると、応募する側としては採用する側の立場に立って履歴書等を作成する必要があると思います。
相手が何を知りたいのか、どんな人材を求めているのかなどを企業が採用広告から発信しているメッセージを読み取ってそれに対してどう受け止め何を思い応募したのか志望する理由を履歴書等に明記するべきであると言えます。
履歴書は志望する企業へのラブレターと言えるのではないでしょうか?
応募の段階からすでにコミュニケーションは始まっていて、相手の知りたいことを的確にとらえた履歴書等であれば書類選考を通過して面接に進めるのではないかと思います。
相手の立場に立って考えるということは
「相手の意図や目的を正しく理解し、高いプレゼンテーションのもとに成果を出す」
ということで、採用の場合で言えばすでに履歴書の段階で判断されているということです。
- 三角褒めは効果的

丹下 優子- 数百人の受講者を集める有名なセミナー講師に『何か手伝えることがありますか?』と聞くと『それでは講演が終わったら、私をほめてほめてほめちぎってください』と言ったそうです。
褒められるという行為は、大人であってもどんな立派な人でもやる気の源泉になります。
さらに、三角褒めは大変効果的。直接ほめるのではなく、"○○さんが素晴らしいと言っていましたよ""いつも頑張ってるってほめてたよ"とうように、第三者が発していたことを本人に伝えると、あ~、私がいない所でそんな事を言ってくれてたんだ・・・と、言葉の信憑性が増し、うれしいという気持ちも増大するのだそうです。
お世辞をいうということではなく、周りにいる人に喜んでもらうように、素直に良いところをほめたり伝えたりすることができたらいいなと思います。
- 信頼は98%。あとの2%は、相手が間違った時の許しの為にとっておく

石原 あい- これは渡辺和子さんの「置かれた場所で咲きなさい」の本の一節にあるものです。
渡辺さんは大学では人格論という授業を教えていました。
人間は一人の人格である。
自ら判断して、その判断に基づき選択、決断し、その決断に責任を持つ。
そういう人がパーソンに呼ばれるに値する。
みんな渡るから赤信号でも渡る、そういう人は人間だけど人格ではない、といった話をしているそうです。
そして人格である限り、あなたと相手は違うし違っていいのです。
私と違うあなたを尊敬する。相手も自分と違う私を尊重してくれる。
その間には絆や愛情が育っていきます。
そして人間は、決して完全には分かり合えない不完全なものです。
それなのに100%相手を信頼するから許せなくなる。
この98%の信頼と2%の許しとは、
「私はあなたの事を他の人よりずっと信頼しているけど、あなたが神様じゃないと私は知っているから間違えてもいいのよ」
ということだそうです。
この2%の許しが、人付き合いの上でもとても大切な事だと思いました。
- 怖がるな、ドキドキしていけ

土肥 宏行- 水揚げ日本一のカツオ一本釣り漁船の漁労長の明神さんの話。
カツオの一本釣り漁船は一年間のほとんどを船の中で暮らし、船員の生活(給料は)は漁労長の判断によって決まる。
カツオ漁師は、その日どこでとれたか互いに情報交換を行う習わしがある。
その習わしに従っていると、常に二番手以下になってしまう。
そんな中、明神は独自の方法論を研究し、ち密な計算とハイテク機材で他とは異なる漁場を開拓し、一人勝ちを狙うスタイルに徹している。
そこだけを聞くとかっこいいが、こければ自分だけでなく船員全員の生活が不安定になる痺れるような状況で、結果を出し続けるために常に自分に言い聞かせている言葉がこの言葉です。
責任と「ドキドキ、もっと楽しむじゃないけど」向かい合う。
- 商品の効果を考える

永山 友梨子- 青山フラワーマーケットの社長である井上英明社長の言葉です。
井上社長はかつてニューヨークの会計事務所で働いていましたが、仕事に面白味を感じられず、退職して起業するに至りました。
始めから花に興味があったわけでもなく、ある日たまたま部屋に花を飾ったところ、花のある空間がいつもより良いものだと感じたことか花の取り扱いを始めたそうです。
井上社長は現在も、様々な街並みを歩き回りいいなと思う場所を見つけると、なぜその場所を良いと思うのか、その理由がわかるまで何度もその場所へ足を運ぶそうです。
私も、自身が提供するサービスが良いものだと感じてもらえるのであればその原因は何か、どうしたらよいものだと思ってもらえるのか考えたいと思います。
- 誠実な姿勢が信頼を呼ぶ

鈴木 正大- 江戸時代の会津藩の藩主、保科正之のお話です。
彼が着任する以前の藩主は、住民に身の丈以上の重税を課すことで、会津藩の石高を増やし、見せかけ上の兵力を高めていたそうです。
保科正之は着任後すぐにこれを改め、会津藩の取れ高に見合った本来あるべき税制に正したそうです。
その結果、年貢の取れ高は偽装されていた2万石分、少なくなってしまったそうです。
しかし、保科のこの誠実さに感動した住民達が、当時隠し持っていた水田を自主的に申告してくるようになり、最終的には、取れ高は2万3000石(実質3000石のプラス)になったそうです。
これは、保科の誠実さが、住民の信頼を勝ち取ったからこそ生まれた結果だと思います。
- まずは周りから信頼される人間になろう月間MVP

丹下 優子- ある会社で大きなプロジェクトが成功した時、部下の一人が上司に言いました。
『部長が織田信長のような采配を下してくれたので、我々は的確な行動をすることができました!』
部長はうれしそうに
『ありがとう!A君のおかげだよ』
と言いました。
このやりとりを聞いていたBさんが同じように
『部長はまるで信長のようです!』
と言ったところ
『何?!では私が誰かに裏切られるとでも?まさか君が裏切り者ではないだろうな?』
と激怒してしまいした。
Bさんは普段から信用できない人物だったようです。
同じことをしても同じことを言っても、周りが受ける反応は変わることがあります。
これは普段の努力とその人となりが影響します。
まじめに、真摯な言動を心がけたいとおもいます。
- 想うは招く

野本 理恵- 先日TEDというプレゼンテーション動画でみた、植松電機の植松社長というかたの言葉です。
植松社長は、現在北海道でリサイクル用のマグネットを作る会社を経営しています。
小さいころから宇宙にあこがれ、
「将来は宇宙界開発。ロケットを飛ばす」
という夢を見ていた植松社長。
子どもの頃に大人たちに言われた
「宇宙は、とっても勉強ができて、とってもお金がかかる。無理な夢を見るのはやめなさい」
という言葉に植松社長は
「できそうな夢しかみちゃいけないのかな?」
「だれが『できない』って決めたのかな?」
と疑問に思ったそうです。
想いつづけることで夢をかなえた社長です。
私たちも「想い」の強さを感じたいと思います。
- 見込6割で意思決定し、残りの4割は行動しながらカバーする

柴崎 誠- 一つ間違えたら永遠に取り返しがつかない。
意思決定などそうはありません。
また絶対に正しい意思決定もありません。
この事実を認識し、見込6割で意思決定し、残り4割は行動しながらカバーしていく習慣をつけていきます。
逆にいうと残り4割をどうカバーするか、多少間違ってもどのようにカバーしていくかが意思決定において大切だといえます。
ある優秀な医師は手術中ドクターに求められるのは100%の正解ではないそうです。
綿密に検証し、ベストと決めた手術法を行っても数%程度不測の事態が起こることがあるといいます。
こんなはずではないというアクシデントにいかに対処していくか、その応用力こそ真の意味での実力だということだそうです。