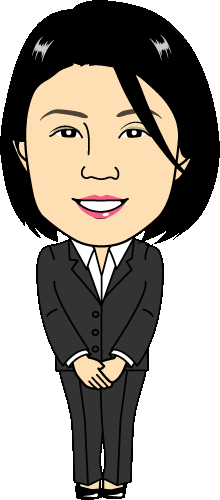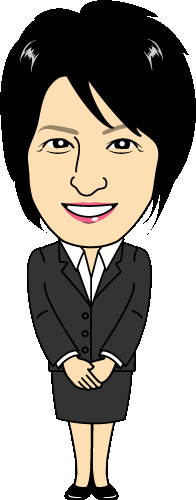スタッフのおすすめ
- 毎日1㎜でも成長するための努力をしよう

江原 智恵子- これはある歌手の方が言っていた言葉です。
この方は今年、毎年NHK主催で開催されているNコンという合唱コンクールの中学生の部の課題曲を担当することになり、自分が書いた曲が中学生たちにどういう風に感じてもらっているのかを直接聞くため全国の中学校に出向いで交流をとってきたそうです。
その中である男子中学生がその歌手の方に
「夢や目標をかなえるために大事なことは何ですか?」
という質問をしたところ
「毎日1㎜でもいいから成長する努力をすることかな、毎日1㎜でもそれが続けばすごいことだよね」
と答えていました。
その方は現在34才位なのですが最近になって歯の矯正を始めたそうです。
世間からも認められている歌唱力をもっていても、もっと歌が上手くなるためにどうすればよいかを考えどんなことでもいいから成長するためにやってみるという姿勢にただすごいなと感じました。
一生懸命がむしゃらに努力することも大事ですが、自分が成長するための努力を毎日続けることが夢や目標をかなえるために大事なことではないかと思います。
- 「高まるために捨てる」

石原 あい- この言葉はニーチェの言葉の中にある「生」について書かれたものです。
「人生はそれほど長いものではない。夕方に死が訪れてもなんの不思議でもない。だから私達が何かをなすチャンスは、今この瞬間にしかないのである。そして、その限られた時間の中で何かをなす以上、何かから離れたり何かをきっぱりと捨てなくてはならない。しかし、何を捨てようかと悩んだりする必要はない。懸命に行動していれば不必要なものは自然と自分から離れていくからだ。あたかも、黄色くなった葉が木から離れ去るように。そして更に身軽になって、目指す高みへとますます近づいていくのである。」
と超訳されています。
一般的によく言われる「何かを得れば何かを失う・捨てる」といった正負の法則というのがありますが、この「失った」と感じるものは全て、本当の意味で今まで必要のなかったものを削ぎ落とし、よりシンプルに、より輝いて生きていくためのみそぎのような作用だと捉えれば、この失う作業はとても崇高な浄化のような作用だと捉える事ができる、と解説している記事がありました。
今までに何を失ってきたかなんて正直記憶にない位に、今が恵まれている状態であるなら、やはりこの言葉の通り、不必要なものは自然に離れていった証拠だと実感しました。
- 直感力を鍛えるには「音」を読む

柴崎 誠- 誰でも何度かは受けて迷惑している営業・勧誘の電話には共通する独特の話し方があります。
話の内容以前の問題として怪しさを感じる人が多いのではないかと思います。
やや大げさにいえば身の危険を察知しているわけで、これは一種の「直感」です。
この相手は誠実か不誠実か、価値観を共有できるか、今後もコミュニケーションを図れそうかといった「人対人」の距離感をつかむことができるわけです。
「それぐらいなら、無意識のうちにやっている」という人がいるかもしれません。
ただ場面によっては話の内容を理解することに一生懸命になりすぎて声だけで違和感を覚えることが減っているケースがあるのではないかと思います。
この直感的な判断力が研ぎ澄まされれば、仕事上の大きな武器になることは間違いなくそれをもとにこちらから出せる情報や協力できる範囲、あるいは次に会うかどうかなどを決めることができます。
- 既存の価値観を疑え

吉田 昇平- 野球のアメリカ大リーグにアスレチックスという、非常に強いチームがあるのですが、このチームにはいわゆる大スターといわれる選手はおらず、選手に支払われる年棒総額は大リーグ30チーム中下から3,4番目という資金力に乏しい低予算のチームなのです。
ではなぜアスレチックスはそんなにも強いチームになったのでしょうか?
それはビリー・ビーンというGMが、打率や打点という既存の評価基準の信憑性に疑問を持ち、独自の評価方法により評価を行い、他のチームで不当な評価を受けているであろう選手や戦力外になってしまった選手を集めたからなのです。
既存の価値観を疑うことで、本当は良いものを安く買い高付加価値を実現する、というのはビジネスにおいても勝利を掴むための鉄則ではないでしょうか。
- 勝たないと、勝てない

土肥 宏行- プロ野球の世界に何十年もの間、何人ものスター選手を育てた人がいます。
今は2軍監督になり、彼が育てた選手は1軍で見事活躍しています。
しかしプロ野球シーズンで最も大事な秋に育てた選手達は失速してしまったのです。
もちろん選手は必死になって戦うのですが、必死なだけでは勝てなかった。
何が足りなかったのか?
それはプロにとって一番大事な「勝つ」という結果への執着心ではなかったのかと監督は考えました。
今まではピッチャーがどんなに点を取られ結果負けても、選手を「育てるため」最後まで投げさせていた。
そこから「試合に勝つこと」を選手に染み込ませようという意図をもった采配に変えました。
本当に大事なことに気づき、今まで成功してきた自分のやり方を捨て、勇気をもって変化をさせた。
今年の秋は失速することもなく早くも結果が出てきたようです。
- 説得から納得へ

永山 友梨子- 家族経営で杉山フルーツを営む杉山清さんが、生ゼリーという商品が人気商品になるまで常に心掛けていたことは、説得では誰も動かない。
お客様にいかにその価値を納得していただくか、という点です。
安売りチラシのようなものは、お客様に安いから買ってくれ、と相手を説得して購入に至らせようとするものです。
杉山さんは、このような説得ではなく、お客さまに価値を納得してもらうことが重要なカギであると述べています。
また、価値を作り出す上で、その商品に「こだわり」をもつことがありますが、このこだわりについても、お客様の共感が得られるものでなければ単なる説得にしかならなくなってしまう点に注意しなければならない、ということです。
杉山さんはお客様に納得してもらう努力を惜しむべきではないと述べています。
私たちもお客様に納得してもらっているか、独りよがりの説得となっていないか常に考えてみるのはいかがでしょうか。
- 「打ち解ける」と「信頼される」は別物

鈴木 正大- 元営業マンの方の本に書かれていた言葉です。
その方は、若いころ、お客様と打ち解けることはできても、なかなか仕事の話に結びつかないことに悩んでいたそうです。
それから、自身のお客様との会話の中で、何が足りなかったのかを改めて考え直して、あることに気づいたそうです。
それは、普段の会話の中で、「目的」をもって会話をしていなかった、ということです。
友人との雑談と違い、ビジネスの場で会話を交わすことには、常に、何かしらの「目的」をもつことが必要だということです。
日々の雑談の中で、目的意識を持ち、「○○の件はいかかがですか」とお客様に伺うようにした所、段々とお客様からも信頼され、仕事の話もしていただけるようになったそうです。
- やりがいとは見つけるものではなく自らの手で「つくる」ものだ

石原 あい- この言葉は、元ライブドア社長の堀江貴文氏の著書にあったものです。
著者が以前、懲役を受けて服役中に与えられた仕事は、無地の紙袋をひたすら折るという仕事でした。
担当から折り方を教わり与えられたノルマは一日50個。
始めはたったの50個、と思ったそうですが、やり始めると意外に難しくノルマを達成するのもギリギリで悔しい結果でした。
どうすればもっと早く、うまく折ることが出来るのか、教わった折り方や手順には無駄があるのか、折り目を付ける時に紙袋の角度を変えてみてはどうか、など色々な自分なりの創意工夫をこらし三日後には79個折ることが出来て単純に楽しいし嬉しいと感じたそうです。
仕事の喜びは、こういう所から始まるのだと思います。
仮説を立てて実践し試行錯誤を繰り返す、そんな能動的なプロセスが与えられた仕事から作り出す仕事へと変わっていく。
やりがいとは、業種や職種で規定されるものではありません。
「仕事をつくる」とは何も新規事業を起こすことだけを指すのではなくこの能動的なプロセス自体が「仕事をつくる」ことだ、と述べています。
やりがいの感じ方は自分の価値観に左右される所が大きいと思います。
人に左右される事なく、この自分基準をしっかりと持ち改めて「自らつくっていく」事の意味を感じた言葉でした。
- たった一人の「あなたのために」

山田 祐子- これは、農業・土木建設・林業等の産業機械メーカー筑水キャニコムの代表取締役会長包行均さんの言葉です。
「ものづくりは演歌だ」というのが、モットーで、ものづくりの出発点は'ぼやき,にあるといい、困っているユーザーの思いに耳を傾け「義理と人情」でものづくりをするのだそうです。
そんな'ぼやき,を拾う為、営業マンにはユーザーの感想をビデオで撮ってくるくることが課されていて、そのビデオの中から生まれた製品もあります。
草刈り機を購入したが、土手は草刈り機が登れないので手で草刈りをしていたというぼやきから、1年がかりで社内の反対を説得して、4輪駆動の草刈り機をつくってしまったという。
その草刈り機を使ってみたお客様は「覚えていてくれたんだ」と大変感激され、当時で140万と高額にもかかわらず購入してくださった。
そして口コミで話が広がり、年間1000台売り上げる程になったそうです。
その後も、たった一人のあなたのためにと作られた製品は増えていき、国内のシェアートップにまでなったということです。
ちょっと、古臭い感じもしますが、ものづくりの原点は「あなたのために」そして「あなたの笑顔をみるために」作り上げていくものなのかなと思いましたので、本日の推薦する言葉としました。
- 知っていても行動しない人が9割

野本 理恵- アイスバケットチャレンジというものを知っていますか?
ALSという難病の周知と寄付を募るアクションの連鎖です。
ネット上やニュースで氷水をかぶった動画が賛否両論ですが、ある友人は指名を受けて氷水をかぶりました。
もちろん寄付もですが。
その時のFBで「みんなこの動画を見ていいねと押したかもしれない。」でも実際に寄付する人が何割だろうか。見て、称賛したり、非難しても結局『行動しない人』が9割だ。多くの人が知っていて行動しない9割になっている」ということです。
これは一例にすぎません。
様々なことの中で「知っていても行動しない9割」にはなりたくないと思います。
人ぞれぞれの小さな行動でつなげていきたいと思い、この言葉を推薦しました。
- ホスピタリティが信頼を生む

永山 友梨子- オリエンタルランド第1期正社員の福島文二郎さんは、ホスピタリティが予想外の感動を生む、そして予想外の感動を受けたお客様は、その人に対し、この人は信頼できるという気持ちを抱くと述べています。
ホスピタリティとは、お客様に対する主体的な思い遣り、すなわち相手の立場に立って、共に考えてあげる気持ち・心・言動を指すそうです。
近いもので"サービス"がありますが、サービスはお客様に対して必ず履行・提供しなければならないものであってサービスは作業レベルなどマニュアル化が可能なもの、ホスピタリティはマニュアル化できないものなのだそうです。
このサービスについて言えば、そもそもお客様に対する思い遣りの観点から作られた仕組みであるため、ホスピタリティによってサービスを改訂することが大切と言えます。
また、ホスピタリティには気をつけなければならない点が2つあります。
一つは、ホスピタリティが相手に通じるためには思うだけではだめで、行動しなければならないのだそうです。
もう一つは、ホスピタリティの心は、事務所の清潔さなどからでも、すなわち直接人を介さなくても通じてしまうという点です。
最後に、魅力的な会社とは、そこで働く人がホスピタリティの心を持っている会社だそうです。
自分がどのような応対を受けたらその会社のファンになるか、今一度考えてみたいと思います。
- 情熱が人を呼び寄せる

鈴木 正大- 私の学生時代にお世話になった大学教授の話です。
その方は、大学教授にしては珍しく、自分の書く本の執筆を補佐する、アシスタントを雇っていました。
私も珍しいな、と思い、そのアシスタントの方に経歴を聞いてみたのですが、よくよく聞いてみると、その方は、出版社の出身で、以前は、教授が出版をされる際に、長年、担当者として一緒に仕事をしてきた間柄だったそうです。
そして、長年一緒に仕事をしていくうちに、夜遅くまで熱心に研究をしている教授の仕事ぶりに共感し、「この人と共に働きたい」と思い、自分が所属していた出版社を辞め、今は教授の下で働いているのだそうです。
今では教授にとって欠かせない存在になっていますが、その方が、決して教授から声を掛けたのではなく、自ら教授のもとへやってきた、というのは、教授の熱心な仕事ぶりがそうさせたのではないかと思います。
私もお客様にとって、そのような存在になりたいと思います。
- 本物の感動に変える

江原 智恵子- 私たちのまわりにはたくさんの感動があふれています。
音楽や映画なども基本的には誰かを感動させてり何かを伝えるために作られています。
感動と勘違いしやすいものに熱狂がありますが、熱狂は冷めてしまえばそれで終わりで長くは続きません。
しかし本物の感動はいつまでも心に残るものです。
私たちもお客様に感動を与えられるような仕事ができたら最高ですが、言葉で言うのは簡単ですが実際はものすごく難しいことだと思います。
いつまでも人の心に残るような本物の感動を作る為には、まず自分が何かに感動した時に、なぜ自分がそれに感動したのかを突き詰めて考えるのだそうです。
例えば好きなアーティストがいるなら何に感動し何が好きなのかを突き詰めて考えるのだそうです。
突き詰めて考えていくと感動の根本にあるものが見えてきます。
自分自身が感動したことを突き詰めて考えることによって、目の前のお客様に対して自分がどのように接したりサービスを提供すれば感動していただけるのかということをはじめて考えられようになるのではないかと思います。
- 問題を見極める。できる方法を考える。

丹下 優子- あるビルのエレベーターは、持ち時間が長いとクレームの的でしたが、ある事をしたことで、そのクレームを一気に減らすことができました。
そのある事とは、エレベーターホールの壁を鏡に替えること。
人は鏡があれば無意識に自分をチェックするものです。
エレベーターの待ち時間は変わらなくとも、意識を他に集中させ待っている時間を短く感じさせることで、クレームを解消したのです。
困っている事の相談を受ける時、その不安や不満の本質は何なのかを考え、発想や角度を変えてできる方法をみつけることで、例えばエレベーターの構造まで変えなくても、問題を解決することはできるのだと思います。
- 「運とは口説くもの」

山田 祐子- サッカー日本代表キャプテンの長谷部選手は、人からよく「運がいいね。」と言われるそうだ。
しかし、「運というのは、何か行動を起こさなければこないものだ。」と思っている。
普段から、やるべきことに取り組み、万全の準備をしていれば、運が巡ってきたときにつかむ事ができる。
多分、運は誰にでもやってきて、それを活かせるか、活かせないかは、それぞれの問題なのだと思う。
以前代理人から、アルゼンチンのことわざを教えてもらった。
「スペイン語で運(la suerte)は、女性名詞。だから、アルゼンチンの人達は、『運を女性のように口説きなさい。』と言うんだ。何も努力しないで振り向いてくれる女性なんていないだろ?それと同じで、運も、こちらが必死に口説こうとしないと振り向いてくれないんだ。」
と、ユーモアがあって、堅苦しくなくて、長谷部選手はこのアルゼンチンのことわざを一発で好きになったそうだ。
私も運を味方につけるくらいの努力と万全の準備をして運を待ち続け、運が巡ってきたら、あの手この手で運を口説き落としたいとおもいます。
- 「とりあえず」ではなく「まず」と言ってみる。

野本 理恵- 99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ
という本の中に書いてありました。
筆者が新入社員だった頃、先輩から色々な仕事を任されていた時、自分自身は気づいていませんでしたが、
「じゃあ、とりあえずこの資料作っておきます」という「とりあえず」という言葉が口癖だったようです。
そして、ある日先輩から「お前の仕事は「とりあえず」のやっつけ仕事か!」と指導を受けたそうです。
「じゃあ、なんて言えばいいんですか」と反発した筆者に「「まず」というんだ。そしたら「次」と続くんだ」と先輩は言ったそうです。
これによって修正前提のような「とりあえず」から、次のステップを意識した「まず」の仕事になるそうです。
言葉の少しの差ですが、「言霊」ともいうように言葉が仕事のモチベーション、品質です。
自分も意識して「まず!」と言ってみようと思います。
- 「速さ」だけではなく「早さ」を心がけよう

柴崎 誠- 「仕事の時間を早める」ということは、かける時間を短くするだけでは達成できるものではありません。
効率的な仕事をするために重要なのが、着手を早めることと抱えている業務の優先順位をすぐ終わるもの⇒大事なものの順番にしてみるのです。
重要性の高いものを優先するのは普通のやり方ですが、それらはたいてい時間がかかるケースが多いものです。
そこですぐ終わるものから先に終わらせてしまう、という優先順位づけをしてみると、順序を変えただけなのに仕事がスムーズに進んでいきます。
このときに大切なのは、すぐ終わる仕事を「完全に終わらせてしまう」ことです。
進捗率99%ではなく、100%にしてしまうことが重要です。
絶対に完了してしまうことを条件に優先順位をつけてしまえば、想像以上に仕事がはかどるはずです。
- 結果は数年遅れてくる

吉田 昇平- 昔ゴールデンタイムにテレビ放送されていて、大人気だった新日本プロレスは、一時期倒産寸前までいきましたが、近年大復活を遂げ、集客人数は右肩上がりです。
なんとなく世間の認識では、最後のブームであった闘魂三銃士のブームが終わり、不人気になったため、テレビ中継が無くなり…という流れですが、実は闘魂三銃士のブームが始まったのは、ゴールデンタイムの放送が終わった後でした。
悪い要素が出てきても、既存のファン(顧客)がいれば、すぐには業績は悪化しないのです。
そこに騙され、次のスターや新規のファンが出てこなかったため、三銃士ブームが去った後、経営が一気に傾きました。
今の業績の良し悪しに一喜一憂するのでなく、良い時は悪い芽が育っていないか、新規の顧客が獲得できているかを、悪い時はいずれ結果が出ると信じて徹底し続けることが出来ているかを注視しなければいけないのです。
- 準備の差が勝負の差となる

土肥 宏行- 北京オリンピックで金メダルに輝いた女子ソフトボールの斉藤ジャパンですが、世界の頂点に立つために、世界一の準備をしていたようです。
彼女たちは世界一の練習をして準備をしていました。
ただ中国では野球はマイナースポーツ。
球場の設営が非常に悪かったそうです。
それを事前に察知した監督の斉藤は選手を事前に球場に前入りさせ念入りに球場の凹凸を調べさせたそうです。
それに加え何か見落としはないかと選手に確認すると、誰かがスタンドの照明が眩しすぎるという話に。
そこで照明が眩しくないナイターに使えるサングラスを用意し、着用を義務付けました。
サングラスで金メダルになったわけではないですが、準備に準備を重ね、もうやることがないぐらい準備をして普段通りの力が発揮できたのではないでしょうか。
ちなみに4位だった野球の星野ジャパン。
イージーフライを2球エラーした選手の帽子の上にはサングラスが…。
どうやら着用していなかったようです。
- 生きるコツは、「できるだけ好きになる」「生まれてきた目的を考える」

清水 真海- 本当は、この世は楽しくて楽しくてしかたがないはずです。
なぜなら、仕事は相手への効果であり、善意に基づき行われるからです。
世の中にあるもの、遭遇するもの、その全てに喜びはあります。
無いと感じるのは、そこにない訳でなく、まだ見つけていないということです。
また、人間として生まれてきた目的は、人の役に立つためではないでしょうか。
人に迷惑をかけ、失敗も多い人生ですが、全て、社会に役立つための糧と思えば、合点が行きます。
学べば、頭が良くなり。働けば、成果が出ます。
忙しくて、道を見失いそうなときは、生きる目的を考え、いかなるときもしっかりと自分の人生を歩んでいきたいです。
- 足して二で割る案は最悪になる

江原 智恵子- 日本人は和を大切にする人種であると言われます。
例えば会議で両極端の案が出ると、議論を闘わせるよりもその二つの案を折り合わせようとする傾向があります。
こうして出された結論は革新性も斬新さもない、どこか中途半端でインパクトのないものになってしまいます。
これでは会社を前進させたり、危機を脱するための武器にはならないと思います。
まるく収めようとしすぎないことも時と場合によっては大事なのではないでしょうか?
- 一番に動く

丹下 優子- 江戸時代、明暦の大火という大火事が発生しました。
それを知った商人の河村瑞賢は、即座に自らの家財を売り払い、大金を手に山ごと木材を買い占めました。
江戸の火事がおさまり再建が始まった際、瑞賢は手にしていた材木を使って莫大な富を得ることができました。
この話を聞いて、ずる賢い人だなと思うか、優れた実業家だと思うかは人それぞれだと思います。
しかし、いつの時代も一番はじめに行動を起こした人のみが大きな成功をおさめることができることは否定できない現実です。
何かを成し遂げたいと思ったら、アンテナを張り巡らし一番に動ける状況を整えましょう。
- 決意は伝えなくとも伝わる
うまくやろうと思わずに全力でやる 
石原 あい- うまくやろうとしすぎると、過程にすら評価を得たいと思い人目を気にするようになり、不要な努力や思いが集中力を低下させ、評価がなければやる気がなくなるといった性格を人に見透かされると、この人本気じゃないなと思われて応援や手伝う気持ちも引いてしまう。
全力でやることの大切さは、結果だけを目指してなりふり構わずに集中していることで、その一生懸命さに心を打たれ応援したくなるからです。
そして、私は決意しています、本気です、と言っても誰も評価はしてくれません。
目先の事を考えず全力で一生懸命にやっていれば、その人の本気が伝わり人の心を突き動かし応援を受け手助けされる様になるということです。
- 改善は巧遅より拙速を尊ぶ

吉田 昇平- これはトヨタの理念の一つで、改善は時間をかけて上手にやるより、ヘタクソでもいいからとにかく早くやるべきだという意味の言葉です。
上手くやろうとすればするほど準備に時間がかかるものです。
時間をかけて上手く出来たとしても、その時間を失ったことによる機会損失を埋められないことも多々あります。
そのため、とにかくまずはやってみて上手くいかないところはその都度直す。
という方法を選ぶことが改善を効率よく進める方法なのです。
- むずかしいことをやさしく やさしいことをふかく ふかいことをおもしろく

土肥 宏行- この言葉は小説家・劇作家として有名な井上ひさしさんが、表現者として大事にしていたことです。
「むずかしいことをやさしく」
言うには、中途半端な知ったかぶりではできません。
難しい術語を並べて煙に巻いて誤魔化したり、上辺だけをなぞって子供騙しをしたりでは通用しません。
「やさしいことをふかく」
言うには、その事の目的や本質をきちんと理解している必要があります。
「ふかいことをおもしろく」
言うためには、聞く側の立場に立って考えることができなければなりません。
私たちの仕事は言葉を使いますが、伝えたいことが相手伝わるということが大事です。
言葉を使うに当たって頭の中に入れておきたい言葉でした。
- 「場」を求める

永山 友梨子- これは、アナウンサーの安住紳一郎の資質を示す言葉として用いられた言葉です。
アナウンサーはニュースやバラエティなど様々な場面に応じて言葉を巧みに用いますが、安住さんは自身が元々話術に長けていたという訳ではなく、言葉を巧みに使う方法を意識的に取得したそうです。
彼の相手の話を巧みに引き出す話術は、彼独特の言葉の重みが伴うようになり、自身もその強みを活かせる「場」を求めていると評されています。
このように、自分強みを磨くこと、そしてそれを活かせる場を求めることを反復的に行うことで、自身の置かれた仕組みにおける場の充実を図ろうと考えているそうです。
自分自身の立場に置き換えても、自身の強みを理解し、強みに対する努力の積み重ねを怠らないことで、場の充実を図る事ができるのだと思います。
- 「疑問点をピックアップ」

鈴木 正大- 先日読んだ本に、書いてあったことです。
そこでは、学校の試験と仕事との違いについて、次のように書かれていました。
「学校の試験は、完全な文章であることを前提に、問題を解くものです。一方、不完全な資料であることを前提に、自分で調べていくのが仕事です」。
その本では、仕事をするうえで、相手から与えられた資料を一通り見渡しても、よくわからなかったら、いい意味で「相手がわるい」と思うことも必要と書かれていました。
ここで大事なことは、
「最初からすべてを理解しようとするのではなく、まずは、疑問点がどこにあるのかをピックアップする」
ということです。
これは、すべての仕事に繋がる、仕事をするうえでの第一歩になるのではないかと思います。
- 自分が未熟だと他人が未熟に見える
成長する程、相手の強さが見えてくる 
石原 あい- 成長すると一口に言っても心の成長を計ることは難しい事だと思います。
自分は未熟だから駄目だと考える事はよくありません。
その未熟さを受け入れるからこそ、一生懸命やり、いっそう努力する事もできる、自分の未熟さを受け入れる強さがとても大切であると書いてある記事がありました。
そして、成長の度合いを計る時、なぜか殆どの人達が、毎日の中に発生する「歓び」「感動」「期待」等のうれしさ系の感情の数量で計ろうとする落とし穴があるそうです。
成長度はうれしさ系の感情だけでは決して計れません。
不安や迷い、恐怖心や警戒心を知る事、そしてそこから抜け出そうともがく事を止めなければ人は成長し続けていくという事です。
どんな人でも良さがあり強さがある、それに気付いて尊重する事が自分の強さとなって成長に繋がるのだと思います。
- 「客観的に自分を見る技術を身につける」

山田 祐子- 「その日に言われた事と、それにどう対応したのかをできるだけ正確にノートに書きだしてみなさい。」
という上司の指示で始めた事がきっかけで自分自身の問題を客観視できるようになり、すり合わせをすることで言葉の行き違いも少なくなった。
例えば、「今日中」という指示でも、「退社時間まで」なのか「チェックする時間を含めて」なのか、「実は今すぐ」なのかということである。
自分を客観視できるようになると
①問題点を見いだす「現状把握力」
②まず展開を考える「段取り力」
③すり合せをするなど確認をする作業で「コミュニケーション力」
④相手との距離を縮めることで気持ちをセーブしない「素直力」
⑤目的意識をはっきり持つ「自己表現力」
がアップし、信頼が増していくということになる。
今の自分の状況を変えるきっかけとして、「自分を客観的にみてみる」ということは、有効な手段のひとつではないでしょうか。
- 「ゼロは何倍にしてもゼロだが、1あれば、改善して増やすことができる」

野本 理恵- この言葉は、楽天の三木谷社長の言葉です。
1990年、楽天市場が開設された当初は13の出店30程度のユーザーで月商13万円という厳しいスタートを切りました。
大手競合も多い中、誰の眼からみても「成功はない」と思われた楽天市場。
そんな時三木谷社長が言った言葉が「1あれば、改善して増やせる」ということでした。
「なぜ選ばれないかという小さな理由を改善していく。」
メディア等から受けるイメージとは違う一面を感じる言葉でした。
私たちの仕事においても、「革新的な仕事術」などなく、やはり小さな当たり前のような習慣や癖を見直し、改善していくことが一番の近道なのではないでしょうか。
- 人のために働くと大化けできる

柴崎 誠- これはアマゾンの立上げに参加した土井英司さんの言葉です。
会社のために働く、つくすというと会社サイドにとって都合のいい人物になると思われがちですが、土井さんは上司の思惑を超えて会社のために働くというのを課したそうです。
アマゾンの場合、上司以上に取引先である出版社との関係が大切だったそうです。
他にも出版社と書店を結ぶ問屋のような取次先も大事な存在です。
最初は会社のためにやったことが取引先をも巻き込んでいく。
すると会社のためだけではなく、次には取引先の人のためにがんばるようになる。
取次先とのバランスを取るなかで、次第に視野も広がっていき、自分にために働いているときよりも何倍も心地よくはるかに大きな成果を上げる「喜び」を与えてくれることを仕事を通じて体験したのだそうです。
- 自分に向いている仕事など、一生わからない

清水 真海- 本日紹介する言葉は、船井総合研究所、元代表取締役会長の小山政彦さんの言葉です。
自らの天職を知るためには、「自分に合う仕事を探す」のではなく「仕事に自分を合わせる」という視点が必要です。
どんな仕事でも一定期間はひたむきにただ打ち込み、人から感謝されるレベルになってその仕事が楽しくなった時に、初めてその仕事が"天職"となるのです。
天職とは、"天から与えられた仕事"ではありません。
己を知り、己と向き合う中で結果として掴めるものなのです。
ところで、仕事の種類はさまざまで、お互いの職分もそれぞれに異なるけれど、それが仕事として成り立ているのは、社会の求め、必要があるからです。
たとえ小さな仕事でも、それがなければ会社が困ります。
そうした仕事の意義、尊さを自覚して、どんな仕事にも誇りをもって取り組み、力を尽くす所存です。
- 追いかけるより、引き寄せよう

江原 智恵子- ある女性フリーライターの話ですが、彼女は特別な才能がある訳ではなく、営業活動をバリバリとしている訳でもないのに自然と仕事が集まってくるのだそうです。
彼女に仕事をどうやってとってくるのですか?と質問したところ
「頼んでくれた人の期待を裏切らないようにあたり前の事をしているだけですよ。そうすると次も仕事がもらえるんですよね。」
と答えたそうです。
彼女のように仕事やお客様を追いかけなくても自然と仕事が集まってくるのはなぜでしょうか?
頼んでくれた人への感謝の気持ちを忘れずに、期待を裏切らないように仕事をすることが当たり前という考えた方で仕事に取り組んでいると、自分の気持ちが明るくポジティブになるので自然と仕事を引き寄せることができるのかもしれません。
気持ちが与える影響は大きいと思いますので、自分の気持ちがポジティブになるような環境を自分自身で作っていきたいと思います。
- 弱みをさらけだす。

丹下 優子- 歌手のマドンナは有名になる前、生計をたてるためヌードモデルをしていたことがあり、それをマスコミに聞かれた際さらっとこう対応しました。
「それは事実よ。私は骨格がはっきりしているので描きやすいって大人気だったの!」
このマドンナの対応をマスコミは好意的に受取り、その記事によりファンも増えたのだそうです。
誰にでも弱みやコンプレックスは隠したいと思うものです。
しかし人が親近感を感じたり好いたりする瞬間は、実はその人のすごい所を知った時より、そういう弱みを見た時なのだそうです。
隠したいと思っていたことをさらけ出すことで、何か吹っ切れるものがあるかもしれません。
- 真の人間関係に、駆け引きなど存在しない

土肥 宏行- 高校の女子サッカー部の熱血監督と選手の密着取材をテレビで見ました。
練習の時の監督はまるで鬼で、ビシバシしごきます。
ただし練習が終わると親しげに生徒と監督が話している光景になります。
この監督は練習だけでなく、自分の家を寮にして食事をつくり、プライベートの相談にのり生徒にとって良いと思うことを何でも無償でやっているようでした。
こうすれば自分が得をする。
こんなことをやっていては自分が損をする。
そんなことを考えて行動している間は本当の意味での人間関係や信頼は得られないのだろうなと思いました。
- 「何事であれ、最終的には自分で考える覚悟がないと、情報の山に埋もれるだけである」
(羽生善治さんの言葉) 
渋谷 佳代- 仕事をしていると、さまざまな情報や必要な資料が多くなっていきます。
情報に埋もれて、これらのうち、本当に必要なものを探せないでいることはありませんか?
自分で考えて
①必要な情報を明確にする。
②情報を取捨選択する。
最初は、言われたことを言われたままに行うマニュアル人間になってしまいます。
こんな時でも、何かを自分なりに考えたり意識しながら仕事をすることを心掛けましょう。
基礎を固めた上で、後になって、同じ仕事をしたり、類似している問題に当ったときに、その差が生まれてくると思います。
人より半歩でも先を行く仕事をしたいです。
- 1つ1つを乗り越えて、今がある

鈴木 正大- 社会人の先輩から受け取った言葉です。
その先輩は、今でこそ現場の第一線で活躍していますが、新人の頃は、ある程度、いい意味でも悪い意味でも、手を抜きながら仕事をしていたそうです。
そんな中、ある時、今までのやり方では乗り切れない、1つの「きっかけ」になる仕事に取り組むことになったそうです。
それを乗り越えて、今の地位にいるんだ、というお話をされていました。
そこでその先輩が何をしたのかというと、「特に特別な事はしていない」のだそうです。
ただ、目の前に現れた壁を1つ1つ乗り越えていったことで、気が付いたら、今の地位に自分がいたそうです。
あまりにも高望みな目標を抱えすぎず、今の自分が乗り越えられる課題を1つ1つ乗り越えていくことが、理想の自分に近づく第一歩なのかもしれません。
- 失敗は成功のもと

山田 祐子- 発明家トーマス・エジソンは
「私は今までに1度も失敗をしたことがない。電球が光らないという発見を今まで2万回したのだ。」
と言っています。
マイケル・ジョーダンは
「高校時代は代表チームの選考から漏れた。9000回以上シュートを外し、300試合に敗れ、決勝シュートを任されて26回も外した。だから、私は成功した。」
と言っています。
失敗したっていい、失敗しても前に進めばいい、反省して自分の力にしていけばいい。
私は、失敗を恐れるのではなく、失敗が無ければ成功は無いんだということ、そして自分の力を信じて進んでいきたいと思います。
- 「成功するまでやめない」

野本 理恵- 何かにチャレンジしているとき、成果がでないと
「そもそもこのやり方が間違っているのではないか?」
「ゴール自体が誤っているのではないか?」
と思ってしまいます。
しかし、往々にしてこれは自分を守るための言い訳であったりするのかなと稲盛氏の言葉を聞いて感じました。自ら退路を経って、
「成功するまでやり続ける」
ということが大切なんだと思います。
チャレンジするかぎり、成果がでないということはつきものです。
しかし成果がでないことは失敗ではなく、チャレンジを辞めた時が失敗だと思いました。私自身、このエピソードを聞いて少し気持ちが軽くなりましたのでおすすめしたいと思います。
- 見込み60%で意思決定し、残り40%で行動する

柴崎 誠- 1つ間違えたら永遠に取り返しのつかない意思決定など、そうはありません。
また、100%絶対に正しい意思決定もありません。
見込み6割でどんどん意思決定し、残り4割は行動しながらカバーしていく。
そうすると多少間違っていてもどのようにカバーしていくかが、意思決定においては大切だといえるのです。
リクルートには「まず行動しろ」というスピーディーな力を求められる企業風土があるそうです。
そこには「6割はじっくり詰め、残り4割は深追いせずに行動に移れ」という意味合いが込められています。
6割部分が充実しているからこそ、素早く決断して実行できるということです。
また、もしうまくいかなかった場合には、あらかじめストックしてある選択肢のうち、今回は使わなかったものを次回の策として投入することでカバーできます。
- 効率化を考えるときはゼロベースから考える

吉田 昇平- 物事を効率よくするために、無駄をなくそうとしようとする際に、今ある形をイメージして、そこから無駄をなくしていくというようなイメージで考えていませんか?
それでは本当の効率化は出来ません。
効率化を考えるときは、まずゼロから最低限必要な工程をイメージし、その上で必要なチェック項目などを肉付けしていかなければ、無駄というものはなくならないのです。
本当に効率化をしたいのなら、今あるものを一度完全に捨て去って、一度根本から見直さなければならないのです。
- 相手のことだけを話題にする

江原 智恵子- 人と上手にコミュニケーションをとるための第一歩は、まず人間の本性は何かをきちんと理解することだそうです。
人間の本性は何なのかというと、人間はもともと自分の事しか考えていない、自分のことしか関心がない生き物だそうです。
この事を認識した上で、人と会話をする時はどんな話題がよいのかというと、相手の一番関心のあること、つまりはその人自身の事を話題にすればいいということになります。
相手の事を話題にすれば、それは相手にとって一番関心があることですから、まさに人間の本性をついている訳です。
人と会話をする時に肝心なのは、自分がその話題に関心があるかではなく、相手がその話題に関心があるかということだと思います。
- 頑張らなくていい所で誰よりも努力する

丹下 優子- 今年人気となった、東進ハイスクールの林先生が、生徒に一番伝えたい言葉がこれだそうです。
先生の話を例にとれば
「僕がジャニーズ事務所に入りたいと努力したところで、それは不可能に近いこと。ならば適性があると思う塾の講師という職業で、甘んじることなく死ぬほど努力することが人生のベスト」
ということのようです。
職業を選択する時に限らず、自分の得意とする分野で、誰よりも努力する。
そうすることで道がひらけたり成果が出たり、自分自身も幸せを感じることができるのだと思います。
- 何が起きるかを考えると不安になる
何を起こすかを考えるとワクワクする 
石原 あい- 不安に勝つ方法とは、色々あるかとは思いますが、「客観視と座禅」が良いそうです。
へんに押さえたり目を背けようとすると返って不安は巨大化するので、自分の心を客観視する力を高め、思考と現実との違いを見極める、この作業が座禅につながるようです。
座禅までしなくても、今を見つめ今に集中する瞑想する事で、脳の血流をアップさせて考える力が高まるとの事です。
一休さんのフレーズで、「気にしない、気にしない」「ひとやすみ、ひとやすみ」というのがありましたが、これも心を落ち着かせるのに良い言葉だと思います。
そして、「何を起こすか」というところで、自分が起こそうとする行動や起こした行動がワクワクすることに繋がれば、プラス思考となり自分への期待も高まり、自己評価があがり自分の力を信じる事ができるのだと思います。