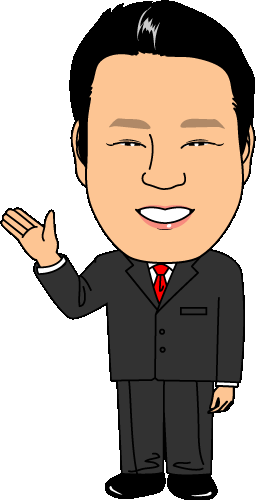SMC税理士法人スタッフの推薦する言葉(令和4年7月)
- 脳のワーキングメモリの負荷

堺 友樹人間の脳は常に大量の情報を処理していますしかしながら、人間のワーキングメモリは思った以上に小さいです。
例えば、授業を聞きながらノートを取ると、ワーキングメモリの負荷が非常に大きいことが分かっています。スタンフォード大学オンラインハイスクールの星校長がテレビに出ていた際に、ノートは授業後に思い出しながら書き出すという行為が、脳科学的に非常に効果が高いという結果が出ていると言っていました。
仕事においてもメモを取る機会が大きと思いますが、聞きながら取るのではなく、聞き終わってからその状況を思い出しながらメモを取ることをおすすめします。
- ありえないことを考える

山村 佳恵最近「SF思考」という言葉が注目されています。
これは未来社会を想像して、そこにある課題について考えるという思考方法です。
SF思考が注目されている背景には、コロナの世界的なまん延といったまるでSF世界のような新しいリスクに企業が対処しなければいけなくなったということがあります。
SF思考の思考プロセスは3段階あります。
- まずは自由に自分で未来の世界を想像してみる
- 想像した未来にはどのような課題・問題があるか考える
- そしてその課題・問題が今ある技術で解決できるのか、できないのであればどのような技術が足りないのかについて考える
- マッチングリスク意識

中澤 正裕マッチングリスク意識とは、商品やサービスが本当に自分にとって役に立つのか、価値のあるものなのか消費者が考えることで、購入を踏みとどまる原因の一つです。
売る側はこれを解消する対策が必要です。心理学の要素を組み合わせると良い効果が期待できます。
- ザイオンス効果
繰り返し接触することで好感度が上がる心理効果 - 返報性の法則
人からタダで何かしてもらった際にお返しをしないといけないと感じる - ウィンザー効果
当事者よりも第三者の意見の方が、信憑性が高いと感じる
欲しいけど購入に踏み切ることができない方へどのようにアプローチしていくか考える必要がありそうです。- ザイオンス効果
- 物事の数字には理由がある。

丹下 優子プリンのパックは3つ組が多く、ヨーグルトは4つが多い。
プリンはおやつという感覚でお母さんと子供2人で食べるから、ヨーグルトは朝食としてお父さんも含めた家族全員で食べるから、という発売当時の理由。新幹線の座席が2列と3列なのも、複数人で旅をする際ひとりぼっちが出ないようにという配慮から生まれたらしい。
たしかに何人でも対応できる。物事の数字にはなんらかの理由があることが多い。
消費者に、より手にとってもらいやすい選んでもらいやすい工夫という観点から、私達の仕事にも参考になるかもしれない。